| 2009年4月から本年2010年6月30日まで掲載の集大成、CD版7月7日完成! | ||
|
CDには「木花-world」、「名木古木」、「さくら-world」のすべてを収録、全1069件の樹木情報(ファイル数 3450個)を満載! 現代の自然環境の一端を樹木を通して次世代に末永く語り継ぐ資料にするためのCD化です。 |
|
| 2009年4月から本年2010年6月30日まで掲載の集大成、CD版7月7日完成! | ||
|
CDには「木花-world」、「名木古木」、「さくら-world」のすべてを収録、全1069件の樹木情報(ファイル数 3450個)を満載! 現代の自然環境の一端を樹木を通して次世代に末永く語り継ぐ資料にするためのCD化です。 |
|
| 03 富士山に咲く ハクサンシャクナゲ(白山石楠花)の花 | |||||
|
所在地 | 富士山の中腹を一周する「お中道」の付近 | |||
| 科・属など | ツツジ科ツツジ属 常緑低木 | ||||
| 見どころ | シャクナゲの花は2ページNO.30と16ページNO.27に掲載されています。「ハクサンシャクナゲ」の花は白から淡い紅色で、内側に薄い緑色の斑点があります。富士山の中腹の暗い針葉樹林内に咲いているので、パッと明るく華やかで綺麗でした。(撮影は失敗しましたけれど) | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.07.15 | ||
| 22.花と間違えてしまいました。シナサワグルミ(支那沢胡桃) の実 | |||||
|
所在地 | 横浜市緑区寺山町291 県立四季の森公園内 | |||
| 科・属など | クルミ科サワグルミ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 花と間違えてしまいました。遠くから見ると25センチくらいの房状の果穂が! 確か4月下旬に撮影した時より大きくなっていましたが、岩田会長に指摘されるまで、気がつきませんでした。堅果には翼が付いていました。 ※シナサワグルミの花は17ページNO.33に掲載されています。 |
||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.08.15 | ||
| 10 黄緑色の球状の花が咲く! カクレミノ(隠蓑) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西4丁目 民家の入り口 | |||
| 科・属など | ウコギ科カクレミノ属 常緑高木 | ||||
| 見どころ | 7ページNO.40に樹形が、11ページNO.39に実が載っています。7~8月に枝先に4~7㌢の花枝を伸ばし、球状に集まった散形の花序を形成し、11月頃実が黒紫色に熟します。日陰でもよく育ち、常緑の葉は艶があって綺麗なので、庭木に良く植えられています。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.07.15 | ||
| 25.連日の猛暑の中、細身で大きいドングリをつけた、マテバシイ(馬刀葉椎) | |||||
|
所在地 | 東京都新宿区内藤町 新宿御苑千駄ヶ谷門付近 | |||
| 科・属など | ブナ科マテバシイ属 常緑高木 | ||||
| 見どころ | 連日35度を超す猛暑が続き、昨夜のテレビは「熱中症死亡者が全国で283人。昭和21年統計を取り始めて空前の記録」と報じていました。「この猛暑は当分続き、秋が短く、夏からすぐ冬に入る」とテレビは言っています。 こちらの老人は果たして今年の秋を見ずに、あの世に・・・、なんて良からぬ心配しながら汗を拭き拭き、御苑千駄ヶ谷門に向かっていました。と、大きなマテバシイの木に黄色く色づいたドングリが鈴なりに生っているではありませんか。♪ちいさな秋みつけた~。樹木の営みのほうが気象庁の予測よりも正確だと思うと、急に元気が出てきました。※マテバシイの花が2ページNO.23に載っています。 |
||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.08.17 | ||
| 01 アルゼンチン国花セイボ(アメリカデイゴ)を現地で撮る | ||||||
|
所在地 | 南米・アルゼンチンのブエノスアイレス市街 | ||||
| 科・属など | マメ科デイゴ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ |
|
|||||
| 撮影者 | 山田紀子 | 撮影日 | 200.9.11.05 | |||
さくいんのページへ戻る
木花-World TOPへ戻る
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
| 19.書体の楷書のようにまっすぐ伸びる、楷樹(カイノキ) 別名コウシボク(孔子木) | |||||
|
所在地 | 横浜市金沢区金沢町212-1 称名寺境内 | |||
| 科・属など | ウルシ科カイノキ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | この樹は日本では数十か所にしか植えられていない、たいへん珍しい樹だそうです。楷の樹は、書体の楷書の文字のように幹や枝がまっすぐに伸び、枝の分かれ方もきちんと整っていることから「楷」の名がついたそうです。花は4月~5月に新葉に先立って咲き、10~20センチの雌花は紅色、雄花は淡い黄色の大型円錐花をつけます。落葉高木なので秋に紅葉したのち、冬には枝だけとなります。中国の孔子廟に植栽されているところから「学問の聖木」とされ、日本には大正時代に渡来しました。 | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.08.11 | ||
| 21.種子が顔を出してきた、ミツバウツギ(三葉空木)の実 | |||||
|
所在地 | 横浜市緑区寺山町291 県立四季の森公園内 | |||
| 科・属など | ミツバウツギ科ミツバウツギ属 落葉低木 | ||||
| 見どころ | 葉が3小葉で枝がウツギのように中空のためミツバウツギ(三葉空木)と名付けられたそうです。ちょうど私が「四季の森公園」へ行った時、果実は先端が袋状になって、ふくらんでおり一部、種子が顔を現していました。袋の中には5ミリほどの種子が入っているそうです。※ミツバウツギの花は21ページNO.20に、掲載されています。 | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.08.15 | ||
| 17 鳥海山麓 奇形ブナの林を散策! ブナ(橅)の原生林 | |||||
|
所在地 | 秋田県にかほ市 鳥海山麓、獅子ケ鼻湿原 | |||
| 科・属など | ブナ科 ブナ属の落葉高木 | ||||
| 見どころ | 奇形ブナの原因は、豪雪、噴火、炭焼きでの伐採などの説があるそうですが、はっきりとはわからないとか。ブナ林のなかには炭焼き釜の跡が50基以上も見つかっていることから、炭焼き説も有力視されているとか。豪雪地帯のため 雪の上から木の枝などを伐採するので、そこから枝葉が伸びて、形が奇形になるらしい。中でも、「森の主」と言われる、幹周り7.62メートルの奇形ブナは、日本では、奇形ブナとしては、日本一の太さで「あがりこ大王」と言われ、幹が上がった所で子に分かれている事から名付けられたそうです。「
森の巨人たち百選」にも選ばれています。久しぶりにたっぷりと森林浴ができました。 ※ブナの木の詳細は22ページNO.20に掲載。名木古木4ページNO.41にこのブナの巨木「あがりこ大王」が登場しています。 |
||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.08.03 | ||
| 30. ナツメのこんな高木見たことがない! 実もたわわに。この持ち主が、なんと~?! | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田東5丁目 塩谷家久さん宅 | ||||
| 科・属など | クロウメモドキ科ナツメ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 先ほど新羽町のお寺に向かってバイクを走らせていたら、美味しそうな実がたわわに生っている木を発見、急停車し戻って撮影しました。その後、その家をチラッと見たら、なんと“盟友のSY・IH家”ではありませんか?! 縁って本当に不思議なものです。彼は3日前、久しぶりに当編集室をわざわざ猛暑の中、訪ねてくださったばかり。 卵形のナツメの実はすでに赤茶系に熟しています。私はまだ食べたことがありませんが、生で食べられ、美味しいそうですね。ドライフルーツや砂糖漬けにもでき、利尿や強壮の薬効もあるそうです。それにしても、これほど豊作ですと、収穫が楽しみであり、一苦労でもあるのでは? SYさん、今年は収穫のお手伝いにうかがいましょうか? 5ミリほどのナツメの小さい花は21ページNO.39に載っています。 |
|||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.9.14 | |||
| 12 3本の葉脈と4本の雄しべがあるのが特徴! オオコメツツジ(大米躑躅)の花 | |||||
|
所在地 | 山形県鶴岡市 月山八合目 弥陀ヶ原湿原 | |||
| 科・属など | ツツジ科ツツジ属 落葉低木 | ||||
| 見どころ | ツツジ科ツツジ属の落葉低木で、秋田県~滋賀県の日本海側の山地に分布します。オオコメツツジは基部から出る3本の葉脈が際だち、花弁は4裂し雄しべが4本あります。よく似ているコメツツジの花の 葉脈は中央の1本が目立ち、また花弁は5裂して、雄しべも5本あります。どちらも6~7月に白い花をつけます。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.08.02 | ||
| 08 9月~10月に真っ赤に熟す。 サンザシ(山査子)の実 | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田東6丁目 新吉田小学校前の道路 | |||
| 科・属など | バラ科サンザシ属 落葉低木 | ||||
| 見どころ | 19ページNO.05に白い花が、19ページNO.36に赤い花が載っています。実の先端が、ちょっと割れて反り返り、まだ花がらが残っていますが、秋には真っ赤に熟し美しい。果実の干したものは、生薬名で「山査子(さんざし)」といい、消化吸収を助ける作用や体を温める効用があり、特に肉類の食べ過ぎに効果があるとされ、また、血をサラサラにして血流を良くする働きもあるそうです。ダイエット効果もあるといわれ、脂っこい料理の好きな人にはおすすめの人気の甘いドライフルーツです。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.07.06 | ||

| 33.ユニークな形の、ハクモクレンの実 | |||||
|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 五島美術館庭園内 | |||
| 科・属など | モクレン科モクレン属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | ハクモクレンの実は我が家の近くでも見ますが、昨日、五島美術館へ行きましたら綺麗な実を見つけましたので、パチリ!! ※ハクモクレンの花は14ページNO.36に掲載されています。 | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.9.18 | ||
| 11 紅や桃色の花が一般的だが、白い花も清楚で良いもの! サルスベリ(百日紅)の白花 | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西5丁目 民家の庭 | |||
| 科・属など | ミソハギ科サルスベリ属 落葉中高木 | ||||
| 見どころ | 6ページNO,29に燃えるような濃いピンクの花が、13ページNO.16に紅葉した樹木、名木古木4ページNO.25に大聖院のサルスベリが載っています。百日紅の名がついているように長~い間花が楽しめます。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.07.15 | ||
| 27.花からは想像できない面白い形の実! リキュウバイ(利休梅) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院道路沿い植え込み | |||
| 科・属など | バラ科ヤナギザクラ属 落葉低木 | ||||
| 見どころ | 春に茶花として愛用される清楚な白い花を咲かせるリキュウバイですが、花からは、ちょっと想像できない変わった星形の実が生ります。最初に見たのは5月下旬ですが、昨日もほとんど同じ状態で、緑色のままでした。多分去年の古い実の抜け殻だと思いますが、2つ3つ茶色で中の実がなくなっている”かさかさ”した実が残っていました。いつ頃に熟して茶色になるのでしょうね? 15ページNO.20に白い花が載っています。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.9.7 | ||
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2010.07.20~09.26 | 掲載27種 |
| 35. 自生地は日本に数カ所という珍種、ヒトツバタゴの実。別名ナンジャモンジャ | |||||
|
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町1957-1 川崎市平和公園 | |||
| 科・属など | モクセイ科ヒトツバタゴ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | モクセイ科の雌雄異株のこの木は、日本の自生地が本州では長野・岐阜・愛知県、九州では長崎県対馬列島という珍しい木です。たまたま川崎市が植樹したばかりの木と出合いました。樹高3メートルほどの木にブドウ色の実をたった1個だけ。台風が去った後の強風に煽られ、その実がじっと静かにしていないのです。ピントが甘いのは、そのせいですからね。 ※ヒトツバタゴの花は「ナンジャモンジャ」の名で1ページNO.10、NO.11に連番で載っています。 |
||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.9.25 | ||
| 32.真っ赤な実をつけ、葉も紅葉し始めた、アメリカハナミズキ | |||||
|
所在地 | 川崎市中原区等々力 等々力緑地公園 | |||
| ミズキ科ミズキ属 落葉小高木 | |||||
| 見どころ | 今年は記録的な猛暑日の連続で、9月も明日から下旬になろうというのに、30度を超す暑さ・・・。例年並みの秋はいつからか、と思いつつ、アメリカハナミズキの並木を見ました。と、その葉はすでに色づき、真っ赤な実が生っています。しかも、実の下には来年の小さな花芽を数個ずつ付け、しっかり来春の準備をしているではありませんか・・・。樹木にとっては、もう秋到来なのですね~。※花が2ページNO.40に載っています。 | ||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.9.19 | ||
| 04 果実酒にすると美味しい、ウワミズザクラ(上溝桜) の実 | |||||
|
所在地 | 横浜市緑区寺山町291 県立四季の森公園内 | |||
| 科・属など | ウワミズザクラ(上溝桜)バラ科サクラ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 花は17ページNO.06に掲載されています。ウワミズザクラ(上溝桜)は高木でしたので、実は小さく撮影されましたが、果実は長さ6~7ミリメートの卵形で、初めは黄色で、熟すと赤色から黒色になります。果実酒にすると美味しいそうです。けれど高木なので、小鳥たちに先に食べられてしまいます。 | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.07.21 | ||
| 24.蕾がまん丸の球形になる! タマアジサイ(玉紫陽花)の蕾と花 | ||||||
|
所在地 | 東京都立川市緑町3173 国営昭和記念公園 花木園展示棟の庭 | ||||
| 科・属など | アジサイ科アジサイ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ | 山地の沢沿いに多く自生。葉の先端は尖り縁にギザギザがあります。両面に短い毛があり、ザラザラとした触感がします。総苞(蕾を包んでいるもの)に覆われた蕾は、直径3~3.5センチの球形で、その姿が名の由来です。やがて総苞が落ちて、小さな両性花と2~3センチの白い装飾花を咲かせます。実は直径3.5ミリの球形で熟すと裂けるそうです。3ページNO.01にガクアジサイの花が、 22ページNO.27にヤマアジサイの花が掲載されています。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.08.16 | |||
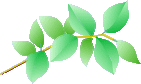
| 13 花の姿がとてもユニーク! ミヤマホツツジ(深山穂躑躅) | |||||
|
所在地 | 山形県鶴岡市 月山八合目 弥陀ヶ原湿原 | |||
| 科・属など | ツツジ科ミヤマホツツジ属 落葉低木 | ||||
| 見どころ | ツツジ科ミヤマホツツジ属。亜高山の林縁などに生える落葉低木です。葉の先は尖らず、花の外に突き出した雌しべは、弓状に象の鼻のように曲がり、3枚の白い花弁が反り返って丸くなります。花期は、7~8月です。よく似ている「ホツツジ」の花の雌しべは、ほとんど曲がらず伸びたままです。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.08.02 | ||
| 29.実はあまり見たことがないけれど? ボタン(牡丹)の実 | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院道路沿い植え込み | |||
| 科・属など | ボタン科ボタン属 落葉小低木 | ||||
| 見どころ | 美しく華麗に咲いた花も、花後はあまり気にされませんが、ちゃんと立派な実が生るのです。秋にはヒトデのような形をした子房の鞘が割れて、中から黒光りした種が見えるようになります。栄養が種にとられてしまうので花が色あせてきたら、早い段階で切り取り、花後にお礼肥えをするのだそうです。そのため、あまり実を見ることがないのかもしれませんね。また、ボタンはシャクヤクを台木にして接木をするので、台木からシャクヤクの新芽が出て繁殖してしまう事もあるので芽を摘み取らねばいけないそうです。 カンボタンの花が13ページNO.36と14ページNO.01~NO.03に載っています。 |
||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.9.7 | ||
写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 37. 高木の枝に見事に咲き競う、オオモクゲンジの花 | |||||
|
所在地 | 川崎市中原区木月住吉町1957-1 川崎市平和公園 | |||
| 科・属など | ムクロジ科モクゲンジ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | きょうは午後から台風一過の青空。10メートルを超える高木に黄色い花が映えます。いったい、この木なんの木、気になる木です。またもや、インターネットの“花の先生”に質問すると「オオモクゲンジ」という珍しい木であることが分かりました。この木は、私の手で一抱えもある太い幹でした。 ※北澤美代子さん投稿のモクゲンジの花は21ページNO.33に掲載、比較してご覧ください。 |
||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.9.25 | ||
| 18.別名をキジュ(喜寿)と呼ばれ高木になる、 カンレンボク(旱蓮木)の花 | |||||
|
所在地 | 横浜市金沢区金沢町212-1 称名寺境内 | |||
| 科・属など | ヌマミズキ科カンレンボク属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 中国固有種で生命力、繁殖力が強いため「喜樹」とも呼ばれます。 木の高さは30メートルくらいにもなる高木です。葉は長さ12~28センチ、幅6 ~12センチの広く互生です。雌雄同株で、雌花は上に、雄花は下に咲きます。開花期は7~8月で、花の色は淡緑色。花径は3センチくらいの球形をしています。実は10~12月。果実は痩果で、長さ2.5センチの長楕円形。これが多数集まり、大きいコンペイ糖のようになる集合果で、さわるとやわらかい。 名前の由来は高木になるので、中国では千丈樹や旱蓮木の名とも。カンレンボクは旱蓮木を日本語読みにしたものです。 | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.08.11 | ||