次ページNO.10へ
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
木花-World TOPへ戻る
| 6.昔は薪や炭材、今は子供たちに人気のクヌギ(檪) | |||
|
所在地 | 東京都八王子市廿里(とどり)町1833-81 多摩森林科学園 ℡042-661-0200 | |
| 科・属など | ブナ科コナラ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 「楽しい木」と書いて“檪(くぬぎ)”。丸くて大きなドングリは子供たちに人気。夏、男の子たちは樹液に寄ってくるカブトムシやクワガタ欲しさにクヌギの木を探します。クヌギは、私たちに数々の楽しい思い出をつくり、残してくれる木です。春、葉が開くと同時に穂のように垂れ下がる黄色い花序。樹皮は写真のように縦にできる割れ目。細長い葉には鋭い鋸歯。これらがクヌギの特徴です。※クヌギの花は17ページN0.7に掲載。 | ||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
| 7.花粉症の原因と嫌われるが、日本の木造住宅建築の重要な建材。スギ(杉) | |||
|
所在地 | 東京都八王子市廿里(とどり)町1833-81 多摩森林科学園 ℡042-661-0200 | |
| 科・属など | スギ科スギ属 常緑針葉高木 | ||
| 見どころ | 幹がまっすぐ伸び、樹高50㍍にもなる常緑高木。勝れた建材のため古くから植林され、日本の樹木のなかでスギが人工造林面積では最大です。秋田杉・吉野杉など各地の気候風土に合ったスギの美林があります。鹿児島県屋久島が世界遺産となったのは、樹齢7000年の“縄文杉”を代表とする屋久杉の存在が大きいと思います。※スギの花は15ページNO.14に掲載。 | ||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
| 8.白藤のような花は香りが良い、ニセアカシア。別名ハリエンジュ(針槐) | |||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目、日大高校付近 | |
| 科・属など | マメ科ハリエンジュ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 6ページNO.32にも載っているニセアカシアはマメ科の落葉高木で、ハリエンジュとも呼ばれます。私が見たニセアカシアは樹高6㍍ほどでした。日本には明治時代に公園樹、街路樹などに用いられています。6月ころ白色の蝶形花を総状に垂下し、よい香りがします。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
| 10.郵便局のシンボルツリーは「タラヨウ(多羅葉)」の木だとご存じですか? | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西1丁目、民家の庭 | ||
| 科・属など | モチノキ科モチノキ属 常緑高木 | |||
| 見どころ | 12ページNO.9に、大木が「名木古木」5ページNO.26に掲載。 | |||
| 撮影者 | 北澤美代子 | |||
| 12.美味しい大きなタケノコを提供してくれるモウソウチク(孟宗竹) | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 第3京浜国道都筑インターへの道路沿い | ||
| 科・属など | イネ科マダケ属 多年生常緑竹 | |||
| 見どころ | 1736年(元文元年)薩摩藩(現鹿児島県)が大きなタケノコを採るため中国からモウソウチクの地下茎を輸入し、栽培したのが最初。以来、北海道南部から九州にいたる全国各地に広まりました。タケは種類が多く、笊(ざる)ル、篭、笠、筆、竿、筆など用途別に使い分け、作られています。晩春に生えるタケノコは、夏には親竹に生長します。この旺盛な生命力は、「地震がきたら竹薮に逃げろ!」といわれる地下茎の根張りに支えられています。近頃、間伐(間引きした竹)の竹での“竹炭”は空気・臭気・水の浄化作用があり、注目されています。 | |||
| 撮影者 | 守谷明子 | |||
| 13.壱岐・対馬・沖ノ島に自生するハイビャクシン(這柏槙)の実 | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町1-45-1 慶応普通部校舎入り口 | ||
| 科・属など | ヒノキ科ビャクシン属 日本原産の匍匐性の低木 | |||
| 見どころ | 常緑針低木。ヒノキ科ビャクシン属。 幹や枝は地面を這うように広がっています。「ソナレ」と呼んで園芸植物として庭園樹、公園樹に使用されています。自生地は壱岐・対馬・沖ノ島とごく限られています。毎日、私はどんな実がつくのかな? きょう7月15日、白い実を1個見つけました。 | |||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
| 14.早春に白い花が咲くコブシ。7月のコブシ(辛夷)の実 | ||||
|
所在地 | 横浜市中区根岸台 根岸森林公園内 | ||
| 科・属など | モクレン科モクレン属 落葉広葉高木 | |||
| 見どころ | 春先に白い花をたくさん咲かせて綺麗だった“辛夷(こぶし)”の花。きょう森林公園で、私が初めて見た木の実、これ、何の実かな? 帰宅してインターネットで調べましたところ「コブシの実」だと分かりました。袋の中に実がたくさん入っていて、秋になると赤い実が出てくるそうです。 ※コブシの花は14ページNO.32、実が10ページNO.27に載っています。 |
|||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
| 15.秋にもう一度観たいクサギ(臭木)の花 | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区下田町4丁目 松の川緑道沿い旧鎌倉街道の道標があります。その角に咲いています。 | ||
| 科・属など | クマツヅラ科クサギ属 落葉低木 | |||
| 見どころ | 樹高3〜4㍍ほどの落葉樹です。クサギはもちろん「臭木」の意味で、葉をもむと独特の臭気がします。ユリに似た芳香に気づかれないようです。また、秋になると花も果実もとても綺麗です。 ※実は10ページNO.38に掲載。 |
|||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町1581-6 日吉本町公園内 | ||
| 科・属など | ホルトノキ科ホルトノキ属 常緑高木 | |||
| 見どころ | 常緑高木。樹高は10〜15㍍、葉は5〜12㌢で、ヤマモモの葉に似ています。古い葉は赤く紅葉しますので、緑色の葉とまじっていて綺麗です。7〜8月に総状の白い小さな花を咲かせます。公園や街路樹に植えられています。※古い葉が紅葉した木は18ページNO19に。 | |||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
| 17.奇妙な形の実がたくさんつく、モクゲンジ | |||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院の庭 | |
| 科・属など | ムクロジ科モクゲンジ属 落葉小高木 | ||
| 見どころ | 白い花のようなものがいっぱい付いているので近寄ってみると、三角形の袋状の実が鈴なりについていました。栴檀の木の葉の様子に、又菩提樹の実に似ている事から別名センダンバノボダイジュ(栴檀葉の菩提樹)と呼ばれるそうです。6月中旬から7月初旬にかけて、枝先に穂状の花序を付け、たくさんの黄色の花を咲かせます。花は開いた当初は、黄色だが、一両日の内に中央のふくらみが赤く色付きます。英名で「ゴールデン レインツリー」と呼ばれ、金色の雨が降るようにはらはらと散るそうです。葉は羽状複葉で、小枝にも粗い鋸歯が確認できます。果実は三室の袋状で各室に1‾2コの種子が入っています。この硬い種子で数珠が作られるそうです。お寺に植えられることが多いようです。「金色の雨」が降る時に出会ってみたいと思います...。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
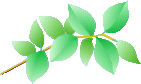
| 19.花糸がこんなに長い、純白のハイビスカス | |||
|
所在地 | 東京都大田区南雪谷1丁目 友人宅の温室 | |
| 科・属など | |||
| 見どころ | 「珍しい白い花が咲いた。花見に来て、花の名前を教えて欲しい!」と友人の電話で、現物の花を見ました。でも、私も花の名前が分かりませんでした。そこでインターネットの“花名辞典の掲示板”に問い合わせ、上記であることが分かりました。ハイビスカスの花といえば、赤か黄色と思っていましたが、こんなに花糸が長い、純白の品種があるとは?! ※黄花と赤花が4ページNO.17とNO.18、連番で掲載。 | ||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
| 27. ココアがお好きな方、現物の木をご存じですか? カカオノキ | |||
|
所在地 | 東京都調布市深大寺北町1-4 都立神代植物公園 | |
| 科・属など | アオギリ科アオギリ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | カカオノキは、葉は枝につけますが、花(実)を直接幹につける“幹生花”というものです。アオギリ科の常緑小高木で高さ6〜10㍍になります。南アメリカ熱帯地方原産で気温28度以上の高温多湿な肥沃地に自生しています。花は、ガクがピンク、花弁が黄色の6弁花。花は一年中咲きますが、結実率が極めて低く、200〜300個の花のうち1個程度しか実がつきません。結実した実は長さ約20㌢、直径約10㌢の長楕円形で橙黄色から濃黄色へと変わり、熟します。実の中は5室に分かれ20〜50個の種子があります。 この種子を木箱で4〜5日発酵させると、香気が出て表面が赤褐色になり、それを水洗いして乾燥させたものが「カカオ豆」です。このカカオ豆を炒って種皮を除き、すりつぶしたものが「カカオペースト」です。このカカオペーストを圧縮すると、脂肪分と残物とに分かれ、その脂肪分は「カカオ脂(カカオバター)」となり、残物は乾燥させて粉末にした物が「ココア」となります。ココアは熱湯で溶かして飲みます。チョコレートはカカオペーストに砂糖・ミルク・香料を加えて固めたものです。 |
||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
| 29.紅褐色の樹皮も変わっていますが、名前も変わっているバクチノキ(博打の木) | |||
|
所在地 | 東京都調布市深大寺北町1-4 都立神代植物公園 | |
| 科・属など | バラ科 サクラ属 常緑高木 | ||
| 見どころ | 沿海地に生える高さ10〜15㍍になるバラ科の常緑高木です。愛媛県新居浜市には同市指定天然記念物の大きな木が集まっている自生地があります。樹皮は剥げ落ちる性質があり、その剥げ落ちた褐色の肌は木々の中でひときわ目立ちます。バクチノキのバクチは「博打」。博打に負けて着物まで脱ぎ取られ丸裸にされた様子に樹皮を形容したものです。※「名木古木」7ページNO.39にビランジュの名前で載っています。 | ||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
| 31.白い花が白雲たなびくように樹全体に咲く、ハクウンボク(白雲木)その実 | |||
|
所在地 | 東京都調布市深大寺北町1-4 都立神代植物公園 | |
| 科・属など | エゴノキ科エゴノキ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 落葉高木のエゴノキ科エゴノキ属で写真の果実もエゴノキの実にそっくりです。樹皮は灰白色で滑らか、葉が互生し10〜20㌢と大きく円形、葉柄の中に来年の芽が納まっていること。これらがハクウンボクの特徴です。※ハクウンボクの花は19ページNO.10に掲載。 | ||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
|
所在地 | 東京都調布市深大寺北町1-4 都立神代植物公園 | |
| 科・属など | キリ科キリ属 落葉広葉高木 | ||
| 見どころ | 昔、女の子が誕生するとまず植えたのがキリノキでした。その桐で嫁入り道具の桐箪笥を作り、持たせてやるためでした。女の子がいる家屋敷には何本かの桐があり、あちこちに“桐畑”もありました。東横線反町駅近くに地名「桐畑」という伝統ある町内会があります。桐の花は夏の風物詩のような花でしたが、ライフスタイルの変化でどこをさがしてもキリノキが見当たりません。ようやく神代植物園でその木と出合いました。※ようやく出合ったキリの高木は19ページNO.35に掲載。 | ||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
| 38.魚と同じ名前の樹木、ゴンズイ(権萃)の実 | |||
|
所在地 | 横浜市緑区寺山町291 四季の森公園 | |
| 科・属など | ミツバウツギ科ゴンズイ属 落葉小高木 | ||
| 見どころ | 落葉小高木。樹高6㍍。樹皮は若木は灰褐色、太くなると黒褐色。白くかすれたような模様があります。花期5〜6月頃で黄緑色の小さな花を多数つけます。私が行った時は赤い実は袋果で、まだ熟していませんでした。熟すと裂開し、黒い光沢のある種子が1〜2個顔を出すそうです。材が脆くて役に立たないので同じような役にたたない魚のゴンズイの名がつけられたという説があります。※ゴンズイの花は20ページNO.31に掲載。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
|
所在地 | 東京都文京区白山5-31-26 白山神社境内 | |
| 科・属など | ミズキ科ミズキ属 常緑樹 | ||
| 見どころ | 花は日本産の普通見かけるヤマボウシは総苞(花に見えるもの)の先端が細く尖っていますが、ジョウリョクヤマボウシの総苞の先端は丸く、ほんの少しだけ尖っています。葉は濃い緑でつやつやしていますので、違いは明らかです。花期は5月〜6月です。 ※花が1ページNO.16に、実は10ページNO.28に載っています。 |
||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||

写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2009.7.14〜7.28 | 掲載22種 |
| 40.ウワミズザクラ(上溝桜)に似ているイヌザクラ(犬桜) | |||
|
所在地 | 横浜市緑区寺山町291 四季の森公園 | |
| 科・属など | バラ科サクラ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 丘陵地や山地に生える落葉高木で、高さ10-15㍍になります。葉は長楕円形で先端が尾状に長くとがり、浅い鋸歯があります。前年枝の節から5-10㌢のブラシのように見える総状花序を出し、白色の小さな花を多数つけます。花期は4〜6月で私が行った時はもう果実になっていました。ウワミズザクラ(上溝桜)と似ていますが, 花の個数は少なく,花序の下に葉がついていないことなどの違いがあります。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
さくいんのページへ戻る