| 01. 晩秋に咲くビワ(枇杷)の花 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4-986 コンフォール南日吉団地内 | |
| 科・属など | バラ科ビワ属 常緑高木 |
||
| 見どころ | 実が1ページ№30に また新宿御苑の大木が20ページNO.39に掲載されているビワ(枇杷)の花です。白くて小さな枇杷の花が咲き始めていました。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
| 01. 晩秋に咲くビワ(枇杷)の花 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4-986 コンフォール南日吉団地内 | |
| 科・属など | バラ科ビワ属 常緑高木 |
||
| 見どころ | 実が1ページ№30に また新宿御苑の大木が20ページNO.39に掲載されているビワ(枇杷)の花です。白くて小さな枇杷の花が咲き始めていました。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
次ページNO.13へ
| 03. 6月頃咲く花を観たい! ナンキンハゼ(南京櫨)の実 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町3丁目 マンションの庭 | |
| 科・属など | トウダイグサ科ナンキンハゼ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 中国原産の落葉高木で街路樹に多いです。6月頃の花の時期に、ほとんど全部の枝先に細長い円錐状の花の房が付いています。この木の種子の、特に白いロウ質の種皮には良質の脂肪が沢山ふくまれ、ロウソクを作ったり、石鹸や頭髪油、潤滑油など幅広く利用されています。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
木花-World TOPへ戻る
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
| 07. センダン坊主と言われるそうです。センダンの実 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4丁目 交番付近の街路樹 | |
| 科・属など | センダン科センダン属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 2ページNO.15にセンダンの花が掲載されています。落葉して葉がほとんどなくなっ木に、淡黄色の楕円形の実がぎっしり残っていました。とても風情があり、良いものです。1個の実に5~6個の種子が入っています。実は有毒で人や家畜は、中毒症状を起こすそうですのでご注意ください。でも、ヒヨドリやカラスなどは、平気で食べるそうです 。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
| 09. 実がようやく熟しました。タラヨウの実 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西1丁目 民家の庭 | |
| 科・属など | モチノキ科モチノキ属 常緑高木 | ||
| 見どころ | 9ページNO.10にタラヨウの木と葉が掲載されています。ぎっしりと実が付いていたのですが、葉に栄養が行届かなくて、葉が黄ばんでしまうそうで植木屋さんが実を摘んでいました。 真っ赤には熟さないようです。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
| 10. 公園や街路樹に植えられます アメリカ.フウの実 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4丁目 地域ケアプラザ前の街路樹 | |
| 科・属など | マンサク科フウ属 落葉高木 |
||
| 見どころ | 別名はモミジ.バ.フウといわれます。「フウ」とは「楓」でカエデのことです。葉は5裂で、枝にコルク質の翼があります。カエデ類と違って、葉は左右交互に付きます。スズカケノキやモミジ.バ.スズカケノキに似ていますが、よりゴツゴツとした感じの実が生り、中に多くの種子が入っています。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
| 11. 真冬2月が収穫期なのに夏ミカンとは、これいかに? | |||
|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目のわが家の庭 | |
| 科・属など | ミカン科ミカン属 常緑高木 | ||
| 見どころ | この写真は11月12日に撮影しましたが、ようやく少し色づき始めました。毎年2月中旬が食べごろになります。真冬なのに、なぜ夏ミカンと呼ぶのでしょう? 「夏ミカン」の正式名称は「夏橙(だいだい)」って言うのだそうですね。 | ||
| 撮影者 | 臼井昭子 | ||
| 12. たくさんある甘柿の種類。いったい、わが家の柿の種類は? | |||
|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目のわが家の庭 | |
| 科・属など | カキノキ科カキノキ属 落葉広葉高木 | ||
| 見どころ | 地元ではこの種の甘柿を「エダガキ(枝柿)」と呼びますが、柿の種類にこの名はありません。「枝柿」は渋柿を枝を着けたまま折り採って晒し乾しする製法を言うようです。 当然柿には甘柿、渋柿があり、甘柿だけでも御所柿・御所丸・百目柿・霜丸・つるの子・大々丸・禅寺丸・似たり御所柿・蜘蛛の巣丸・丹久鶴・油壺・甲州丸・豊岡柿・富有柿・乾柿といった種類があることがインターネットで分かりました。 |
||
| 撮影者 | 臼井昭子 | ||
| 13. 竹に南天にモミジ、わが家の晩秋 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1丁目のわが家の庭 | |
| 科・属など | |||
| 見どころ | 竹の樹皮も葉も黄ばみました。南天の実が真っ赤に色づき、その葉も光沢を増し、イロハモミジの葉も緑から黄色になってきました。わが家の晩秋の庭の一角、その風情です。 | ||
| 撮影者 | 臼井昭子 | ||
| 19. 花と実が同時に見られる秋に咲く花 シロダモ(白だも) | |||
|
所在地 | 東京都港区白金台5-21-5 国立科学博物館付属 自然教育園内 | |
| 科・属など | クスノキ科シロダモ属 常緑高木 | ||
| 見どころ | 常緑高木で秋に黄色い花が咲き、果実は翌年秋に赤く熟しますので、今年の花と前年の実が同時に見られる面白い木です。近くの公園にもシロダモの木がありますが、黄色い花が咲いていただけでした。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
| 20. 紅葉が見事なメタセコイアの葉とその球果 | |||
|
所在地 | 東京都文京区白山 3-7-1 小石川植物園 内 | |
| 科・属など | スギ科メタセコイア属 落葉針葉高木 | ||
| 見どころ | 1ページ№38に掲載されているメタセコイアです。小石川植物園で撮影したメタセコイアの球果です。紅葉していて球果もはっきりしませんが、松かさに似ているかもしれません。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
| 23. 椿の原種、ヤブツバキ(藪椿)の花 | |||
|
所在地 | 鎌倉市山ノ内1367 東慶寺境内 | |
| 科・属など | ツバキ科ツバキ属 常緑高木 | ||
| 見どころ | 常緑樹木で日本の山地や海岸など各地見られる“ツバキの原種”ですね。椿油はこの藪椿から採れ、伊豆大島の広大な藪椿の林から採取された種から精製される椿油は有名。葉は厚く、艶やか。花は主に早春の2~4月に見られますが、鎌倉の東慶寺は暖かいのか、11月下旬に満開でした。 | ||
| 撮影者 | 臼井昭子 | ||
| 25. 苺の木とも言われる ストロベリーツリーの花 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西5丁目 民家の玄関先 | |
| 科・属など | ツツジ科アルブツス属 半耐寒性常緑中低木 | ||
| 見どころ | 常緑低木で、寒さには比較的強く、丈夫な花木で生育も早く、関東地方でも露地植えが可能だそうです。花はドウダンツツジやアセビに、実はヤマモモに似ています。 花は晩秋に咲き、次から次へと咲きます。紅色の種類もあります。実は、それから約1年後に実るので同時に花と実が見られる場合もあります。果実は砂糖煮やジャムに加工できますが、観賞用に植えられることが多いようです。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
| 30. 街路樹や生垣に多く使われているネズミモチの実 | |||
|
所在地 | 東京都港区芝公園 4丁目 芝公園内 | |
| 科・属など | モクセイ科イボタノキ属 常緑小高木 | ||
| 見どころ | 3ページ№35にネズミモチの花と7ページ№02に掲載されているネズミモチです。実の形が鼠の糞に似ているから名付けられたそうです。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
| 32. 大気汚染に強いクロガネモチ、その実 | |||
|
所在地 | 横浜市鶴見区馬場2丁目20-1 「鶴見馬場花木園」 | |
| 科・属など | モチノキ科モチノキ属 常緑高木 |
||
| 見どころ | 常緑性の高木です。寒さには少し弱いですが、大気汚染に強いので、公園や街路樹に多く植えられています。また、「クロガネモチ」が「金持ち」に通じるから縁起木として庭木として好まれています。葉は卵形で濃緑色で表面はツヤツヤとした光沢があります。葉の縁はぎざぎざがなくなめらかです。5月~6月にごく淡い紫色がかった小さな花を咲かせます。花自体は小さく目立ちませんが花後に1㌢足らずの果実をたくさん付け、秋になると真っ赤に熟します。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
| 37. 樹液はシロップになるイタヤカエデ(板屋楓) | |||
|
所在地 | 東京都文京区白山 3-7-1 小石川植物園 | |
| 科・属など | カエデ科カエデ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 樹高は20㍍、直径1㍍達します。葉は長さ、幅ともに5~10㌢で、掌状に浅く裂け、無毛で鋸歯がなく秋には黄褐色となって散ります。 花は小さい淡黄色で5月頃に咲きます。 建築、器具、車両、床柱など装飾材に利用され、 樹液は砂糖を製造します。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
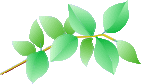
さくいんのページへ戻る

写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2009.11.8~ | 掲載23種 |