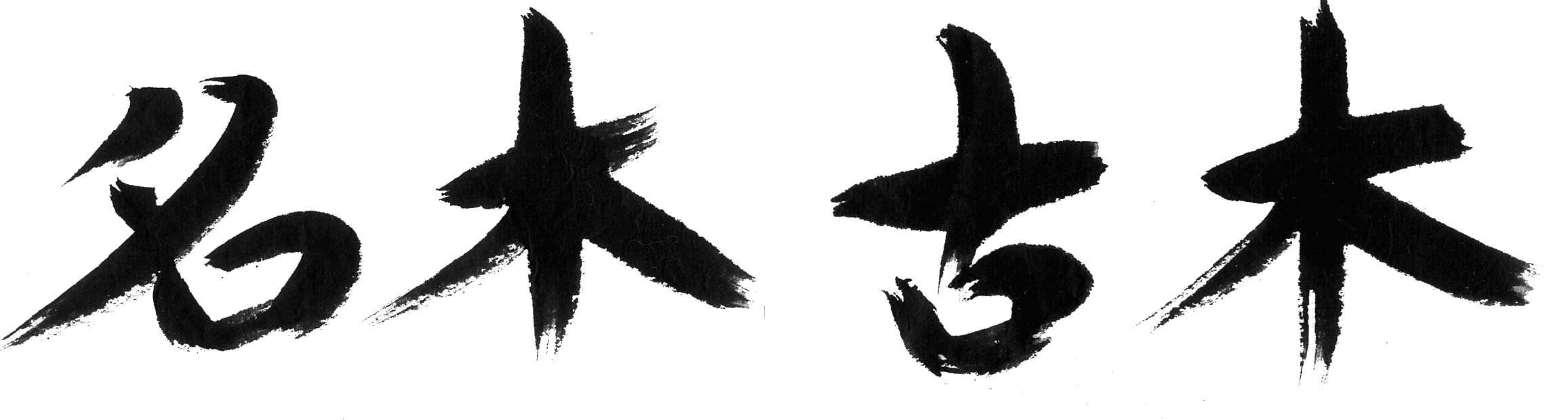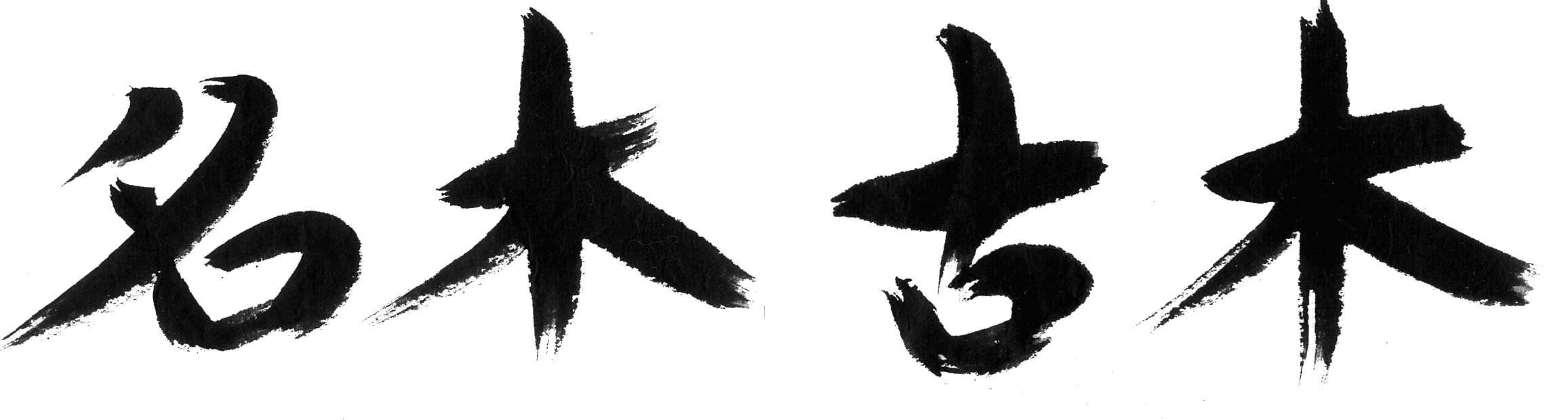樹皮一枚は添え木に支えられ、枝を伸ばし逞しく生きています |
|
|
生い立ち&
見どころ |
一昨日8月15日は終戦から64年目の記念日でした。「焼夷弾の直撃を受けたサルスベリが大聖院にある」と岩田会長から話をお聞きし、きょう17日、行って参りました。岩田会長の話では、私が住む日吉の箕輪町には軍需工場の岡本工作機械製作所(旧サンテラス日吉の所)があったために米軍の攻撃の標的となりました。昭和20年(1945年)4月4日と5月24日、二度もB29の空襲で焼夷弾攻撃に遭いました。
親切な住職さんに、いろいろと説明をしていただきました。
そのサルスベリは境内の裏庭に根を残しながら樹皮一枚で地上から高さ2㍍~3㍍の所で横になっていました。幹の途中から3本に枝分かれして成長しています。時には雪の重みで倒れそうになったりしながらも、添え木にやっと支えられ、毎年真夏8月になると精いっぱい花を咲かせます。住職さんらの愛情に応えるかのように・・・。
きょうも鮮やかな赤紫色の花が満開・・・。それは平和を願っているかのようです。この木の生命力は凄いですね。戦争を知らない人々が多くなった現代、戦争の悲惨さや残酷さを知って欲しいと願っているように私には見えました。 |