| 02 カエデ類の中では、細長い形の葉でやや肉厚! カラコギカエデ(鹿子木楓 )の花 | ||||||
|
所在地 | 神奈川県箱根町仙石原817 箱根湿生花園内 | ||||
| 科・属など | カエデ科カエデ属 落葉小高木 | |||||
| 見どころ | 葉の先端は、鋭く尖り縁には不ぞろいのギザギザがあります。5~6月に薄い黄緑色の花を付け、10月には鋭角に開いたつばさ形の実が紅褐色に染まります。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.02 | |||
| 02 カエデ類の中では、細長い形の葉でやや肉厚! カラコギカエデ(鹿子木楓 )の花 | ||||||
|
所在地 | 神奈川県箱根町仙石原817 箱根湿生花園内 | ||||
| 科・属など | カエデ科カエデ属 落葉小高木 | |||||
| 見どころ | 葉の先端は、鋭く尖り縁には不ぞろいのギザギザがあります。5~6月に薄い黄緑色の花を付け、10月には鋭角に開いたつばさ形の実が紅褐色に染まります。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.02 | |||
次ページNO.23へ
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
木花-World TOPへ戻る
| 08 森林公園とは名ばかり。標示板は、このアブラスギ(油杉)一本だけ | ||||||
|
所在地 | 浜市中区根岸台1-3 根岸森林公園(元根岸競馬場跡地 | ||||
| 科・属など | マツ科 アブラスギ属 常緑高木 | |||||
| 見どころ |
|
|||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.06.19 | |||
| 11小さくて見つけにくい、ツゲ(柘植)の花 | ||||||
|
所在地 | 東京都千代田区九段北3丁目1-1 靖国神社境内 | ||||
| 科・属など | ツゲ科ツゲ属の 常緑広葉低木~小高木 |
|||||
| 見どころ | |
|||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.05 | |||
| 17. 日本の温帯林を代表する樹木の一つ。 ミズナラ(水楢) | ||||||
|
所在地 | 山梨県山梨市牧丘町北原 乙女高原 | ||||
| 科・属など | ブナ科コナラ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 樹皮は灰褐色で、縦に不規則な裂け目があり、薄片状のものが重なっていて、剥がれます。材は堅く、やや赤みを帯びた淡褐色。葉は互生し、枝の先に集まり、倒卵状長楕円形で、基部はくさび形に狭くなり、葉柄は無いか、ごく短いのがミズナラの特徴で、縁には大きな鋸歯があります。 開花は5月、黄緑色の花が垂れ下がります。9月~10月に実が熟します。実は渋みが強いので、野ネズミ、リスなどの動物は、どんぐりを集めると、土中に埋めて、あく抜きをして食べます。 |
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.21 | |||
| 18. 樹皮は灰褐色で紙のように剥がれる。 ダケカンバ(岳樺) | ||||||
|
所在地 | 山梨県山梨市牧丘町北原 乙女高原 | ||||
| 科・属など | カバノキ科カバノキ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | シラカバ( |
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.21 | |||
| 19. 見事な満開のレンゲツツジ(蓮華躑躅)の群生! | ||||||
|
所在地 | 山梨県山梨市牧丘町北原 乙女高原 | ||||
| 科・属など | ツツジ科ツツジ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ |
|
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.21 | |||
| 20. 「緑のダム」とも言われる保水力が大きい、ブナ(橅)の木 | ||||||
|
所在地 | つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園内 | ||||
| 科・属など | ブナ科ブナ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 神奈川県山北町は、市町村の木としてブナが指定されています。青森県と秋田県にまたがる「白神の森」はブナを中心とした冷温帯・落葉広葉樹林が広がる“世界自然遺産”で、わが国自然保護の象徴とも言われています。 以前は、東北地方を中心に近年に至るまでブナ林は伐採されずに残っていました。その大きな理由はブナが材木としてはほとんど役立たなかったのですが、ブナ林は保水力が大きく、夏、比較的雨の少ない日本海側はブナ林が貯えた水が夏の乾燥から作物や山野の植物を護って、多雪地帯の人々にとって貴重な食糧となりました。近年ブナは水源涵養林としての役割を見直され「ブナを植える会」などの活動が活発になっています。神奈川県内のブナ林は丹沢湖にあります。 |
|||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.24 | |||
| 27. ガクアジサイ(額紫陽花)に似ている、ヤマアジサイ(山紫陽花) | ||||||
|
所在地 | つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園内 | ||||
| 科・属など | ユキノシタ科アジサイ属 落葉低木 |
|||||
| 見どころ | アジサイ(紫陽花)の花は2ページNO.10とNO.16 3ページNO.01とNO.31 11ページNO.12に掲載されています。 |
|||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.24 | |||
| 29. 大きな葉、直立した円錐状の穂に白い花が咲く! トチノキ(栃の木)の花 | ||||||
|
所在地 | 山梨県山梨市牧丘町北原 乙女高原へ行く途中 | ||||
| 科・属など | トチノキ科トチノキ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 21ページNO.02に生ったばかりの |
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.21 | |||
| 30. 鮮やかな新緑と紅葉がすばらしい! カラマツ(唐松) | ||||||
|
所在地 | 山梨県山梨市牧丘町北原 乙女高原へ行く途中 | ||||
| 科・属など | マツ科カラマツ属 落葉針葉木 | |||||
| 見どころ |
|
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.21 | |||
| 35. 実が赤く色づき始めました! エノキの実 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院道路沿いの植え込み | ||||
| 科・属など | ニレ科エノキ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 6月に青い新しい実が生り、今、赤や黄色、オレンジ色に色づいて、きれいです。10月頃には赤色から赤褐色に変わります。 16ページNO.37に |
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.9.7 | |||

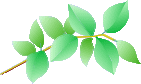
写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 36. 黒く熟した実は甘酸っぱく、野鳥も大好物! ムクノキ(椋の木)の実 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西4丁目 早淵川の土手 | ||||
| 科・属など | ニレ科ムクノキ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 18ページNO.28に |
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.19 | |||
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2010.06.17~ | 掲載22種 |
さくいんのページへ戻る