| 01. 鶴岡八幡宮ぼたん庭園のヤチヨツバキ(八千代椿) | |||
|
所在地 | 鎌倉市雪ノ下2丁目 鶴岡八幡宮 ぼたん庭園内 | |
| 科・属など | ボタン科ボタン属 落葉低木 | ||
| 見どころ | 透けるようなピンク色の中輪で、華やかに咲き誇っていました。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
| 01. 鶴岡八幡宮ぼたん庭園のヤチヨツバキ(八千代椿) | |||
|
所在地 | 鎌倉市雪ノ下2丁目 鶴岡八幡宮 ぼたん庭園内 | |
| 科・属など | ボタン科ボタン属 落葉低木 | ||
| 見どころ | 透けるようなピンク色の中輪で、華やかに咲き誇っていました。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
さくいんのページへ戻る
| 35.ヒガンザクラ(彼岸桜)と間違えやすい、ヒカンザクラ(緋寒桜) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉2丁目 民家の庭 | |||
| 科・属など | バラ科サクラ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 久しぶりに散歩に出ると、民家の門の脇に真っ赤な花が咲いています。近づくと鮮やかな緋紅色の一重の花が下向きに咲いている「緋寒桜」でした。このヒカンザクラ(緋寒桜)はヒガンザクラ(彼岸桜)と混同しやすいため「カンヒザクラ(寒緋桜)」とも言われます。沖縄では1月~2月に開花、本州の関東あたりでは3月に開花します。 | ||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.03.12 | ||
| 34.NO.8に掲載と同種。30~50個の花がかたまって咲く、ミツマタの満開 | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町3丁目5番 民家の庭 | |||
| 科・属など | ジンチョウゲ科ミツマタ属 落葉低木 | ||||
| 見どころ | NO.8の写真は同じミツマタでも咲き初め。こちらは蕾は一つもなく、ミツマタ(三又)の枝先にびっしりと30~50個の花がかたまって咲いています。花びらに見えるのは実はガク(萼)で、内側が鮮やかな黄色で美しい。 | ||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.03.10 | ||
| 32.春を彩る代表的な花木。果実が“握り拳”に似ているコブシ(辛夷) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区高田東3丁目36番の民家 | |||
| 科・属など | モクレン科モクレン属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 私は毎年正月頃からこの花が咲くのが待ち遠しい。コブシの白い花とその芳香で春の到来を実感するからです。雪に閉ざされた北国ではコブシの白い花が農作業を始める目安になっています。 | ||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.03.13 | ||
| 23.桃の節句には欠かせません! ハナモモ(花桃) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島台 綱島市民の森 「桃の里」 | |||
| 科・属など | バラ科サクラ属 耐寒性落葉低木 | ||||
| 見どころ | 桃色と濃いピンク色の花が満開でした。ハナモモは切花に使われます。戦前、綱島は岡山と並ぶ日本のモモの二大産地でした。有名な綱島桃畑の蕾は、まだ固い状態でした。「東京園」のサクラの花と同時に見られるでしょう。(綱島駅から徒歩5分)。※綱島ラジウム温泉 東京園に掲載 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.03.08 | ||
| 20.馬が食べると酔ったようになることから漢字名で、アセビ(馬酔木) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区高田町 高田中学校近くの民家 | |||
| 科・属など | ツツジ科アセビ属 常緑低木 | ||||
| 見どころ | 5-14に石川さん撮影、アセビの実が掲載されています。高さ1~8㍍の常緑低木。早春からスズランに似た釣り鐘型の花を咲かせ、春の到来を感じさせる植物です。花が美しいので庭木としても人気がありますが、有毒植物です。写真の花は紅色を帯びた品種でした。 | ||||
| 撮影者 | 配野美矢子 | 撮影日 | 2010.03.05 | ||
| 18.シキミ(樒)の花が咲き始めました! | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町2丁目 金蔵寺境内 | |||
| 科・属など | シキミ科シキミ属 常緑高木 | ||||
| 見どころ | 8ページNo.05にシキミの実が掲載されています。 その木に淡黄白色の花が咲きはじめました。仏前に供える木です。 金蔵寺の帰りに「シキミ」の鉢植えを5鉢も置いてある家がありました。(綱島西5丁目)日当たりが良いためか良く開いていたので、こちらの家の画像を載せます。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.03.02 | ||
| 13.濃いピンクの実がびっしり! マユミの実 | |||
|
所在地 | 神奈川県下足柄郡二宮町 吾妻山公園頂上 | |
| 科・属など | ニシキギ科ニシキギ属 落葉小高木 | ||
| 見どころ | 5ページNo.32に若い実が、 11ページNo.16に実が割れて種子が顔を出した様が掲載されています。ピンク色の実が割れて、中の種子はほとんど落ちてなくなり殻だけが残っていました。まるで木全体に花が咲いているようでした。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
| 12.葉が銀灰色をしている ギンヨウ(銀葉)アカシアの花 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西3丁目 民家の庭 | |
| 科・属など | マメ科アカシア属 常緑樹 | ||
| 見どころ | 5ページNo.34にインゲン豆のような実が垂れ下がっている様子が、13ページNo.22のフサアカシアの見所の中にも掲載されています。ギンヨウアカシアとフサアカシアの花は全く同じに見えます。黄色い球状の花がびっしり咲きます。葉は、いろいろの形があるようです。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
| 05. 初めて実物の花を見ました。ユーカリノキの花 | |||
|
所在地 | 鎌倉市岡本1018番地 県立フラワーセンター大船植物園 温室内 | |
| 科・属など | フトモモ科ユーカリノキ属 常緑高木 | ||
| 見どころ | 6ページno.20に木が掲載されています。フトモモ科の常緑樹で樹皮は,はがれやすく幹はすべすべで白くなっていました。葉が肉厚で卵形の園芸植物もユーカリの木と同じ種類だそうです。花期は、4~5月とありますが、温室の中では咲き始めていました。開花と同時に花びらが落ちてしまうため、雄しべだけが目立つのだそうです。もう少し拡大したかったのですが、高木のため私のカメラでは、これが限界でした。 | ||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
木花-World TOPへ戻る
| 25.ツツジの仲間の中でも早春真っ先に咲くミツバツツジ | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区高田町 高田中学校付近の民家 | |||
| 科・属など | ツツジ科ツツジ属 落葉低木 | ||||
| 見どころ | ツツジ科ツツジ属の落葉広葉低木、近畿から関東の太平洋側の山間地に生育し、3月下旬から4月にかけて葉が出る前に赤紫の花を咲かせます。 枝が細くすんなり上に伸びていて、菱形状をした緑色の葉が枝先に3枚輪状に付くのが特徴です。 | ||||
| 撮影者 | 配野美矢子 | 撮影日 | 2010.03.10 | ||
| 08.和紙や紙幣の原料となるミツマタ、その花 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区篠原北1-26-22 わが家の庭 | |
| 科・属など | ジンチョウゲ科ミツマタ属 落葉低木 | ||
| 見どころ | 12年前に入院中の主人が退院したのを記念し、縁起の良いミツマタの苗木を庭に植えました。毎年1月下旬に開花して3月上旬まで楽しませてくれます。1ページNO.21に珍しい赤い花のミツマタが載っていますが、わが家のは黄色い花で掲載写真に一輪だけ咲いています。 | ||
| 撮影者 | 臼井昭子 | ||
| 11.早春に咲く花 サンシュユ | |||
|
所在地 | 横浜市緑区寺山町291 四季の森公園 内 | |
| 科・属など | ミズキ科ミズキ属 落葉小高木 | ||
| 見どころ | 11ページ№02に掲載されているサンシュユです。黄色の小さい花が満開でした。サンシュユの果実でお酒を造ります。漢方薬にも使われています。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
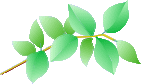
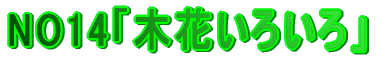
写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 36.早春の陽だまりに花開き、夕方には閉じる。よく目立つハクモクレン(白木蓮) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 民家の庭 | |||
| 科・属など | モクレン科モクレン属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 「元町・中華街行き」の東横線の電車が日吉駅ホームを出るとすぐ車窓右手、“箕輪の丘”の下の屋敷にこの大きなハクモクレンの木に今を盛りと白い花が咲いている。いつかこの木の花が満開の様子を写真に収めようと思っていたが、ようやくその思いが叶った。9枚の花びらが完全に開ききるのを何度か行って撮影したが、コブシとは異なり、モクレン同様完全には開ききらないということが分かった。 | ||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.03.11 | ||
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2010.01.29~03.13 | 掲載26種 |
| 19.中国原産で日本に導入されて日が浅い新花木、ミヤマガンショウ(深山含笑)の花 | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区樽町3丁目 民家の庭 | |||
| 科・属など | モクレン科ミケリア属 常緑花木 | ||||
| 見どころ | オガタマノキ(招霊の木).ウンナンオガタマノキ、カラタネオガタマノキなどの仲間です。花期はハクモクレンよりも早く、2月半ば頃から咲きます。一重の白花で花径は10センチ程の大輪で、良い香りがします。モクレン類は枝先に花をつけますが、ミヤマガンショウは枝の途中に花をつけるのが特徴です。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.03.03 | ||
| 14.羽根木梅林の梅「呉羽しだれ」 | |||
|
所在地 | 世田谷区代田4-38-52 | |
| 科・属など | バラ科サクラ属 落葉高木 | ||
| 見どころ |
|
||
| 撮影者 | 西川恭永 | ||