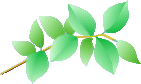| 01. 街の中よく見かけるピラカンサスの実 | |||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 民家の庭 | |
| 科・属など | バラ科トキワサンザシ属 常緑広葉低木 | ||
| 見どころ | 2ページNO.34に花が掲載されているピラカンサスです。冬になると小さな赤い実をたくさん付けます。赤い実は毒性を持ち不味いので、鳥たちはあまり食べません。実は少しずつあちこちにばらまかれることになるので、結果としては繁殖に有利となります。棘があるので注意しましょう。 ※大木に実を鈴なりにつけた木は13ページNO.15に。 |
||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||