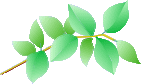
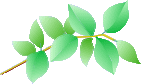

| 39. 淡緑色で小さく目立たない、ナツメ(棗)の花 | ||||||
|
所在地 | 東京都文京区白山 3-7-1 小石川植物園内 | ||||
| 科・属など | クロウメモドキ科ナツメ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | ナツメの木は7ページNO.06に掲載されています。花は、4〜5月ころに葉のわきに淡黄色の小さな花を数個ずつつけます。果実は核果で楕円形で、はじめは淡緑色ですが、熟すと暗赤色になります。果実はそのまま食べられます。また、乾燥して漢方薬として用いられます。 | |||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.16 | |||
| 20. 花は完全には開かない! ミツバウツギ(三葉空木)の花 | ||||||
|
所在地 | 神奈川県箱根町仙石原817 箱根湿生花園内 | ||||
| 科・属など | ミツバウツギ科ミツバウツギ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ |
|
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.02 | |||
写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 27. 類似種の「ウワミズザクラ」との違いは基部に葉がないこと! イヌザクラ(犬桜)の花 | ||||||
|
所在地 | 神奈川県箱根町仙石原817 箱根湿生花園内 | ||||
| 科・属など | バラ科サクラ属 落葉広葉小高木 | |||||
| 見どころ | バラ科の落葉広葉小高木です。葉は長い楕円形で先端が尖って、縁に細かいギザギザがあります。花は5〜7ミリと小さく、まとまって房になって咲き、花びらは目立たず雄しべが目立ち、ブラシのような形に見えます。葉が出たあとに咲きます。9月〜10月に赤から黒紫の実が熟します。9ページNO.40の赤い実をご覧ください。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.02 | |||
| 24. 陰暦の5月に咲く花、お馴染みのサツキ(皐月) | ||||||
|
所在地 | 川崎市中原区中丸子 NEC玉川工場生垣 | ||||
| 科・属など | ツツジ科 ツツジ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ | 陰暦の5月(皐月)に咲く花、サツキです。今を盛りに咲くこの花は100m歩けばどこかで咲いています。それほど私たちの眼を楽しませ馴染み深い花なのに、今までどなたも投稿しません。あまりに“サツキちゃん”が可哀相ですね。 旧暦の5月は、陰暦でいえば6月上旬から7月上旬にあたります。この時期栄養分が無い所でも逞しく育ち、美しい花を咲かせることから江戸時代から盛んに庭木や盆栽として親しまれてきたようです。 |
|||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.06.06 | |||
| 16 道行く人の足を止める赤紫色の、ベニバナトチノキ(紅花栃の木)の花 | ||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田3丁目 さくらが丘分譲住宅地内 | ||||
| 科・属など | トチノキ科トチノキ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 1ページNO.9にトチノキの園芸品種「ベニバナトチノキ」の花が載っていますが、これは白とピンクの花が総状の花序に入り混じって咲いています。掲載の花は赤紫色一色の花が少々盛りを過ぎていますが枝先に咲き誇っているのが道行く人の足を止めていました。その下にはすでに実が生っている枝もあります。 | |||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.06.04 | |||
| 13 大きな円錐形の房に小花を咲かせる! 種は羽子板の玉、ムクロジ(無患子)の花 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4丁目 コンフォール南日吉団地の街路樹 | ||||
| 科・属など | ムクロジ科ムクロジ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 11ページNO.29に黄色く熟した実が載っています。円錐形の房に直径4〜5ミリの薄黄緑色の花を多数咲かせます。咲き終わると雨のように降ってくるそうなのでその瞬間を見たいものです。種子は、数珠や羽根突きの球に使われます。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.01 | |||
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2010.05.28〜 | 掲載27種 |
| 33. 開花当初は黄色だが、中央のふくらみが赤く変わる! モクゲンジの花 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院の庭 | ||||
| 科・属など | ムクロジ科モクゲンジ属 落葉高木 |
|||||
| 見どころ | 9ページNO.17にぎっしり付いた実が載っています。6月中旬から7月初旬にかけて、枝先に穂状の花序を付け、たくさんの黄色の花を咲かせます。花は開いた当初は、黄色ですが、一両日の内に中央のふくらみが赤く色付きます。金色の雨が降るようにはらはらと散る様子を見てみたい! | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.11 | |||
| 32. お料理の風味づけには欠かせない サンショウ(山椒)の実 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 民家の庭 | ||||
| 科・属など | ミカン科 サンショウ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ | 花が3ページNO.13に掲載されています。雌雄異株の山椒は、実は雌株にだけつきます。秋には、実が赤くなり、種子を外してすりおろして粉にします。初夏の時期は、青い実をまるごと料理に使うことが出来ます。 | |||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.11 | |||
| 23. 松の花に似ている、ラカンマキ(羅漢槇)の雄花 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町4-986 コンフォール南日吉団地内 | ||||
| 科・属など | マキ科 イヌマキ属 常緑針葉樹 | |||||
| 見どころ | ラカンマキ(羅漢槇)は,中国原産で、イヌマキの変種です。全体に小型で、葉の長さは4〜8センチで、長さ、ともにイヌマキの半分ほどです。雌雄異株であり、花は5月頃から咲き始め、雄花はマツ類とよく似た形をしています。ラカンマキの果実はイヌマキとそっくりです。イヌマキに関しては実が6ページNO.39に、イヌマキの「名木、古木」が1ページNO.10に掲載されています。 | |||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.04 | |||
| 22. 普通は「オニツツジ(鬼躑躅)」と呼ばれる! レンゲツツジ(蓮華躑躅)の花 | ||||||
|
所在地 | 神奈川県箱根町仙石原817 箱根湿生花園内 | ||||
| 科・属など | ツツジ科ツツジ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ | 低山帯の日当たりの良い草地に生える落葉低木です。 葉は長さ5〜10センチで光沢がなく、長楕円形で毛が多くあり、しわしわが多く、少し外側に反り返って いるのが特徴です。花は葉と同時に開き2コ〜8個の短総状花序だが、1カ所に集まって咲くので散状花序に見えます。花色はいろいろに変化し、濃朱紅色から黄色のものまであります。 有毒植物なので家畜が食べないので、放牧地に植えられていることが多いです。※レンゲツツジの群生は22ページNO.19に掲載。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.02 | |||
| 03 ニレといえばこの木のことで、別名をエルムと呼ぶ、ハルニレ(春楡) | ||||||
|
所在地 | 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑 | ||||
| 科・属など | ニレ科ニレ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 天を突くような30メートルもある高さ、左右にもこんもりと茂るその堂々たる樹姿はひときわ目立ちます。冷涼な気候を好む樹種だそうですが、この元気なこの木を見ると、暖かい東京でも手入れ次第で巨木に育つことを証明しています。幹に近づくと、樹皮は縦に細かい割れ目があるのがこの木の特徴のようです。秋の紅葉も美しいそうですから、また秋、お目にかかりたい! | |||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.05.28 | |||
次ページへNO.22へ
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
木花-World TOPへ戻る
さくいんのページへ戻る
| 40. 最高級建築材として使われる、ヒノキ(檜) | ||||||
|
所在地 | 東京都文京区白山 3-7-1 小石川植物園内 | ||||
| 科・属など | ヒノキ科ヒノキ属 針葉樹 | |||||
| 見どころ | 木目が通り、斧や楔で打ち割ることによって製材できるヒノキ(檜)は古くから建築用材として用いられてきました。特に寺院、神社の建築には必須で古くから利用されています。樹高は20〜30メートルになりますが、大きいものでは高さ50メートル直径2.5メートルほどになるのもあります。葉は鱗片状になって枝に密着しており、材は美しく耐久性が高いので、高級建築材として使われています。ヒノキは檜の字を当てられていますが、元来は「火の木」であり、擦り合わせて火をおこしたことに由来すると言われています。 | |||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.16 | |||
| 36. 樹皮がウリに似ている、ウリハダカエデ(瓜膚楓) | ||||||
|
所在地 | 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑 | ||||
| 科・属など | カエデ科カエデ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 成木は灰褐色になるそうですが、若木の樹皮はウリ(瓜)のような木肌です。葉は3裂や5裂のもの、切れ込みのないものなど、いろいろの葉を着けています。秋の紅葉も葉ごとに色合いが異なり、バリエーションがあります。カエデ属の中でも特異な存在です。 | |||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.06.15 | |||
| 35. 枝や葉は、神前に玉串として供えられる、サカキ(榊)の花 別名 ホンサカキ | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区高田東2丁目 民家の庭 | ||||
| 科・属など | ツバキ科サカキ属 常緑高木 | |||||
| 見どころ | 葉は分厚く光沢があり、縁はギザギザはありません。6〜7月に、葉の付け根に白い清楚な花が咲き、だんだん黄色を帯びてきます。神事には欠かせない樹木ですが、花は初めて見たような気がします? | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.10 | |||
| 31. 道路沿いに咲いていた アカメガシワ(赤芽柏)の雄花 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西6丁目 道路沿い | ||||
| 科・属など | トウダイグサ科アカメガシワ属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 花が4ページNO.23に掲載されています。雌雄異株で雄花だけ咲いているのを見つけました。道端にこんな綺麗な花が咲いていてびっくりしました。今までは気がつきませんでした。 | |||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.11 | |||
| 29. 秋にぶどうの形に似た赤い実の房を垂らすイイギリ(飯桐)の雄花と雌花 | |||||||
|
所在地 | 東京都港区白金台5-21-5 国立科学博物館付属 自然教育園内 | |||||
| 科・属など | イイギリ科 イイギリ属 落葉高木 | ||||||
| 見どころ | 実が1ページNO.37と11ページ34に掲載されています。雄花も雌花も同じように黄緑色で3〜5月頃咲き、円錐花序となり垂れ下がります。長い柄のあるハート型の葉で、昔はこの葉でご飯を包んだことが名前の由来です。 私が撮影に行った時は、雄花(写真下)は散り地上に。2.〜3日後に雌花(写真上)の様子を見に行きましたらは房状に垂れ下がっていました。 樹高が15〜20メートルくらいありますので、花径が1センチくらいの雄花を拾い撮影しました。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.06.03/6.06 | ||||
| 25. サクラのような高木に純白の花 シロヤシオ(白八汐) | |||||||
|
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字湯本 那須高原 | |||||
| 科・属など | ツツジ科ツツジ属 落葉樹 | ||||||
| 見どころ | 高原に幹の太さが50センチ以上もある、松のような木肌のツツジの木。樹高がサクラの木のように高く、7〜10メートルもあります。それが5本、10本と群生し、枝先に純白の花を咲かせる清楚な光景は、まさに“夢園”のようです。花の名前を聞けば、シロヤシオ(白八汐)・・・。枝先に菱形の葉が5枚輪生することから「ゴヨウツツジ」とも言い、このような古木の樹皮がマツに似ているので「マツハダ(松肌)」とも呼ぶそうです。 | ||||||
| 撮影者 | 大田孝子 | 撮影日 | 2010.06.05 | ||||
| 17 高木の枝先に咲くセンダン(栴檀)の花 | ||||||
|
所在地 | 川崎市宮前区神木本町2丁目 県立東高根森林公園 | ||||
| 科・属など | センダン科センダン属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 目通し直径1m以上もある高木の周りに白いものが敷き詰めたように落ちていました。見上げると、8mほどの高い枝に白い花がたくさん咲いています。これ、何の花? この写真をインターネットに投稿し、花名を尋ねました。10分も経たずに“花の先生”が「センダンの花」と教えてくださいました。センダンといえば、葉も、樹皮も、果実も、材木も私たちの生活に役立ってきた樹木と聞いていましたが、現物を見たのは初めて。 2ページNO.15にもセンダンの花が載っていますが、高木のこの花も掲載します。 |
|||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.06.04 | |||
| 15 枝いっぱいに独特の色合いの花をつける! ウツギ・マギシェン 別名・紅花梅花空木 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 民家の畑 | ||||
| 科・属など | ユキノシタ科ウツギ属 落葉低木 | |||||
| 見どころ | ウツギの交配種で流通名は「ベニバナバイカウツギ」「アカバナウツギ」と呼ばれています。蕾の時は紅色で、開くと白地に濃いピンク色の絞り模様が付く上品な花を房状に付けます。庭園樹や記念樹として利用されることが多いそうです。バイカウツギの花は2ページNO.19に載っています。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.06.01 | |||
| 12 川崎市原産の柿 ゼンジマルガキ(禅寺丸柿)の花 別名 王禅寺丸柿 | ||||||
|
所在地 | 横浜市南区六ツ川3丁目122番地 横浜市こども植物園 | ||||
| 科・属など | カキノキ科カキノキ属 落葉高木 |
|||||
| 見どころ | 禅寺丸柿(ぜんじまるがき)とは、鎌倉時代に川崎市麻生区にある星宿山蓮華院王禅寺の山中で自生しているものが偶然に発見され、それまで日本各地の柿の木は全て渋柿であり、甘柿の存在は知られてなく、日本で最初の甘柿(不完全甘柿)として位置づけられているそうです。ゼンジマルガキ(禅寺丸柿)は日本最古の甘柿の品種です。甘柿が12ページNO.12に載っています。 | |||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.05.31 | |||
| 10 "地球に優しい新素材を生み出す"と注目され始めた! モリシマアカシアの花 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3300 日産スタジアム周囲の植え込み | ||||
| 科・属など | ネムノキ科アカシア属 常緑高木 | |||||
| 見どころ | 開花時期は、フサアカシアなどより遅く5月10日頃から6月10日頃です。花色も地味なクリーム色。甘い香りがします。「モリシマ」とは、名前ではなく,軟らかい、軟毛のあるという意味だそうです。 オーストラリア原産で、70年前頃から日本でも植えられるようになった歴史ある木ですが、途中見捨てられながらも、現在では、地球に優しい新素材を生み出す研究のなかで再び注目を浴びるようになっています。樹皮粉末から断熱性に優れた良質の「生分解性ポリウレタンフォーム」を生成できるのだそうです。バルブ材となる他、樹皮からタンニンが採れます。 |
|||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.05.28 | |||
| 08 幸運なことに雄株と雌株の木が並んでいました! ナギノキ(梛ノ木)の雄花と雌花 | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院内駐車場植え込み | |||||
| 科・属など | マキ科ナギ属 常緑針葉高木 | ||||||
| 見どころ | 19ページNO.40に実(昨年の実が残っていた)が載っています。雄花は前年枝の葉腋に、円柱形の淡黄緑色の花粉がいっぱいの花を付けていました。雌花(下の写真)は前年枝の葉腋に、小さく丸い胚珠が1〜2個付きます。 | ||||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.05.28 | ||||
| 07 葉は常緑、三行脈がくっきりしている! ヤブニッケイ(藪肉桂)の花 別名 クロダモ | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区小机町3211 横浜労災病院内駐車場植え込み | ||||
| 科・属など | クスノキ科クスノキ属 常緑高木 | |||||
| 見どころ | クスノキ科常緑高木。葉の表面は光沢があり、裏面は灰白色です。花は6月に、本年枝の葉腋から長柄のある散形花序を出して、一つの花序に5〜13個の淡黄緑色の花を付けます。果実は秋に黒紫色に熟し、種子からは香油が採れます。葉や樹皮はリュウマチ、打撲などの薬用にも使われます。ニッケイ(シナモン)に似て芳香はありますが劣ります。 | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.05.28 | |||
| 02 栃餅の食材となる、トチノキ(栃の木)の実 | ||||||
|
所在地 | 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑 | ||||
| 科・属など | トチノキ科トチノキ属 落葉広葉 | |||||
| 見どころ | 樹高20〜30メートルにもなる高木の下枝に実が付いていました。花期が5〜6月なのに、早くも実が生り、その周りにまだ花殻が残っています。羽ウチワのような形の大きな葉と、直立した円錐状の穂に白い花がこの木の特徴。この青い実は9月に熟して割れ、中から大きな1〜2個の種子を出します。この種子にデンプン質を豊富に含み、これを加工したのが“栃餅”です。 高木のトチノキの姿が5ページNO.29に、葉が紅葉し始めた様子が11ページNO.32に載っています。 |
|||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.05.28 | |||