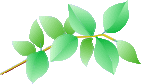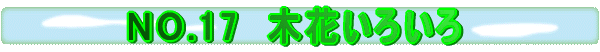| 11. 新芽が黄金色の キンメキャラボク(金芽伽羅木) | |||||
|
所在地 | 横浜市緑区寺山町 四季の森公園 へ行く途中の民家の庭 | |||
| 科・属など | イチイ科イチイ属 常緑低木 | ||||
| 見どころ | 8ページNO.06に赤い実が掲載されている、イチイの仲間キャラボクの一種です。成育は遅く、枝葉もキャラボクよりひとまわり小さくなります。樹形は半球形で、新芽はあざやかな黄金色で、黄緑から緑色に変わっていきます。秋には雌株には、1センチの赤い丸い実を付けます。 | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.04.18 | ||