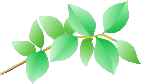| 02 小さな バナナが集まっているように見える、 カンレンボク(旱蓮木)の実 | ||||||
|
所在地 | 横浜市南区六ツ川3丁目122番地 横浜市こども植物園内 | ||||
| 科.属など | オオギリ科 カンレンボク属 落葉高木 | |||||
| 見どころ | 実の大きさは5~6センチ位で、丸い形に集まる果実ひとつひとつが、バナナが集まっている感じです。熟すと黄色くなります。別名「喜樹(キジュ)」とも呼ばれ、縁起の良い名前から、原産地の中国では公園樹のほか、お祝いの木としても親しまれているそうです ※カンレンボクの花は23ページNO.18に掲載されています。 |
|||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.10.14 | |||