| 1.日陰でも育つ、丈夫なアオキ | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 日吉の丘公園 | ||
| 科・属など | みずき科アオキ属 常緑低木 | |||
| 見どころ | 樹皮が緑色であるので「アオキ」。光沢ある常緑葉、綺麗な赤い実、日陰でも育つ成長力が魅力で庭木としても植えられています。※アオキの花は15ページNO.34に載っています。 | |||
| 撮影者 | 岩田忠利 | |||
| 1.日陰でも育つ、丈夫なアオキ | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町3丁目 日吉の丘公園 | ||
| 科・属など | みずき科アオキ属 常緑低木 | |||
| 見どころ | 樹皮が緑色であるので「アオキ」。光沢ある常緑葉、綺麗な赤い実、日陰でも育つ成長力が魅力で庭木としても植えられています。※アオキの花は15ページNO.34に載っています。 | |||
| 撮影者 | 岩田忠利 | |||
次ページNO.6へ
木花-World TOPへ戻る
| 4.イチョウの花を探していたらもう実が・・・ | |||||
|
所在地 | 横浜市中区日本大通り | |||
| 科・属など | イチョウ科イチョウ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | イチョウは雌雄異株とは聞いていましたが、「花をみつけてみよう、どんな花かしら」と探していました。ところが、すでに小さな大豆大の実になっているのを発見しました。6月現在。 ※今年3月に倒れた鎌倉・八幡宮の大イチョウが元気な頃の姿は「名木古木」1ページN0.8に掲載。 |
||||
| 撮影者 | 佐野紀子 | ||||
| 5.南国情緒を醸し出す、ソテツ(蘇鉄) | |||||
|
所在地 | 川崎市宮前区野川419 影向寺 | |||
| 科・属など | ソテツ科ソテツ属 常緑低木 | ||||
| 見どころ | 九州南部や沖縄、中国や台湾など暖地の海岸に自生し、崖地に多い。「蘇鉄」の名前は、弱った株に鉄釘を刺すと勢いを取り戻すという言い伝えに由来します。写真右の木の幹の先端に雄花の花序が見えます。何本もフサフサとした花穂が出ています。 ※ソテツの大きな雌花(26ページNO.1)ををご覧ください。 |
||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||||
| 7.駐車場でたわわになっているブドウ | |||||
|
所在地 | 横浜氏港北区日吉5丁目 民家 | |||
| 科・属など | ブドウ科ブドウ属 つる性落葉低木 | ||||
| 見どころ | ブドウ科は世界に約12属700種もあります。それを大別するとヨーロッパブドウとアメリカブドウで、日本で作られているのはヨーロッパブドウが主流だそうです。ブドウの木は強健で、放置すると、どんどん生長します。冬場の思い切った剪定が重要です。 | ||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||||
| 12.何だろうと近づけば、ヒマラヤスギの雌花 | |||||
|
所在地 | 横浜市中区日本大通り 県庁の庭 | |||
| 科・属など | マツ科ヒマラヤスギ属 常緑針葉高木 | ||||
| 見どころ | 山下公園から赤レンガ倉庫に続く遊歩道上から眺めた県庁方面。高い木の上に白いものがいくつもみえました。不思議に思って側に 近寄ってみると松傘のようです。松傘は花です。ヒマラヤスギでした。 | ||||
| 撮影者 | 佐野紀子 | ||||
| 14.クリーム色の壺形の花を穂のように吊り下げるアセビ(馬酔木) | |||||
|
所在地 | 川崎市中原区新城4丁目5から井田1丁目35 | |||
| 科・属など | ツツジ科アセビ属 常緑低木 | ||||
| 見どころ | ツツジ科のアセビ属の高さ1~8㍍の常緑低木。箱根・伊豆・大台ケ原に自生していますが、公園や庭に春、花が咲きます。漢字名「馬酔木」は馬が食べると酔ったようになることから。昔は葉を煎じて殺虫剤として利用しました。写真の果実も熟すと上を向く有毒植物です。 ※花14ページNO.20参照。 |
||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||||
| 15.一列に並んだ10軒の家。どの家の玄関先にも美しい若葉のネグンドカエデ・フラミンゴの木 | |||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田3丁目 さくらが丘住宅 | |||
| 科・属など | カエデ科 カエデ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 道の反対側が横浜市港北区下田町、一方が川崎市中原区という市境の道。ここをバイクで通ると、ピンクの新しい枝を伸ばし威勢よく生長している珍しい木が目に入りました。樹木図鑑によればカエデの変種、「ネグンドカエデ『フラミンゴ』」。これが南向きに一列に並んだ10軒の家々の玄関先に植えられています。若木で成長期、どの家の木もピンクの枝先が威勢よく伸びて、美しい。 ※ネグンドカエデ・フラミンゴの果実が20ページNO.33に。 |
||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||||
| 19.生垣には珍しい、ベニバナトキワマンサク(紅花常磐万作) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町6丁目 駐車場の生垣 | |||
| 科・属など | マンサク科トキワマンサク属(ロロペタルム属)中高木 | ||||
| 見どころ | 駐車場の生垣がトキワマンサク。赤い花が咲いていました。豊年万作に通じる縁起の良い植物。冬でも葉が落ちないので、生垣としても人気が高いようです。 ※東横沿線でいま大流行のベニバナトキワマンサク、緑の葉の白い花のトキワマンサクとの組み写真16ページNO.21をご覧ください。 |
||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||||
| 20.満開のベニバナマンサクの花 | ||||
|
所在地 | 八王子市廿里町1833-81 多摩森林科学園 | ||
| 科・属など | マンサク科マンサク属 常緑低木 | |||
| 見どころ | 早春にまだ葉が開く前、写真のように花を咲かせます。そのため、名前も「まず咲く」が訛ったという説と、満開の様子を表現 した「満作」という説があるほど見事な咲きっぷりでした。 | |||
| 撮影者 | 山田紀子 | |||
| 22.樹皮を製紙用の糊(のり)に使ったことからノリウツギ | ||||
|
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817 箱根湿生花園 | ||
| 科・属など | アジサイ科アジサイ属 落葉低木 | |||
| 見どころ | ノリウツギは別名を「ノリノキ」または「サビタ」と呼びます。ユキノシタ科アジサイ属に属し、日当たりの良い山野に生えて います。神奈川県内では丹沢、箱根、県央の丘陵地に自生。 | |||
| 撮影者 | 山田紀子 | |||
| 23.高原といえばシラカバ(白樺)を連想します | |||
|
所在地 | 長野県諏訪郡富士見町 八ケ岳 | |
| 科・属など | カバノキ科カバノキ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | シラカバは山火事の焼け跡にいち早く根づく繁殖力と生命力の旺盛さがあります。また幹は白い皮で覆われていますが、枝の木肌 は黒っぽい。 | ||
| 撮影者 | 山田紀子 | ||
| 24.日吉・松の川緑道のモモ(桃) | |||
|
所在地 | :横浜市港北区高田町 松の川緑道沿いの畑 | |
| 科・属など | バラ科モモ属 落葉小高木 | ||
| 見どころ | 先週、6月第2週、もうこんなに色づいていました。日吉の隣駅、綱島駅周辺一帯は戦前、岡山県と並ぶ日本の桃の二大生産地 でした。日吉でも現金収入となる桃を栽培する農家がかなりの軒数あったという話を日吉に住んでいたころ、隣のおじいちゃんから聞いたことを思い出しました。 ※今でも栽培「綱島桃」の花16ページNO.16をご覧ください。 |
||
| 撮影者 | 山田紀子 | ||
| 27.3ページNO14掲載のエゴノキの仲間、ベニバナエゴノキ | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区高田西 民家の庭 | ||
| 科・属など | エゴノキ科エゴノキ属 落葉小高木 | |||
| 見どころ | 高さ10㍍になる落葉高木。雑木林を代表する花木の一つですが、今まで見てきたのはみな白色でした。初めて紅色のエゴノキを見ました。しかも、こんなに大きな木に育っているのは、きっと珍しいのではないでしょうか。 | |||
| 撮影者 | 山田紀子 | |||
| 28.意外と地味な ナンキンハゼ(南京櫨)の花 | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町3丁目 マンションの庭 | |||
| 科・属など | トウダイグサ科シラキ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | ナンキンハゼの実が1ページNO.35と12ページNO.03に掲載されています。穂のようにたくさんついた雄花が先に咲き始めます。雄花が咲き終わって穂から落ちたころになって、穂の付け根のところの小さな穂が伸びます。小さな穂には、付け根の方に数個の雌花、先の方に多数の雄花がついていて、まず雌花が咲き、その後雄花が咲きます。紅葉の方が素晴らしいですね。 | ||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.07.03 | ||
| 29.さぞ、栃餅がたくさん作れるでしょう。トチノキ(栃の木)の高木 | |||
|
所在地 | 神代植物園東京都調布市深大寺北町1-4 神代植物園 | |
| 科・属など | トチノキ科トチノキ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 1ページNO2に掲載の「ベニバナトチノキ」と同種のトチノキです。写真右下に写る人の背丈とくらべ、樹高をご想像くださ い。枝先に円錐状の穂に花をいっぱい咲かせているのが見えます。果実は9月に熟すと割れ、1~2個の大きなタネを出します。このタネを蒸して杵でついたのが“栃餅”です。この花の蜜はミツバチの好物で、養蜂家にとってもトチノキは大切な樹木の一つです。※秋のトチノキ11ページNO.32参照。 | ||
| 撮影者 | 山田紀子 | ||
| 30.春一番に黄色い花で春到来をつけるサンシュユ | |||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区馬場2丁目20-1 鶴見馬場花木園 | |||
| 科・属など | ミズキ科ミズキ属 落葉小高木 | ||||
| 見どころ | ミズキ科の落葉高木で江戸時代、薬用として朝鮮から渡来しました。春には黄色の小花をいっぱい咲かせることから別名「ハルコガネバナ」とも言います。また、秋には真っ赤な実をつけ、別名「アキサンゴ」とも呼ばれます。日本薬方に収録されていて、止血、解熱剤の作用があります。 ※花は14ページNO.11に、赤い実が11ページNO.2に掲載。 |
||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||||
| 32.材質が強く、弓の材料となるマユミ | |||||
|
所在地 | 横浜市鶴見区馬場2丁目20-1 鶴見馬場花木園 | |||
| 科・属など | ニシキギ科ニシキギ属 落葉広葉低木~小高木 | ||||
| 見どころ | 落葉低木。花は初夏に新しい梢の根本近くにつく薄い緑で四弁の小花。果実は枝にぶら下がるようにつき、小さく角ばった四裂の姿。秋の果実の色は品種により異なりますが、どれも四つに割れ、鮮烈な赤い種子が現れます。材質が強いので、古来から弓の材料と知られ、それが名前の由来。 ※実がピンクになったのが11ページNO.16に、実が熟して割れピンク一色になった様子が14ページNO.13に掲載。 |
||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||||
| 34.葉が銀緑色でギンヨウアカシア(別名ミモザ)の実 | ||||
|
所在地 | 横浜市都筑区北山田 わが家の近くの民家 | ||
| 科・属など | ネムノキ科(またはマメ科)アカシア属 常緑小高木 | |||
| 見どころ | マメ科アカシア属の高さ8~15㍍になる常緑高木。明治末期にオーストラリアから来たというから植樹の歴史は古い。春、黄色 の小さな花が多数集まった球状の花序を房状にたくさんつけます。この花に人気があります。写真は花が終わってインゲン豆のような実が垂れ下がっている様子です。 ※いま人気のミモザの仲間3種14ページNO.12、13ページNO.22です。 |
|||
| 撮影者 | 山田紀子 | |||
| 39.東横線武蔵小杉駅頭で毎日乗客を送迎する、カツラ(桂) | |||||
|
所在地 | 川崎市中原区小杉町 東横線「武蔵小杉駅」前 | |||
| 科・属など | カツラ科カツラ属 落葉高木 | ||||
| 見どころ | 30㍍にもなる落葉高木。なにしろ、雑踏の駅から出て、このカツラの木を見ると本当に心が癒されます。目にしみるような深い緑の丸い葉、縦に割れる目が入る木肌、このカツラの特徴です。鎌倉彫の材になり、葉から抹香を作ります。 | ||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||||
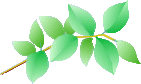

写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2009.6.18~ | 掲載23種 |
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
さくいんのページへ戻る