木花-World TOPへ戻る
次ページNO.5へ
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
|
所在地 | 東京都文京区白山 3-7-1 小石川植物園 | ||
| 科・属など | モクレン科ユリノキ属 落葉高木 | |||
| 見どころ | 「ユリノキ」は樹高15メートルと高い。花は高い枝の茂った間に咲くので気がつきません。花からは多量の蜜が採れます。明治23年大正天皇が皇太子だった頃に「小石川植物園」を訪ね、そこにある日本最古の種木をご覧になられ、その木を「ユリノキ」と命名したとされます。※花は1ページNO.15 と 新宿御苑のユリノキの大木と花が20ページNO.19に載っています。 | |||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
| 6.大きな木の枝先に多数の小さな花をつけたケンポナシ | ||||
|
所在地 | 東京都文京区白山 3-7-1 小石川植物園 | ||
| 科・属など | クロウメモドキ科ケンポナシ属 落葉高木 | |||
| 見どころ | 樹高は15〜20メートルになる。6〜7月にかけ淡緑色の小さな花をたくさん着けます。ちょうど、私が撮影していると若い女性が「このナシの実は鳥も食べないくらいマズイわよ」と教えてくれました。でも材木は木目が美しく、狂いが少ないので家具や器具に使われるそうです。※実は11ページNO.6参照。 | |||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
| 8.わが家のブルーベリーの実 | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 | ||
| 科・属など | ツツジ科スノキ属 落葉低木果樹 | |||
| 見どころ | 写真の果実が熟すと、濃い青紫色になることから「ブルーベリー」と呼ばれます。この実は視力回復、眼病に効くと需要が伸び、ジャム・健康食品などに加工品が多く売られています。千葉県木更津市など全国各地に地域ぐるみの栽培地が増えています。わが家のは、鉢植えながら今年は大収穫が期待できます。これで、わが家は“眼医者いらず”(?) | |||
| 撮影者 | 八城幸子 | |||
| 12.四季咲き、年4回実がなるフクシュウキンカン(別名大実金柑) | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町1丁目 鳥原さん宅の庭先 | |
| 科・属など | ミカン科キンカン属 落葉低木 | ||
| 見どころ | 鳥原さん宅の奥様のお話では「四季咲きで年4回実がなります」。植物図鑑で調べると、中国原産の「フクシュウキンカン」で一般に「オオミキンカン(大実金柑)」と呼ばれているもの。味は「通りがかりの中学生などが採って口にしますが、酸っぱくて捨てて行きますね。野鳥さえ食べません」と奥様。砂糖漬けやマーマレードなどに加工するのが良いそうです。 | ||
| 撮影者 | 岩田忠利 | ||
| 13.美味しそうなヤマモモ | |||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町2丁目 民家の庭 | |
| 科・属など | ヤマモモ科ヤマモモ属 常緑高木 | ||
| 見どころ | 和名の由来は山に生えたモモのような果実をつける樹木であることから、ヤマモモ。高さ15㍍、幹60㌢にもなる常緑高木。日本では房総半島以西から台湾、フィリッピン,済州島、中国に分布。甘酸っぱい味として親しまれるこの木は、庭木としても高価な値段で取引されます。 | ||
| 撮影者 | 石川佐智子 | ||
| 17.マレーシアの国花、ハワイ州の州花のハイビスカス | ||||
|
所在地 | 静岡県伊豆熱川温泉 ホテル庭園 | ||
| 科・属など | アオイ科ハイビスカス属 常緑低木 | |||
| 見どころ | 熱帯・亜熱帯地域に分布するアオイ科フヨウ属の野生種から生まれた花。園芸品種が豊富で花色が赤、ピンク、黄色、白などが あります。寒さに弱いので鉢植えにして冬は室内に入れるのが一般的栽培法です。温度管理を保てば、毎年花を楽しめます。写真の黄花は珍しく、熱川温泉の温室内のものです。ハイビスカスの赤い花が下記へ、白い花が9ページNO.19に載っています。 | |||
| 撮影者 | 守谷明子 | |||
| 23.生長力旺盛で樹高15メートルにもなるアカメガシワ(赤芽柏) | |||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町 新吉田医院駐車場 | |
| 科・属など | トウダイグサ科アカメガシワ属 落葉高木 | ||
| 見どころ | 道端の土手、川岸などに多く、荒地でもどこでもぐんぐん育ちます。新芽が赤く、柏の葉のように植物を乗せたことが名前の由 来です。雌雄異株で写真のように雄花も雌花も穂状に立ち上がり、甘い香りを漂わせます。 | ||
| 撮影者 | 守谷明子 | ||
| 20.黒松はオマツ(雄松)、赤松がメマツ(雌松) | |||
|
所在地 | 静岡県伊豆熱川温泉 ホテル庭園 | |
| マツ科 マツ属 常緑針葉高木 | |||
| 見どころ | 樹皮に黒みがあることから「黒松」、葉先が鋭く、松かさが大きいことから「雄松」と呼んでいます。新芽の基部に雄花がつき 、新芽の先端に雌花が着いています。松かさは開花の2年後に熟し、翼のあるタネを風に飛ばします。※黒松の実は7ページNO.36 参照。 | ||
| 撮影者 | 守谷明子 | ||
| 24.雨に濡れる、ナツツバキ(拡大) | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島西1-14-26 横浜市綱島地区センターの庭 | ||
| 科・属など | ツバキ科ナツツバキ属 落葉高木 | |||
| 見どころ | 2ページの28番に箱根山中のナツツバキが載っていますが、雨の中の白い大きなナツツバキがあまりに清楚で綺麗なのでカメラに収めました。ツバキといってもヤブツバキなどと別属です。 ※箱根山中のナツツバキの花、2ページNO.28 参照。 |
|||
| 撮影者 | 守谷明子 | |||
| .29.昔の旅人はこの実を食べ、疲れをとって、また旅を続けたマタタビ | ||||
|
所在地 | 群馬県みどり市 渡良瀬渓谷 | ||
| 科・属など | マタタビ科マタタビ属 落葉つる性木本 | |||
| 見どころ | 山野に多いつる性の落葉樹。夏場になると枝の上部にある葉が白くなるので、マタタビの木だけは遠くから分かります。花は6〜7月に香りの良い白い花を 咲かせ、10月に熟す実は塩漬けや果実酒にします。「猫にママタビ」の諺どおり、現代の猫も大好物でしょうか。 | |||
| 撮影者 | 山田紀子 | |||
| 28.実の形が金平糖のような球果で変わっている、コノテガシワ(児の手柏) | ||||
|
所在地 | 川崎市宮前区下有馬 民家の庭 | ||
| 科・属など | ヒノキ科コノテガシワ属 常緑針葉高木 | |||
| 見どころ | ヒノキ科に属する木の姿が、枝が直立し、魚の鱗のような葉で裏表がない、と独特です。果実の形も金平糖のようで珍しい。※花はこんな花、15ページNO.18 です。 | |||
| 撮影者 | 山田紀子 | |||
| 31.新芽が“山菜の王様”、タラノキ | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区下田町6丁目 民家の庭 | ||
| 科・属など | ウコギ科タラノキ属 落葉低木 | |||
| 見どころ | 昭和四十年代初め、日吉に移り住んだ頃、現日吉1丁目の丘陵地には住宅もまばら。あちこちの空き地に伸び放題のタラノキがたくさん生えていて美味しそうな新芽がニョキニョキ出ていても誰も採る人がいませんでした。それは、幹や枝先まで鋭いトゲがあるのを 恐れていたからでしょうか。 | |||
| 撮影者 | 岩田忠利 | |||
| 34.都会の中で見かけたナツミカンノキ | ||||
|
所在地 | 東京都文京区白山 5-31-26 白山神社 | ||
| 科・属など | ミカン科ミカン属 常緑小高木 | |||
| 見どころ | 晩秋に色着きますが、春先まで酸味が強く食用には向かない。明治以降、夏に味わえる貴重な柑橘類として認められ、広く栽培されるようになりました。※実は12ページNO.11でご覧ください。 | |||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
| 35.セイヨウミザクラ(西洋実桜)、いわゆる、おなじみのサクランボ | ||||
|
所在地 | 山梨県南アルプス市飯野 | ||
| 科・属など | バラ科サクラ属 落葉高木 | |||
| 見どころ | バラ科のサクラ属の落葉高木。果実を採るために栽培されていて主な産地は山形・福島・長野・山梨の各県。サクランボの果実は雨に弱く、ハウス栽培されています。現在はいろいろの品種が出回ってます。 | |||
| 撮影者 | 石川佐智子 | |||
| 38.初夏の雑木林でひときわ目立つ、ミズキの花 | ||||
|
所在地 | 横浜市港北区高田東2丁目 高田第4公園 | ||
| 科・属など | ミズキ科ミズキ属 落葉高木 | |||
| 見どころ | 葉脈がくっきりしてハナミズキの葉に良く似た葉が茂った落葉高木。子供たちが遊ぶ広場が暗くなるほどうっそうと茂っています。小さな花が多数集まった花序は遠目に白く煙るように見えます。枝が車状に出て独特な樹形になるので別名を「クルマミズキ」と呼び、早春に枝を切ると樹液が滴り落ちることが「ミズキ」の名前の由来。秋の黄色い葉もイチョウ並みに美しい。※実は10ページNO.13 参照。 | |||
| 撮影者 | 佐野紀子 | |||
..
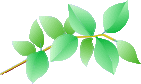

写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。
| 以下の情報の中の“欠番”は、低木・小低木の一部、ツル性植物などで、「野草-World」へ移しました。 | 2009.6.11〜 | 掲載28種 |
さくいんのページへ戻る