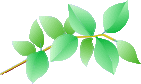| 01 木全体が花序で淡黄色になり、甘い香りが強烈! スダジイ(すだ椎)の花 | ||||||
|
所在地 | 横浜市港北区綱島東1丁目 民家の入口 | ||||
| 科・属など | ブナ科シイ属 常緑広葉樹 | |||||
| 見どころ | 7ページNO.10に樹形が、名木古木4ページNO.24に駒岡八幡宮の大木が載っています。花期は5〜6月で辺りいちめん栗の花と同じような強烈な香りが漂います。葉は先の方に鋭い鋸歯が少しあるか、または全くない場合もあります。葉の裏面は金褐色に見えるのが特徴だそうです。秋にはどんぐりが熟します。子供のころから、落ちているとつい拾いたくなったドングリですが、炒って食べると少し甘味があり結構おいしいとか? | |||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.05.14 | |||
_thumb.jpg)