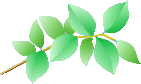| 5.葉を切ると抹香の香りがする、シキミ(樒) | |||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町2丁目 金蔵寺境内 | |||
| 科・属など | シキミ科シキミ属 常緑高木 | ||||
| 見どころ | 仏前に供える木として知られています。仏事に用いるため寺院に植えられていることが多いようです。花は、3~4月に咲き薄白色で細長く、ややねじれたようになります。果実は扁平で周囲に8本の突起が出ています。八角形の袋形が特徴的です。花、葉、茎、根、実まですべて有毒で、特に種子は猛毒だそうです。ご注意を! ※花は14ページNO.18で。 | ||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | ||||