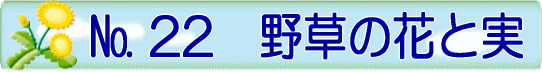| 13 カーネーションなど園芸品種の親、タツタナデシコ(龍田撫子)の花 | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町2丁目 駐車場 | |||||
| 科.属など | ナデシコ科 ナデシコ属 常緑多年草 | ||||||
| 見どころ | 別名はサクラナデシコ(桜撫子)。原産地はヨーロッパ東部〜南部。明治末期に渡来。草丈は30センチ程度です。葉は線状で春〜夏、灰緑色の葉を密に茂らせ、5〜7月ころ、花径3〜4センチの一重で、切れ込みのある桃色地の花の中央に赤い輪模様が入った花を咲かせます。カーネーションなど園芸品種の親でもあります。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.5.14 | ||||






_thumb.jpg)