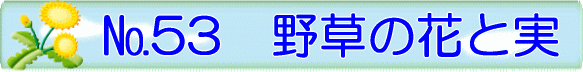| 03.米粒ほど小さな花、ハシカグサ(麻疹草) | |||||||
|
所在地 | 東京都港区白金台5-21-5 国立科学博物館付属 自然教育園内 | |||||
| 科.属など | アカネ科ハシカグサ属 1年草 | ||||||
| 見どころ | 水田の畦、用水路脇、湿地や溜池畔、渓流畔、湿った林床などに生える1年草。草丈は20〜40センチ。各節から根をだし、先のほうはしばしば斜めに立ち上がります。茎の断面は四角で、枝分かれして広がります。葉は2〜6センチの卵形〜狭卵形で対生し、茎の先端や葉腋から花径4ミリほどの白い小さな花をつけ、花冠は筒状で4裂します。花期は8〜9月。葉が乾くと赤褐色に変わる様子が、ハシカの発疹が乾くにつれて赤から褐色に変わる症状に似ているためハシカグサと名付けられたといいます。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.9.1 | ||||