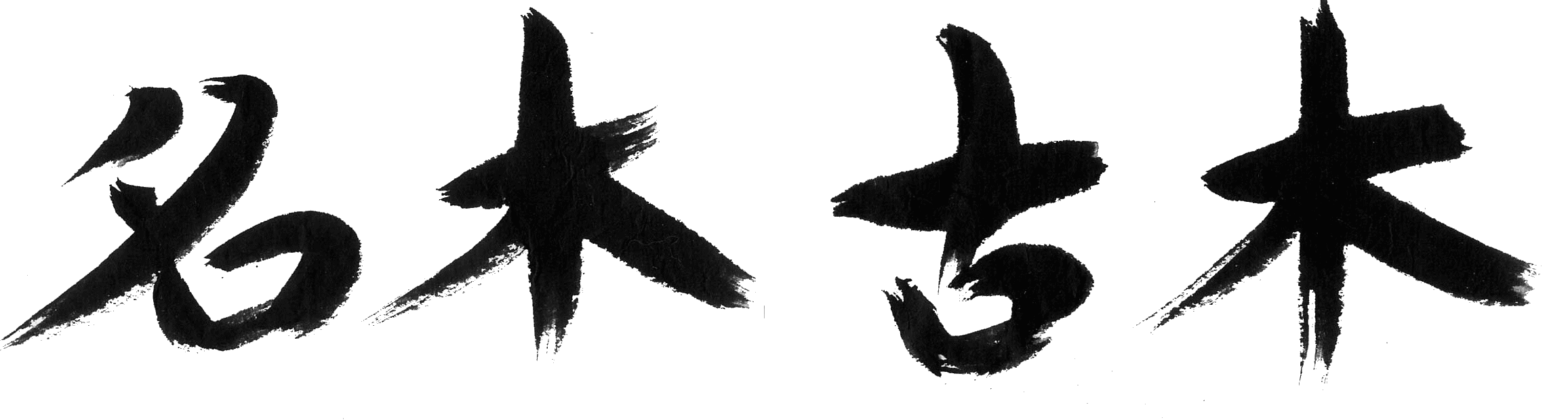小雨降る早朝の滝桜。角度を変えると、また“異なる美しさ”を見せてくれます |
|
生い立ち&
見どころ |
「日本三大桜」といえば福島県三春滝桜、岐阜県根尾谷の薄墨桜、山梨県山高神代桜ですが、最も人気の高いのがこの三春滝桜・・・。
江戸時代の天保年代(1830〜1843)、国学者で家人の加茂季鷹(かものすえたか)がこの滝桜の美しさを短歌にしたことからその名が広く知れわたり、三春藩主の御用木として保護されました。
1000年を超える風雪に耐えた巨樹であるだけでなく、樹高は12m、根回りは11m、幹周りは9.5m、枝張りは東西22m、南北18m、四方に枝を広げた紅枝垂桜の美しさと貫禄は、まさに日本の桜の代表格です。
大正11年(1922年)上記の桜2本とともに国の天然記念物に指定され、平成2年(1990年)には「新日本名木100選」の名木ベスト10に選ばれ、桜の名所ランキングでは常に第1位の評価を得ています。
私が訪れた前年、平成17年(2005年)1月の大雪で枝が十数本折れる被害に見舞われたことは大変残念でした。しかし、写真のようにその優麗の美は筆舌に尽くしがたいものがありました。
|