| 05 全草に悪臭がある、ドクダミ(毒痛み、毒溜み)の花 別名:ジゴクソバ(地獄蕎麦) | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新吉田町の民家 | |||||
| 科.属など | ドクダミ科ドクダミ属の多年草 | ||||||
| 見どころ | 住宅周辺や道ばたなどに自生し、特に半日陰地を好みます。開花期は5〜7月頃で、茎頂に4枚の白色の総苞(花びらに見える部分)のある棒状の花序に、花弁も、萼もなく、淡黄色の雄しべと雌しべがあります。強い臭いや、毒と付く名前のせいもあり、毛嫌いされる植物の一つですが、本来は毒草ということではなく、民間薬として腫れ物、皮膚病などに利用され、「十薬」とも呼ばれます。解毒や痛み止めの薬という意味の「毒痛み」か「毒溜め」から名前の由来とされています。 | ||||||
| 撮影者 | 八城幸子 | 撮影日 | 2011.6.19 | ||||














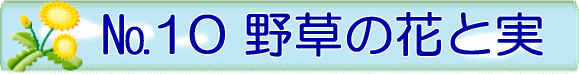




















_thumb.jpg)



_thumb.jpg)



