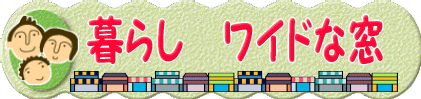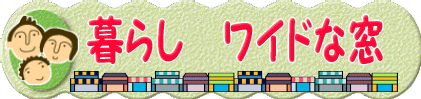幻の授業……地面に文字を書く
ある日こんな情報を耳にした。
「学校を始める。勉強をしたい者は明日昼食後、広場のパンの木の下に集まるように……」
わたしは期待を胸に指定された場所に出向いた。一人の青年がわたし達を迎えてくれた。
「このような木の枝を拾ったら、もう一度集まりなさい」
言われるままに再び先生を囲んだ。彼は、地面に<おひな様>と大きく書いた。美しいと思った。
「一字一字よく見て、みんなもこの通りに書いてごらん」
|
|
わたしは、一字書いては次の「ひ」の字をみつめ、次を書いては「樣」の字を凝視し、手本の文字と自分の筆跡の間を往復した。震えるような感動を覚えながら……。
米軍当局からの圧力があったのか、国民学校の訓導であった青年が再び広場に姿を見せることはなかった。(戦後の占領政策によって国民学校教育は完全に否定された)
|

筆者のホームページ「ドキュメント少年の戦争体験」から |
|
内地の学校で再び習字を……
父と幼い二人の弟は島の土となり、母と次弟と3人が21年の冬、浦賀の地に降り立った。
父の生家である叔父の家から旭村国民学校(現平塚市)に通うことになった。何年ぶりかで再び筆を執った。文字を書く喜びがフツフツと湧いた。懐かしい墨の香りは、父のにおいを思い出させた。
「栗原さんはこれをお使いなさいね」
先生がお持ちの習字用具一式をお貸しくださった。黄ばんだ粗末な半紙も当時のわたしにとってはまぶしく見えた。
一枚書き上げると教卓の前に一列に並ぶ。先生は一字一字朱をいれてくれた。赤い○や◎が魅力的だった。なかにはハナマルをもらう子がいた。順番を待つ子たちから歓声があがった。あまりにもひどい字は先生が修正してくれた。ため息が漏れた。
国民学校の頃の極端な緊張はなく、教室内の空気が温かく楽しげに感じられた。
窓外に見える麦の葉は大山颪(おろし)の冷たい風に揺すぶられていたのだが……。
|
書道の講義を受ける
後年わたしは、教師になるため横浜国立大学学芸学部に進んだ。アルバイトで学費を稼ぎながらの学業は資格を得るためだけの中途半端なものに終わった。
ただ、中山鶴雲先生の「書道筌蹄」(しょどうせんてい)だけは2年続けて受講した。貧しさと時間的な余裕のなさで、どうかするとささくれがちの日々のなか、墨をするひとときが安らぎを覚える唯一の時間であったのかもしれなかった。
|
本格的に書道をやりたい
横浜市立西寺尾小学校時代職員たちが句作に励んでいた。あるときの句会で
湧き水に春待つ芹のふるえたる(季語 春待つ)
この拙句が「天」の評価を得た。
南の島で生まれ育ったわたしに冬の寒さはこたえた。母が励ますように声をかけてくれた。
「もうすぐ春が来るよ。春は暖かいよ」
それで「春を待つ」心でじっと寒さに耐えることができた。
叔父の家は通称「池の上」と呼ばれた。池はヤブツバキの花を映すほど澄んでいた。池の底のあちこちから溢れでる地下水の動きを目にすることができた。溢れた池の水は叔父の家の垣根に沿って小さな流れとなった。流れの中に「春待つ芹」を発見したのだった。
当時の記憶が句を生んだのである。
恒例により選者から直筆の短冊がいただけることになった。その墨跡の美しさに心を奪われたわたしは、俳句と書道を本格的に学んでみたくなった。
ある年の夏、横浜市小学校国語研究会の「書写・書道実技研修」を受講した。書道に親しむ直接の契機となった。
|
大日本書芸院に入会し書を学ぶ
2年後、大日本書芸院の会員になった。書道の普及を目的に阿部翠竹先生が創設された全国的な組織である。本部は横須賀市坂本町にあった。
努めて本部に出向くようにしていたので、翠竹先生の謦咳(けいがい)に接する機会も一度ならずあった。
担任の先生の板書が、小学生のわたしの目にとても美しく見えた。自分もいつかあのような文字が書けるようになりたいと思った。このときの思いが書家を志す動機となった。
「あなたの教室にも、わたしと同じような思いであなたの板書を見つめている子がいるかも知れない。普段から心して美しい文字を書くように努めなさい」
このお言葉とともに直筆の書を頂いた。「盛業在誠勤」という文言が胸に響き、家宝として大切にしている。
はじめて東京都美術館で開催される大日本書芸院展に出品を許されるようになったときはうれしかった。が、会場に足を運び、改めて愚作に対面したときのみじめさは今でも忘れることができない。なさけないほど不出来だったのである。
以後毎回のように出品をつづけた。自分の未熟さや課題が他の作品のなかに置かれたことでよく見えるようになったのである。
|