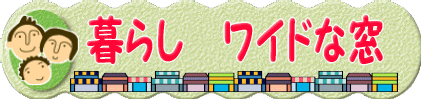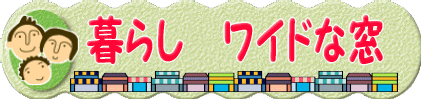新しい憲法……戦争放棄
同年5月3日日本国憲法が発布された。
第9条は戦禍を体験した栗原母子を喜ばせた。戦争をしない国、軍隊を持たない国になったのだ。
軍人を希望していたことなど想念にのぼることもなくなった。
新しい教科書
新しい教科書が配られた。第6期国定国語教科書である。(現行のような教科書会社発行検定教科書は昭和24年からである。)敗戦直後で、紙質は悪く挿絵も少なかった。
外見は粗末でも、内容はすばらしかった。
|
忘れられない教材……百田宗治の詩
70年近くなるのに記憶に残っている教材がある。百田宗治の詩「じゃがいもをつくりに」である。
じゃがいもつくりに 百田宗治
じゃがいもをみると ぼくは 北海道のいなかを思い出す
みわたすかぎりのじゃがいも畑のうねの向こうに
いつもぽっかりとういていた蝦夷(えぞ)富士
|
|
あの山のすがたが 小さいころのことを
いろいろ思い出させる
ぼくが津軽海峡をこえて内地にきたのは
ぼくの2年生のときだった
津軽海峡の海の水が こいみどり色にゆれて
ぼくは 船のかんぱんに おかあさんとふたりで立っていた
北海道の家には うしが4頭いた
みんなちちうしで ぼくによくなれていた
こむぎこで おいしい やわらかいパンもやいた
おかあさんがパンをやくそばで
ぼくは いつも本を読んでいた
ぼくのいすは 小さなゆりいすで
その下に いつもかいねこのメリーがいた
アカシアの花が風にゆれ
畑では いちごがでさかりだった
|
|
おとうさん
ぼくは 大きくなったら またおかあさんといっしょに北海道へいきます
北海道へいって じゃがいもをつくります
それから えんばくをつくります
ぼくは おとうさんと同じように ちちうしをかって
自分でバターをつくります
やぎもかいます
やぎ小屋のまわりには おかあさんのおすきなライラックを植えましょう
おとうさんに 負けないように働きます
日本のこくぐらは 北海道だといいます
さっぽろに農学校をつくられたクラーク先生もおっしゃった
「青年よ 大きな望みをもて」
ぼくは 大きくなったら どうしても北海道へいこうと思う
北海道へじゃがいもをつくりにいこう
おかあさんをおつれして
デンマルクの農業のことを勉強して
ぼくは、いい農夫になろう
|

わたしも農夫の姿を夢見た
|
|
わたしも「いい農夫になろう」
戦死だろうか、父を亡くした少年が「大きくなったら北海道でジャガイモをつくろう。」「いい農夫になろう。」と将来の夢を語った詩である。
一読して感動を覚えた。自分の境遇にも重なる「ぼく」に共感し、自分も将来「いい農夫になろう」と思ったのだった。
|
|
|
|
|