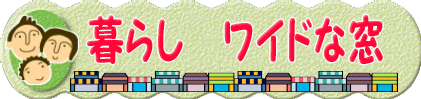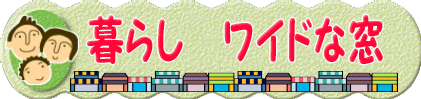戦争の悲惨さが分からない社会(?)
数日前の新聞に「被爆者に『死に損ない』」の見出しで小さな記事が掲載された。(2014/6/8 神奈川新聞)
修学旅行で長崎を訪れた公立中3年の男子生徒数人が、被爆者で語り部の森口さん(77)に向かって「死に損ないの、くそじじい」と暴言を浴びせたという。
学校に抗議した森口さんは取材に対して次のようにコメントしている。
こんな経験は初めてで悲しい。戦後69年が経ち、戦争の悲惨さが分からない社会の雰囲気の中で子供たちが育っているのではないか。
|
原爆体験の風化
記事を一読したとたん、記憶の底に沈んでいたある日の授業のヒトコマがまざまざと思い出された。
あれは確か昭和30年代半ばごろのことで、私は40代の中堅教師だった。
6年生の担任だった。授業のヒトコマというのは今西祐行の「ヒロシマの歌」(平和教材)をわたしが音読したときのことである。わたしは、原爆の語り部になったつもりで心を込めて冒頭の部分を読み始めた。
わたしはそのとき、水兵だったのです。
広島から30キロばかりはなれた呉の山のなかで、陸戦隊の訓練をうけていたのです。そしてアメリカの飛行機が原爆をおとした日の夜、7日の午前3時ごろ、広島の町へ行ったのです。
|
|
町の空は、まだ燃えつづけるけむりで、ぼうっと赤くけむっていました。チロチロと火の燃えている道をとおり、広島駅のある東練兵場へ行きました。
ああ、そのときのおそろしかったこと。ひろい練兵場の全体が、黒ぐろと、死人と、動けない人のうめき声で、うずまっていたのです。
やがて東の空がうすあかるくなって、夜が明けました。わたしたちは、地獄のまんなかに立っていました。ほんとうに、足のふみ場もないほど人がいたのです。暗いうちは見えませんでしたが、それがみなおばけ。目も耳もないのっぺらぼう。ぼろぼろの兵隊服から、ぱんぱんにふくれた素足をだして死んでいる兵隊たち。べろりと皮ははがれて、首だけおこして、きょとんとわたしたちをながめている軍馬。だれもはなしている者はありませんでした。ただ、うなっているか、わめいているばかりです。そして、まだまだ、町のほうから、ぞろりぞろりと、おなじような人たちが、練兵場にながれてくるのです。
読み聞かせが「それがみなおばけ。目も耳もないのっぺらぼう。・・・」あたりにさしかかった時、誰かがくすくす笑った。すると笑い声は教室全体に拡がり、わたしの耳を襲った。
わたしはショックを受けた。「最初に笑ったのは誰か」ではなく「戦争の風化がここまで進んでいたのか・・・」との思いからくる軽い失望感みたいなものだった。クラスが変わる度に語ってきたサイパンでの戦争体験は、この日を境にいっそう熱を帯びるようになっていった。
再び、長崎の被爆者で語り部・森口さんに対する生徒たちによる暴言のことに戻る。
記事によると、今後教育委員会は「生徒への人権教育や教職員の研修強化に努める」という。わたしは、更に一歩すすめて学校教育における近現代史の在り方に問題はなかったかどうか・・・わたし自身の実践も含めてだが、再点検してみる必要があるのではなかろうかと思った。ともあれ、暴言を浴びた森口さんのコメントには共感を覚えた。

農民に銃口を向ける米兵
『十五年戦争と沖縄』から |
|
忘れては、いけない。沖縄戦の悲劇
川崎市川崎区在住の座覇光子さん(74)が、「集団的自衛権を考える」シリーズ(2014/6/13 論説・特報欄 神奈川新聞)で一石を投じておられる。横浜市鶴見区に生まれ終戦後川崎に移った彼女は、両親の故郷沖縄を訪ね歩いては、20万を超える犠牲者を出した沖縄戦の体験談に耳を傾けてきたそうだ。
彼女は、沖縄の悲劇の語り部として小中学校、高校へしばしば足を運ぶ。聞き手の中学生に向かうと、まず「沖縄の中学生になったつもりで聞いてほしい」と切り出す。
「戦争はみんなのおじいちゃんの世代のことだけど、生き延びた本土の人たちは、多くの犠牲を生み本土の防波堤になった沖縄のおかげで存在している」
|
「沖縄の人なら必ずと言っていいくらい身内や親戚に戦争で亡くなった人がいる。今、集団的自衛権が議論されているのはただただ、残念。言葉が見つかりません」
沖縄戦における海軍の指揮官太田実少将が、自決する1週間前に海軍次官宛に送った最後の電文がある。
<沖縄県民斯く戦へり。県民に対し後生特別のご高配を賜らんことを>
沖縄をめぐる戦後の諸施策をみれば、太田実少将が最後の電文に託した願いはいささかも顧慮されることがなかったのではなかろうか。
次世代に語り継ぎたい、わたしの戦争体験
わたしはいま港北区「まちの先生」として少年時の戦争体験を語り伝えている。一つの事例として横浜市立初音ヶ丘小学校6年生対象のスライドショーの様子を報告してみたい。(平成25年12月10日 社会科の授業として)
以下は事後における児童たちの反応の一部である
6年生の感想文「思ったこと・感じたこと」
◆ 戦争体験を聞いて目が熱くなりました。今の日本は戦争がなく平和な日常を送っていますが、昔の日本は簡単に銃声が聞こえた環境だったというところに驚きました。また、昔は「敵からもらったものは毒」「つかまったら殺される」という教育が普通に行われていたと聞き、今の自分も考え方が変わっていたかもしれないと思うと怖く感じました。(田之上拓広さん)
◆ 戦争ってこわくて悲しいことなのだと思いました。今では簡単に飲める水もとても大切なものだと気づき、これからは大切にしようと思いました。お父さんが撃たれた銃声のこと、栄養失調で死んでしまった二人の弟のことなど、つらく悲しかったと思います。・・・戦争のない国になってほしいです。(金子花菜さん)
◆ 初めて戦争体験者から話を聞いて、改めて戦争が恐ろしいものであることを感じました。そして自分たちは普通に食事ができて、お風呂に入ったりできることが幸せであると思いました。(田中香帆さん)
◆ 私は、戦争の話を生ではじめて聞きました。戦争を知らない私は、当時はすごく大変な毎日だったと思いました。今は、水はあって当たり前だけど水がない事を考えると、とても生きていけないと思いました。(谷口菜央さん)
◆ 私は、今までに戦争の話を聞いたことはありますが、くわしく聞いたのは初めてです。今日の話で色々なことを知りました。昔の学校では「つかまったら戦車にひかれる」「毒がもられている」などのことを小さいころから教えられていたのですね。小さいころから教えられたらきっとどんなことも信じてしまうと思います。空しゅうで爆弾が落とされると「目が飛び出る」「鼓膜が破れる」というのにおどろきました。(相澤海月さん)
◆ 私は戦争という言葉を聞くと「こわい」と思うけど、栗原さんの話を聞いて、ただ「こわい」と思うだけでなく、どんなに苦しい生活をしていたかなどと深く考えるようになれたと思います。(川邉百華さん)
◆ 教科書だと爆弾がどれほど大きい音なのかあまり分からないけど、実際に体験した人から聞くと本当に伝わってきました。(渡辺凜)
家族を失う悲しさ」「飢えと渇きの苦しさ」などへの反応が多く、平和な時代に生きる自分たちは幸せであることに触れた感想が目立った。
感想文で多い「伝えていきたい」
◇ はじめて聞きました。理解する力があまりないので不安だったけど、栗原さんのお話は分かりやすくて良かったです。これからもたくさんの人に、この体験を教えてあげてください。(嶺井琉花さん)
◇ 貴重なお話を聞けてよかったと思います。10年後の私は大人だから、戦争の苦しみを子供たちに伝えたいです。(下田玲奈さん)
◇ 当時の人々の苦しい生活を改めて知ることができました。私は、この悲しい事実を自分より後の世代にも伝えていきたいです。(木島直人さん)
◇ 栗原さんに話をしてもらって、少しだけ戦争について調べてみようかなと思いました。あまり聞けない話を聞かせてもらってよかったです。この話を次の世代の人たちにも伝えていきたいです。(高多優凪さん)
|
|
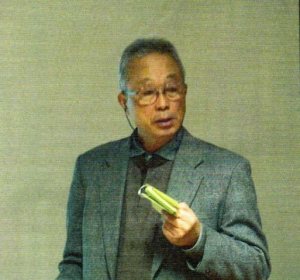
平成25年12月、横浜市立初音ヶ丘小学校6年生に戦争体験を話す筆者 |
|
◇ 今日聞いた戦争体験を次の世代、また次の世代にどんどん伝えていかないといけないなと思いました。(田之上拓広さん)
◇ もう二度と戦争をしてはいけないし、後の世代にもちゃんと戦争のことを伝えていかなければいけないのだなと思いました。(根本稜也さん)
◇ 戦争の話で聞いたことを新聞にのせて、小学生のみんなに見せたいと思います。栗原さんも、いろんな所へいって、体験したことをほかの子どもたちにも教えてあげてください。(大星凜さん)
◇ 戦争の体験談を聞いたことを知ってもらいたいのできかいがあれば伝えたいと思います。(正木里佳さん)
間接体験ではあるが「戦争体験を伝えていきたい」という声が予想以上に多かった。
平成5年夏。朝日新聞朝刊「声」の欄で、次のような中学生(14歳)の声に接した。
戦争がどれだけ恐ろしく悲惨かを知り、後世に伝えるためには、体験した人からそのときの気持ちや苦労を、思いを込めた言葉で直接聞くことが一番だと思う。
「とうよこ沿線」のホームページで手記「ドキュメント 少年の戦争体験」が公開されたとき次のような反響が寄せられた。30歳の若い父親(佐藤様)からである。
このような体験記を、様々な形で紹介していくのは本当に貴重ですばらしいことだと思います。・・・子供たちと、将来戦争とは・・・ということについて話し合い、私が聞いたあらゆる体験談や学んだ知識を残さず伝えていきたいと思います。それが、偉大なる先輩たち(戦争で亡くなった人々、戦後復興を支えた人々)が命を賭けて守り、そして作った日本という国への恩返しだと思います。
長崎の森口さん、沖縄の座覇さん、そしてサイパンのわたし。おたがいに平和の大切さを次世代に語り継ぎ、「海行かば」を歌う時代を再び迎えることがないように微力を尽くしていきたいと願う今日この頃です。
|