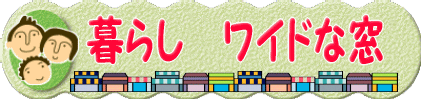|

�E�h�@�V�Ղ�̕��ʂ͏��Ȃ��B�E�̊����x�X�g���c |
|

�E�h�̐|���X�@�M����������Ă��|�� |
|
�@��
�@�����Ă̓^���i��j�̉�B������V�Ղ炪��Ԃł��傤���B�E�h�̓V�Ղ�ɔ��݂�����A���R�炵�����ł��B�A�Y�L�i�A�E�h�̓V�Ղ炾�ƍȂ��q�����H�ׂ܂����A�^���̉�ƂȂ�Ə����h������܂��B��݂������̂ŁA�r�[���ɂ悭�������\�ʂ�����ł��܂��܂����A�V�Ղ�ɂ͋����Ƃ������ƂŁA���̌�A������H�n�߂�ƁA�����{���Ɏ肪�L�сA���Lj��݉߂���Ƃ������ʂɂȂ��Ă����܂��B
�@�^���̉�͂T�����{���{�ł��ˁB�������ɃR�S�~������܂����A�E�h��^���̉��葐������̂悤�ȐL����������̂̋�݂͏��Ȃ��A�^���̉�Ȃǂ̔��x�߂ɂ͂��傤�Ǘǂ��f�p�Ȕ�������������܂��B
|

�ォ��^���̉�A�E�h�A�R�S�~
|
|
|

�R�ɂ͎|���������킹���� |
|
�@�瓇��
�@�t�̎R�̓^�P�m�R�Œ��߂������܂��B�^�P�m�R�ƌ����Ă��{�B�ł������̎q�̂��ƂŁA����ނ��Ă��܂��ƒ��a1.5cm���炢�ׂ̍����̂ł��B�t�L�Ǝϕt����������܂����A�ȒP�ɐH�ׂ�̂Ȃ�A�Ō�̔�ꖇ���c�����܂܃��b�v�Ŋ����ēd�q�����W�Ń`���������̂��}���l�[�Y�ŐH�ׂ�̂��荠�ł��B���ɁA�o�[�x�L���[�̍ۂɂł���t���̂܂܃A���~�z�C���ŕ��ŏĂ��A�����������v����ăA���~�z�C���Ɣ�����Ƃ���ɁA�ݖ����������炵�ĐH�ׂ�̂������葁�����������H�ו��ł��B�̂��Ă����璼���ɐH�ׂȂ��Ƃ����݂����̂ŕۑ��ɂ͌����Ȃ��ł��B
�@���傤�Ǎ����U���̒��{�����^�P�m�R�̂�̃s�[�N�ł��B�Ȃ̂ŁA���N���̋G�߂́u�R�Ŗ��q�v�Ƃ����j���[�X���悭����܂��B
|
�@�s�ҔE�J
�@��������H�ׂ������ǁA���܂�H�ׂ��Ȃ��̂��A�A�C�k�l�M�ł��B�A�C�k�l�M�̓����Ȃł����A���������Ȃ̒��ł����ɏL���j���j�N�A�j���A�l�M���ꓰ�ɉ���悤�ȏL�����Ɠ��ł��B
�@�H�ׂ��オ��ςŁA���͂̐l��Ƒ����ꏏ�ɐH�ׂĂ��Ȃ��ƁA�ƂĂ����f�őa�܂�܂��B�H�ׂ�ʂɂ����܂����A�x���Ƒ��A���A�r�����̑S�Ă������ԃA�C�k�l�M���̂��̂ŁA���ꂪ���͂�焈ՂƂ����܂��B
����ł��Ⴂ���͂��\���Ȃ��ɁA�^���t���W���M�X�J���ƃA�C�k�l�M�����Ƃ����җ�ȏL�C��тт��ē������Ă������̂ł��B���̓����́A�̂�ɍs���ƂȂ�ΌQ����ړ��Ăɂقڈ�N�������n�i���l�H�j���Ă��܂����B���n���Ă��̌�т�������肵�Ă���Ǝw��ɏL�����t���܂����A���̏L���������͏����Ȃ����炢�ł��B���̌�A���������ʂ����āA�o�R�̍ۂɓ��������Ă�����A�R���ŐH�ׂ郉�[�����̖��x�ɂ����̂�Ȃ��Ȃ�܂����B�C���X�^���g���[�����ɃE�B���i�[���A�C�k�l�M�Ƌ��Ɏύ���Ńr�[���Ƃ��������ƁA���R�̌��C���������Ă������̂ł��B���Ȃ݂Ɏύ��܂Ȃ��Ɛh���ł��B���̐h�݂��j���j�N�A�j���A�l�M����ł��傤���B
|

�A�C�k�l�M�̌Q���@�ӂ�ɏL�����Y��
�@�@�@���юR�n�z���W���}���ɂ� |
�@�@ |
�@
�@�ԓc�̋�
�@�c�����ɉ��l�̐ԓc�ŗ��e�ɘA����č̂����̂̓Z���i�ځj�������͂��ł��B�ԓc�̌l���ɒ���t���悤�ɐ����Ă����̂����łނ������āA������Ƀr�j�[���܂ɓ���č̂��Ă��܂����B
�@���R���l�̓c���ł����A���ɒ��ӂ����킯�ł��Ȃ��A�t�ɐH�ו������������Ȃ��āc�c�B�����l����ƒ��Ղ�������ł��ˁB
�@�Z���̓V�Ղ�����ŐH�ׂ��̂��q���Ȃ���ɔ��������āA�����̋ꂳ�ƍ����������ł��Y����܂���B
���̃Z���͖k�C���ł͌������܂���B�L���^���|��ɓ����悤�Ȕw��̂���Z���̓X�[�p�[�Ŕ����Ă��܂����A�l���ɔ����Đ����Ă����悤�ȃZ���͌������Ƃ�����܂���B�����͈�̓������̂Ȃ̂��A���x�X�[�p�[�Ŕ��������̂�V�Ղ�ɗg���Ă݂悤�ƍl���Ă��܂��B
|
|
|

�c���̋L�����h��R�̓V�Ղ� |
|
|