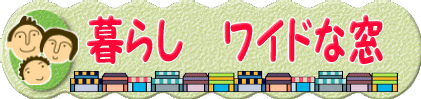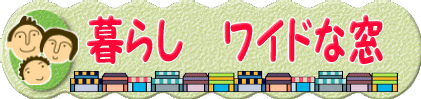昭和19年サイパン島の野外学級
わたしが3年生、弟が新1年生になった昭和19年からアスリート国民学校(サイパン島)へは通えなくなった。利夫は入学式の1日だけ学校の門をくぐった。翌日から二人そろって近くのジャングル(ジャングルの中の野外学級)に通った。1年生から6年生の男女が草の上に腰を下ろした。正規の授業はもうなかった。
風呂敷包みから教科書を取り出しても開いてみる気が少しも起きなかった。もはや音読を楽しむ環境でもなかった。「皇国民の錬成」を目的とした教育を受けた2年間、自学自習の態度が全く身につかなかったわたしだった。学校へ通う日を楽しみに待ち、やっと1年生になった利夫は、入門期の指導すら受けることなく放っておかれた。上級生でさえ途方に暮れているようだった。
同年6月11日昼頃、突然空襲に見舞われた。この時から栗原一家の逃避行が始まった。
15日米軍の上陸が始まると最初の洞窟を出て北のハグマン半島に向かった。新たな洞窟では飢えと渇きに苦しむ毎日だった。26日、父が不在のところを米軍に発見されススペ民間捕虜収容所(キャンプ)に連行されることになった。以後1年半抑留生活を送った。
民間捕虜収容所での勉強「おひな様」
|
来る日も来る日も遊びほうけてばかりいた。母は教育の機会から見放されたことで悩んでいるようだった。紙や鉛筆などの筆記用具はなく、教科書もなかった。学校そのものがないのでわたしの念頭から「勉強」という観念はすっかり消えてしまっていた。
そんなある日「学校を始める」との知らせを偶然耳にした。言われたようにパンの木の下に集まっていくと、元国民学校の若い男の先生が迎えてくれた。
|
| そのとき、先生が木の枝で地面に書いてくれた言葉が「おひな樣」だった。地面に書かれた美しい文字を懸命に真似たあの時の震えるような感動をいまも忘れることはない。
感動の記憶のなかに、ずっと消えずに残った疑問があった。先生が選んだ言葉がなぜ「おひな樣」だったのだろうか・・・。
アサヒ読本の復刻本を調べたら、「おひな様」は2年後期用の教材であった。
おひな様
春が來ました、おひなさま樣。 さあさ、かざってあげましょう。
まあ、お久しい、だいり様。あなたはいちばん上の段。
(3〜5連は省略)
あられ、ひし餅、桃の花、なたねの花も供えませう。
|

先生が木の枝で地面に書いた「おひな様」の文字を懸命に真似て書いたときの感動が今も忘れません
|
|
| 春の季節や桃の花を知らないばかりか、「おひな樣」を見たことのないわたしにとって、この教材は興味関心の外だったのだろうか。記憶に残らなかった。
それにしても、民間捕虜として収容所内に暮らす元国民学校訓導がこのような環境のなかにあっても国定教科書にこだわっていることに時代を映す鏡を見るような、ある種の感慨を覚える。
母子3人は、昭和21年1月浦賀港に上陸、兄弟ふたりは初めて父祖の地を踏んだ。冬枯れのなかで浦賀の町は静まり返っていた。
伯父の家で世話になることとなり、そこから旭村国民学校(現平塚市)に通った。1年遅れの編入学だった。わたしは再び3年生になった。担任は二宮先生という若い女教師だった。
|
教科書を手にした感動、その直後の衝撃
戦争が終わったせいか、教室の雰囲気は明るく活発だった。が、制度上は国民学校が続いており国定教科書を使っていた。長らく教科書と無縁だったわたしは、先生から3年後期用の教科書を受けとった瞬間、大きな喜びを感じた。が、国語の読本を開いてたまげてしまった。ほとんどのページが塗りつぶされていたのである。隣の子の教科書も同様だった。
島の国民学校で初めて教科書というものを手にしたときの小林先生のお言葉を改めて想起したのだった。
「教科書は天皇陛下様から賜ったものです。汚したり破ったりしてはいけません。踏んだり跨いだりしてもいけません。」
兵隊さんが銃を大切に扱うように、みなさんも教科書を粗末にしないように・・・と徹底して指導されたのだが・・・?
初めから順にページをめくっていくと南洋のヤシの木の風景写真があった。墨塗り前の復刻版によると占領地の様子を内地の子たちに幻灯で伝えようとしている。
<常会で勇さんの家に集まってきた子どもたちのために勇さんのおとうさんがげんとうで「南洋」の写真を次々に写してくれ解説してくれる。>
青い海に、静かにかげをうつしてゐるやしの木に寫真がうつりました。
「南洋の海は、明るくてまっさをですから、着物でもひたしてそめたいと思うほどの美しさです。その海面にかげをうつすのがやしの木で、こんなけしきは、南洋のどこへ行っても見ることができます。」
身近な南洋の個所が墨で真黒に
島の国民学校で本土の四季や草・木・花など、知らないことばかり習ったわたしにも、この教材は豊かにイメージ化できそうな教材だった。けれども残念なことに最も身近に感じられる「南洋」は国家主義的、軍国主義的、海外侵略的教材として昭和20年9月20日の文部省通達によって墨で塗りつぶされていたのだった。
文部省通達は占領軍の指令に先立って措置されたようだ。墨塗りは戦争に関する記述が主であり天皇崇拝、皇国史観の教材は残されたらしい。天皇への忠誠を述べた「田道間守」(たじまもり)はわたしが手にした墨塗り本で読んだ記憶がある。唱歌「田道間守」の一部は今も歌える。
2月下旬か3月上旬ごろ、わたしも二宮先生の指示に従いある教科書のどこかを墨で塗りつぶしたと記憶する。
占領軍の指令により天皇崇拝、皇国史観の教材がこのとき墨で塗られたことを推測する。それがどの部分だったかは皆目分からないのだが・・・。
|

上下2冊ずつ同じ教科書
どこをGHQが否定したかが一目瞭然です |
|
|
南の島に生まれ育った純真無垢な一人の少年は、国民学校における「皇国民の錬成」によって軍国少年にふさわしい刷り込みを存分に受けた。
国定教科書「アサヒ読本」が強く影響した。本土の春を知らずサクラの花を見たことのない、実感のほとんどない文章に混じってヘイタイサンは偉いということ、日本の国がカミの国であることなどの観念が確実に増殖しつつあった。そのことはススペの捕虜収容所の1年半を経ても、いささかも揺らぐことはなかった。
今思うと<国定教科書は怖い>とつくづく思う。「支那の子ども」や「支那の春」は国の品格を問われる文章だ。
4年生の春、大磯国民学校に転校した。国民学校が最後となる年度である。墨塗り教科書はもう使わなくなった。仮綴じ本に変わったのだった。サクラ読本のように多色刷りではなく、文字も小さかった。新聞紙にハサミを入れて適当に綴じた体裁はきわめて粗末なものだった。これが教科書だった。
アンデルセンの「みにくいアヒルの子」をまず読んだ。感動した。わたしは、それまで国定教科書しか読んだことがなく、アンデルセンという童話作家を知らなかった。が、物語の内容がわたしの琴線に触れた。
ほかの教材文もみなすばらしかった。教室の雰囲気がのびのびしていることもうれしかった。
|
|