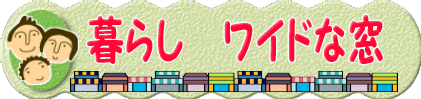遊び場、赤田の田んぼ
横浜市立あざみ野第二小学校が開校した時、私は小学校3年生でした。一学期は20人前後のクラスでスタートしましたが、夏休みが終わると一学年50人弱×3クラス編制となり、その規模で卒業を迎えました。
当時のあざみ野は造成地ばかりで、クラスメイトの大半は団地から通ってきていました。多分殆どの子は横浜市立第一小のほうが近かったのではないでしょうか。
テレビゲームが流行り出す前でしたので、遊びと言えば空き地などの屋外で遊ぶ以外ありませんでした。その遊び場の中でも格別だったのが、「赤田」でした。あざみ野第二小の裏手には道路を挟んで雑木林が広がっていて、そこに付けられた一筋の獣道のような苅分をたどると「赤田」という地区に抜けることができました。
湧水にオタマジャクシ、ドジョウ、ゲンゴロウが泳ぐのを捕まえ、畦道でセリを摘み、帰りにはバケツや虫かごにその日の成果を入れ、薄暗くなった獣道を家路へと急ぎました。それが当時の「日常」でした。
その後30年、わが子と暮らす札幌
あれから約30年が経ち、今は札幌で二子をもうけ、上の子がその頃の私の年齢に近づいてきております。
この子達は、札幌でどのような自然と向き合うのでしょうか。せっかくの機会ですので、札幌の自然について少しご紹介させいただこうと思います。
|
|

日本及びアジア初の冬季五輪開催,
大倉山スキージャンプ場
昭和47年(1972)2月、札幌冬季オリンピックでは宮の森スキージャンプ場(70m級)で1位・笠谷幸生、2位・青地、3位・藤沢と金・銀・銅の表彰台を独占し世界を驚かせ、「日の丸飛行隊」と呼ばれた日がまだ記憶に新しい。
札幌冬季オリンピックで世界的に有名になった、この大倉山スキージャンプ場(90m級)は、札幌駅から6kmという近距離にあります。
|
|