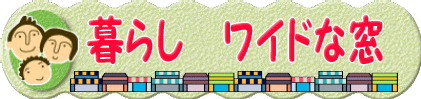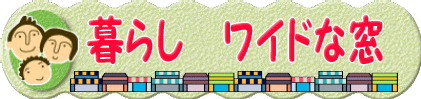1. 現存する巨木…日本一の巨木(鹿児島県蒲生町の大楠)
|
当サイトで「名木古木」の連載を始めたころ、私は日本一の巨木、鹿児島県のこの「蒲生(かもう)大楠」の写真がどうしても手に入れたかったのです。鹿児島には知人友人も一人もいない。一枚の写真のためにわざわざ鹿児島まで行く暇も費用もありません。
「蒲生の大楠」との不思議なご縁
ところが、不思議なことがあるものです。私の写真集「わが町の昔と今」第3巻「神奈川区編」を入院中の父親にふるさと神奈川区の写真をベッドの上で見させたいという人に郵送したことを、ふと思い出しました。さっそく柱 敦史さんという方に「お知り合いの方で蒲生の大楠の写真をお持ちの方がいらっしゃたらお借りしたい」とメールを出しました。
と、15分も経たずに返信が…。なんという有り難いご縁なのでしょうか。
「私はその写真ならたくさん持っています。スキャンして今日中に送ります」とのこと。じつは、この木は彼の自宅から車で15分ほどの隣町、蒲生八幡神社の御神木。毎年の初詣、安産祈願、子どもたちが大楠のようにすくすく成長するようにと七五三、七草など年中行事ごとに家族でお参りする、いわば、柱家の“守護神”だったのです。お参りするたび、この大楠の下で家族の記念写真を撮っていたのでした。

2009年1月撮影・提供:柱 敦史(鹿児島県姶良郡姶良町)
樹齢1500年(推定) 樹高30m、根周り33m、幹の太さ24.2メートルも・・・。根の上には根を傷めないようウッドブリッジが設置されています。
|
|

2009年1月撮影・提供:柱 敦史(鹿児島県姶良郡姶良町)
幹の左下をご覧ください。扉付きでカギがかかっています。扉を開けて中に入ると、八畳間ほどの広さの空洞。見上げると十数メートルの所から外の光がさし込み、トトロの世界を彷彿する神秘な空間だそうです。
蒲生の大楠が日本の全樹種を含め、「日本一の巨木」であることが分かったのは平成元年6月。環境庁が初めて実施した「全国巨樹巨木林調査」の結果によるものです。
|
|
2. 現存する都心の大木…「本郷弓町の大クス」(文京区本郷1丁目)
|
現存する巨木や大木は、ほとんど神社やお寺、公園や植物園内にあり、そこで管理されているものです。この「本郷弓町の大クス」はビルの谷間の民有地、しかも道路端に立っています。それだけに、出合いの喜びは格別なものがあります。
室町時代から世の変遷を見守る自然木
堂々と根を張った根元、まっすぐ伸ばした幹、緑濃く枝葉を広げた姿は威勢がいい。樹齢600年とは、想像できないほど元気です。根元の周りは踏み固めないように竹の柵があり、きれいに掃除され、この木に対する住民の皆さんの優しさが感じられます。
このあたりは江戸時代、旗本・甲斐庄喜衛門の屋敷があった所だそうです。余談ですが、この甲斐氏は南北朝時代の武将、あの楠正成の子孫でした。周囲に与力同心の屋敷があり、御弓町と呼ばれていましたが、明治時代の町名変更で本郷弓町になり、そして今は弓町の名は消え、本郷一丁目になっています。この町内には近代的なビル群の中に明治や大正時代にタイムスリップしたような古い木造の老舗旅館が今もがんばって営業しています。
樹齢600年からからみると、このクスノキは当の甲斐氏の屋敷だったずっと以前、西暦1400年代の室町時代初頭の頃から自生していた“自然木”であったことになります。京都の室町に幕府が置かれ、幕府の財政軍事基盤が弱いため、政変が絶えず戦国時代と呼ばれ、下克上が頻発、さまざまな一揆が各地で起こった悲惨な時代でした。
このクスノキはそんな戦国の室町時代から日本の激動の時代をつぶさに見届けてきたかと思うと、感慨ひとしおです。
|

推定樹齢600年。樹高20m 目通し幹周り8.5m
幹にしめ縄が巻かれ、根の周りを踏み固めないよう竹の柵。民有地なのに、清掃も行き届き、よく管理されています
2010年8月13日撮影:岩田忠利
|
|