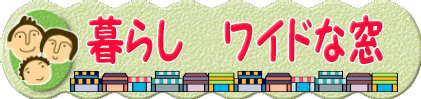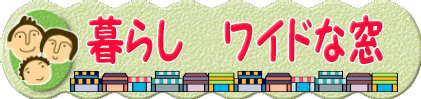
丂丂丂仛夋憸偼僋儕僢僋偟奼戝偟偰偛棗偔偩偝偄丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
|
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俶俷.17丂2014.4.4宖嵹丂 |
|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丗孖尨栁晇乮峘杒嬫崅揷惣 丅挊嶌乽僪僉儏儊儞僩丂彮擭偺愴憟懱尡乿乯 |
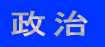 |
丂昐擔憪偺帊乮俀乯
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂寷朄夵惓憪埬戞俋忦傪傔偖偭偰 |
|
|
傒傫側偱峫偊傛偆両丂帺塹戉偺崙杊孯壔亖寷朄夵惓丄惀偐旕偐
|
丂戞俀師垻攞撪妕偑敪懌偟偨偲偒丄恄撧愳怴暦幮偐傜揹榖庢嵽傪庴偗偨丅僒僀僷儞搰偱偺愴憟懱尡傪帺旓弌斉偟偨偽偐傝偩偭偨偐傜偐丄導撪桳尃幰偺堦恖偲偟偰乽崙杊孯乿偵偮偄偰堄尒傪媮傔傜傟偨偺偱偁傞丅婰帠偼師偺傛偆偵揨傔傜傟偨丅
丂塃孹壔傪寽擮偡傞偺偼丄懢暯梞愴憟帪偺僒僀僷儞搰偱晝偲俀恖偺掜傪幐偭偨峘杒嬫偺彫妛峑偺尦嫵桜偺抝惈乮77乯偩丅丂丂
丂晝偼乽崙杊怓乿偺崙柉暈傪拝偰偄偨偨傔丄孯恖偲娫堘偊傜傟暷孯偵廵寕偝傟偨偲偄偆丅乽亀崙杊亁偲偄偆尵梩偱丄崙柉偼崙偵庣傜傟偰偄傞偲巚偆偐傕偟傟側偄偑丄崙傪庣傞偨傔偵崙柉偑媇惖偵側傞偺偑愴憟偺幚懺乿偲巜揈丅抝惈偼乽崱屻偁傜偸曽岦偵岦偐傢偸傛偆丄堊惌幰傪桳尃幰偑娔帇偟偰偄偔昁梫偑偁傞乿偲帺傜偵尵偄暦偐偣偨丅
丂乽婜懸偲寽擮偑岎嶖乿偺尒弌偟偺傕偲丄僶儔儞僗傪偲偭偨偐偨偪偱丄
丂堦曽偱丄帺柉偺奜岎曽恓偵巀摨偺惡傕丅峘撿嬫偺抝惈夛幮堳乮60乯偼乽擔杮偼奜崙偐傜庛偔尒傜傟偰偄傞乿偲晄枮傪曞傜偣偰偄偨丅偦傟偩偗偵丄寷朄夵惓偵傛傞帺塹戉偺乽崙杊孯乿傊偺埵抲晅偗傑偱宖偘偨嫮偄巔惃偵丄婜懸傪婑偣傞丅
丂僞僂儞僯儏乕僗巻乽恖暔晽搚婰乿棑偺宖嵹栚揑偱庒偄彈惈婰幰偺庢嵽傪庴偗偨偺偼嶐擭偺偙偲偩偭偨丅亙庒偄悽戙傊愴憟揱偊傞乿亜偺尒弌偟偱揨傔傜傟偨択榖婰帠偺側偐偱傢偨偟偼師偺傛偆偵弎傋偨丅
丂乽尰嵼丄崙撪偺忬嫷偑曄傢傝條乆側摦偒偑偁傞拞丄庒偄悽戙傪婥偑偐傝偵巚偆丅敾抐偼恖偺帺桼丅偩偑丄敾抐傪壓偣傞偩偗偺楌巎揑側恀幚傪抦傝丄抦幆傪摼偰傎偟偄乿
丂擔暷奐愴偐傜71擭栚偺暯惉24擭12寧俉擔丅恄撧愳怴暦偼丄愘挊乽僪僉儏儊僩丂彮擭偺愴憟懱尡乿偺弌斉傪揱偊傞婰帠傪宖嵹偟偨丅
丂尒弌偟偼亙愴憟偺恀幚傪抦偭偰亜丅寷朄夵惓偵岦偗偨摦偒偵乽恀幚傪抦偭偰乿偺婅偄偼傑偡傑偡嫮偔側傞偽偐傝偱偁傞丅 |

暯惉23擭3寧丄帺塹戉偺搶擔杮戝恔嵭旐嵭抧媬墖

挊幰徯夘婰帠乮恄撧愳怴暦乯 |
|
|
|
崙杊孯偼杮摉偵崙柉傪庣傞偺偐丠
|
丂帺柉搣偺寷朄夵惓憪埬偺戞俋忦偺俀丂嘊偼丂亙崙杊孯偼乧乧崙柉偺惗柦庒偟偔偼帺桼傪庣傞偨傔偺妶摦傪峴偆亜偲側偭偰偄傞偑丄偙偺暥尵傪妟柺捠傝偵庴偗巭傔偰娫堘偄偼側偄偺偩傠偆偐丅
丂徍榓21擭係寧丄悽榖偵側偭偨廸晝偺壠乮暯捤巗乯偐傜戝堥偵揮嫃偡傞偙偲偵側偭偨丅嶳娫偺摴傪峴偔偲丄塃庤偵備傞傗偐側幬柺偺憗弔偺敤偑奼偑偭偰偄偨丅傢偨偟偑婏堎偵巚偭偨偺偼丄偲偙傠偳偙傠偵摼懱偺抦傟偸寠偑偄偔偮傕孈傜傟偰偄傞偙偲偩偭偨丅
丂屻擔丄峩嶌拞偺擾晇偺曽偐傜乽寠乿偺惓懱傪暦偔偙偲偑偱偒偨丅杮搚寛愴偲側偭偨偲偒丄忋棨偟偰偔傞揋偺愴幵偵懳峈偡傞偨傔乽棊偲偟寠乿偲偟偰媽擔杮孯偑岺嶌偟偨傕偺偩偲偄偆偙偲偩偭偨丅
|
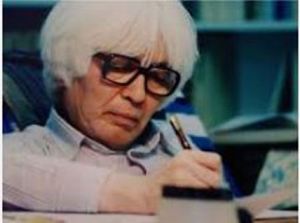
巌攏椛懢榊乮彫愢壠丒僲儞僸僋僔儑儞嶌壠乯丅1923乣1996丂乽棾攏偑備偔乿丄乽嶁偺忋偺塤乿側偳偺挊彂偱偍側偠傒 |
|
丂崙杊孯偵偮偄偰峫偊傞偲偒師偺僄僺僜乕僪偼惤偵帵嵈偵晉傓撪梕偱偼側偐傠偆偐丅
仴巌攏椛懢榊偝傫乮幨恀嵍乯偼摉帪丄愴幵楢戉偺彮堁偱丄杮搚寛愴偵旛偊撊栘導嵅栰偵挀撛偟偰偄偨丅朸擔丄戝杮塩嶲杁偵巌攏彮堁偑幙栤偟偨丅揋偑憡柾榩偵忋棨偡傟偽丄旔擄柉偼娭搶暯栰傪杒忋偡傞丅撿壓偟偰寎寕偡傞晹戉偲崿棎偑婲偒側偄偐丅嶲杁偼懄嵗偵摎偊偨丅乽傂偒嶦偟偰峴偗両乿
仴僒僀僷儞偑愴壭偵尒晳傢傟孖尨堦壠偑嬤偔偺摯孉偵旔擄偟偨偲偒偺偙偲偱偁傞丅
丂嬤椬偺懡偔偺柉娫恖偵崿偠偭偰壗恖偐偺晧彎暫偑墶偨傢偭偰偄偨丅偦偺偆偪堦恖偺暫偑撍慠搟惡傪敪偟偨丅
乽揋偺栚昗偵側傞丅愒傫朧傪媰偐偡側両両乿
乮乽僪僉儏儊儞僩丂彮擭偺愴憟懱尡乿傛傝乯013丄俉丄11丂恄撧愳怴暦丂乽徠柧摂乿
仴俀嵨偺媊梇偪傖傫偼乽僆僽乕丄僆僽乕乿偲媰偒嫨傃傑偡丅偡傞偲暫戉偨偪偑丄乽偦傫側偵媰偐傟偨傜暷暫偵傒偮偐傞偠傖側偄偐僢両丂嶦偣丄嶦偣両乿偲岥乆偵搟柭傝傑偡丅
丂巓偼暫戉偨偪偵愑傔傜傟傞偺偵懴偊偒傟偢丄媰偒側偑傜乽扤偐嶦偟偰偔偩偝偄両乿偲棅傒傑偟偨丅暫戉偺堦恖偑棫偪忋偑傝傑偟偨丅媊梇偪傖傫偺惡偼堦弖偵偟偰巭傑偭偰偟傑偄傑偟偨丅
丂丂丂丂丂乮乽彮擭偺愴憟懱尡乿強廂偺乽撿梞偺堏柉偲愴憟乿偐傜乯丂 |
|
懢暯梞愴憟偺巰幰偼擔杮恖偩偗偱幚偵310枩恖丅僒僀僷儞搰偵尷偭偰尵偊偽丄孯恖丒孯懏栺41丆000恖丄嵼棷朚恖栺10丆000恖偺懜偄柦偑幐傢傟偨偲偄偆丅偦偺拞偵偼崙杊怓偺暈憰備偊偵廵寕偝傟偨晝丄婹偊偲妷偒偵嬯偟傫偩枛偵夓巰偟偨俀恖偺掜丄孯戉偺榑棟偑桪愭偝傟傞廋梾応偺側偐偱梒偄柦傪枙嶦偝傟偨俀嵨偺媊梇偪傖傫偑偄偨偙偲偼偟偐偲柫婰偟偰偍偒偨偄偙偲偱偁傞丅
|
崱忋揤峜偲埨攞庱憡偺恀堄偺堘偄偼丠
|
丂懢暯梞愴憟偑廔傢偭偰60擭栚偺暯惉17擭偺壞丅堅楈偺偨傔偵僒僀僷儞傪朘傟偨揤峜峜岪椉暶壓乮幨恀嵍乯偵傛偭偰丄嵟杒抂僶儞僓僀僋儕僼偵寶棫偝傟偨拞晹懢暯梞偺旇偵栙摌偑曺偘傜傟偨偺偩偭偨丅
丂摨擭12寧偺婰幰夛尒偱暶壓偼丄壞偺乽怱偺廳偄椃乿傪憐婲偝傟丆師偺傛偆偵弎傋傜傟偨丅
丂乽搰偵嵼廧偝傟偰偄偨恖乆偺斶偟傒偼偄偐偽偐傝偱偁偭偨偐寁傝抦傟側偄傕偺偑偁傝傑偡乿
丂乽夁嫀偺楌巎傪偦偺帪戙偲偲傕偵惓偟偔棟夝偟傛偆偲搘傔傞偙偲偼擔杮恖偵偲偭偰丄傑偨擔杮恖偑悽奅偺恖乆偲岎傢偭偰偄偔偆偊偵傕偒傢傔偰戝愗側偙偲偱偡乿 |

丂僶儞僓僀僋儕僼偱栙摌偝傟傞揤峜丒峜岪椉暶壓 |
|
|
丂嬍嵱偺搰僒僀僷儞偺愴嫷偑偄傛偄傛愗敆偟偨俈寧俈擔偺嵟屻偺憤峌寕偵偁偨偭偰撿塤拤堦挿姱偼彨暫偵岦偐偭偰嵟屻偺孭帵傪悅傟偨丅乽惞庻偺柍媷丄峜崙偺栱塰乮偄傗偝偐乯傪婩擮偡傋偔乧乧乿偲偁偭偨偑丄柉娫恖偵偮偄偰偼慡偔怗傟傞偙偲偼側偐偭偨丅
丂桋崙恄幮傪嶲攓偟偨埨攞庱憡偑乽巰幰傪捛搲偡傞偺偼摉偨傝慜偺偙偲乿偲偄傢傟偨偺傕丄偍偦傜偔崙偵柦傪曺偘偨塸楈傪尠彶偡傞堄恾偐傜偱偁偭偰丄柉娫偺媇惖幰偵巚偄傪偼偣傞偙偲偼側偐偭偨偺偩傠偆丅
丂崙柉偺惗柦庒偟偔偼帺桼傪庣傞崙杊孯乧乧偲偺暥尵偩偑丄憪埬戞俋忦偺俀丂嘊偼崱屻怲廳偵嬦枴偝傟傞傋偒帠崁偲巚偆丅
|
 |
乽偲偆傛偙増慄乿俿俷俹偵栠傞 |
 |
師儁乕僕傊 |
 |
乽栚師乿偵栠傞 |
 |
昐擔憪偺帊乮3乯傊 |
|