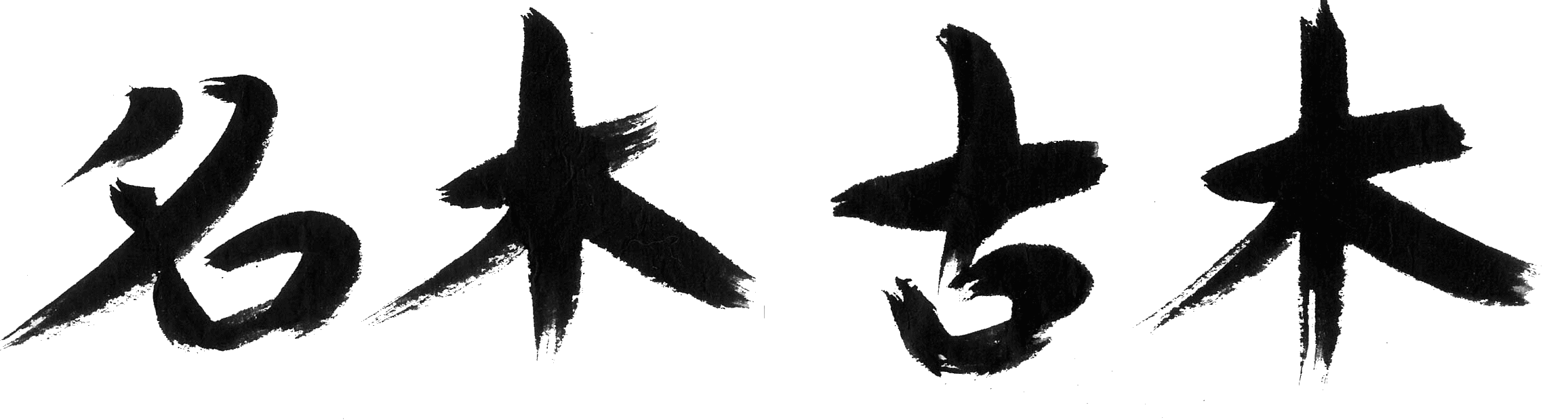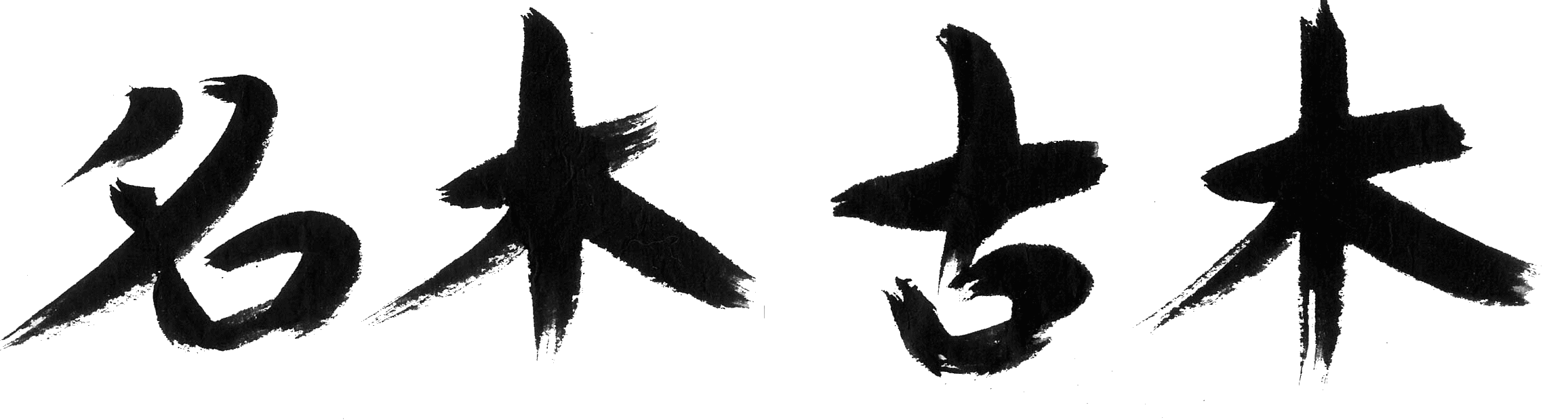|
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂憗弔偺梲偩傑傝偵嶇偔僔僟儗僂儊 丂丂丂憗弔偺梲偩傑傝偵嶇偔僔僟儗僂儊
|
|
|
|
惗偄棫偪&
尒偳偙傠 |
丂搶媫搶墶慄擔媑墂偺惣曽栺1.5僉儘偺廧戭抧偵埻傑傟偰偄傞恀暉帥偼廆攈偼憘摯廆丅奐婎偼宑挿擭娫丄栺係侽侽擭偺楌巎偁傞帥堾偲暦偄偰偄傑偡丅杮懜偼巕堢墑柦抧憼曥嶧偱丄愄偼墢擔偵偼奺抧偐傜傕怣幰偑嶲寃偟丄嶲摴偵偼娺嬶壆丄閈摢壆丄懯壻巕壆側偳偑暲傃丄擌傢偄傪傒偣偰偄偨傛偆偱偡偑丄崱偼偦偺柺塭偼偁傝傑偣傫丅
丂嫬撪偼嫹偄側偑傜丄墶昹巗偺柤栘屆栘偵巜掕偝傟偨庽楊俀侽侽擭傪挻偊偨僋僗僲僉丄傾僇僈僔丄僀僠儑僂側偳俈杮傕偁傝丄惷偐側樔傑偄傪忴偟偩偟偰偄傑偡丅
丂嬤偔偵廧傓巹傕帪愜朘傟偰偄傑偡偑丄巜掕偝傟偰偄傞柤栘丒屆栘偺拞偱傕嵟傕庒偄偙偺幨恀偺乽僔僟儗僂儊乿偑枮奐偺憗弔偵偼枅擭寚偐偝偢峴偔傛偆偵偟偰偄傑偡丅偤傂堦搙偍弌偐偗偔偩偝偄丅攡尒偱偟偨傜俀寧壓弡乣俁寧忋弡偑嵟揔偱偡丅
仸墶昹巗巜掕偺乽柤栘屆栘乿搊榐婎弨偼丄侾.姴廃傝1.5倣埲忋丂2.庽崅15倣埲忋丂3.庽楊100擭埲忋偱偡丅偙偺巬悅傟攡偼偳偺忦審傕枮偨偟偰偄傑偣傫丅偟偐偟巹偑尰暔傪尒偵峴偒傑偟偨傜丄偡偖嬤偔偵乽僔僟儗僂儊乿偲彂偐傟偨屆偄昞帵斅偱崻尦偺晠偭偨傕偺偑柍憿嶌偵抲偐傟偰偄傑偟偨丅
丂偦偙偱丄杮棃側傜柤栘屆栘偵奩摉偟側偄庒偄巬悅傟攡側偑傜愭戙偺柤栘屆栘傪堷偒宲偒丄俀戙栚偲偟偰懡偔偺嬤椬廧柉偵曠傢傟偰偄傞乬柤栘乭偲傒傑偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮拲庍丂娾揷拤棙乯 |