|
大正12年、上記表紙絵の場所
|

大正12年(1923年)6月撮影。中央の道は手前左に直角に曲がり、さらに50mほど先で右に直角に曲がる。後方の田圃の先が現在の武蔵小杉駅だが、当時は何も無く、田畑のみ |
|
|
神奈川テレビの連続番組のDVD
|
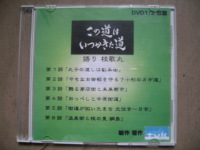
「中原街道編」には第2話「今もなお御殿を守る小杉のカギ道」のほか新丸子、武蔵小杉など6話掲載。
|
|
|
|
一枚の絵に今と昔を描く“異時同時図法”
この表紙絵は、第22号の「武蔵小杉特集」に漫画家・井崎一夫先生が描いた作品である。通巻74号の中で私が最も気に入っている絵だ。
描写の繊細さ、人の動き、ユーモア、それらが「旧小杉御殿跡前」という一幅の絵の中に昔と今の絵を描く手法を“異時同時図法”で物語風にしっかり収められているのは、井崎先生ならではのお見事な作品だと思う。
ユーモア、人の動き、今昔の対比の妙
手前の道には左下の親子が田植えや代かき中の田圃の向こうの西明寺へお墓参りに行くところのようだ。そこに馬上の旅人や徒歩の旅人、飛脚も。茅葺きの茶屋に“めし”と“ラーメン”の暖簾が・・・。小杉御殿入り口前の道にバイクを追跡するパトカー、篭をかつぐ二人が走る。江戸時代にはあり得ないラーメン、バイク、パトカーが登場するあたりが井崎流ユーモアで楽しい。人間も、犬も、大根を食べる馬も、空を飛ぶ雁も、すべて動きがある。茶屋の縁台にお盆に乗せた茶碗、田圃のあぜ道に肥桶、西明寺の参道にお参りに向かう人影・・・じつに芸が細かい。
東海道のバイパス、中原往還(現中原街道)
中原街道は、徳川家康が慶長9年(1604年)相模の国の中原(現・平塚市中原)に別荘を建て、鷹狩りと休養と地方視察の基地としたといわれる。江戸城〜虎ノ門〜三田〜高輪〜荏原〜旗の台〜雪谷〜沼部・桜坂〜丸子の渡し〜小杉御殿〜千年〜勝田〜佐江戸〜中山〜瀬谷〜藤沢用田の村々を通って平塚中原の別荘につながり、東海道に出るのだ。 中原街道は東海道の近道、いわゆるバイパスで荷物の運搬や往来に利用され「中原往還”」と呼ばれ、非常に重要な幹線道路だった。
表紙絵の場所は2代将軍秀忠が防御に造った直角の道
この長く続く中原街道で、たった1ヵ所だけ、50メートルほどの間で直角に曲がる場所がある。そこは、表紙絵に描かれている“小杉御殿跡前”である。それは、2代将軍秀忠が1万2000坪余の小杉御殿を造ったとき、敵陣が攻めにくくした防御策として道路を直角に造ったのだ。
むかし、長い丸太の材木を積んだ荷馬車などは、この角を曲がりきれず四苦八苦する馬引きが何人もいたという話は、御殿跡地に住む原平八さん(屋号・大陣京)から聞いた。
私は「神奈川テレビ」との共催で同テレビ連続番組『この道はいつかきた道』(13回放映)をつくった。中原街道と綱島街道を取り上げ、昔の写真と現在の情景とを対比させ紹介するもの。この「中原街道編」でも道が直角に曲がる小杉御殿跡前を取り上げた。私の手元にそのDVDがある。番組を見逃した方、興味のある方は当編集室までお越しくださればご覧にいれよう。
中原街道と綱島街道を混同する人へ
今でも綱島街道と中原街道とを混同している人がいて、綱島街道のことを中原街道と呼ぶ人がいるが、これは間違いだ。
綱島街道は東京から来て丸子橋を渡り切った所の信号をそのまま直進する道が中原街道、左折する広い道路が綱島街道の基点で、ここから綱島街道は始まる。綱島街道は、日吉に慶應大学の校舎が三田から移転してから新設された昭和10年代の新しい道路である。
|

