|

伊藤三郎川崎市長(右)は市長室で本誌を見ながら私に有料化を親身になって勧めてくれた |
|
|
|
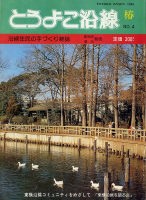
写真は碑文谷公園。撮影:八木欣也(上野毛) |
|
|
|
無料配布は1人100冊。編集室前に列をなす車
9ページに無料配布時代のことを書いたが、無料配布はこちらが配本に飛び回らなくても済むので至って楽だ。内部の会員は欲しい方には一人最高300冊の進呈。外部の欲しい方々には「一人100冊(1束500冊入りを2束)進呈」と誌面で予告した。欲しい方々は朝、私が編集室のシャッターを開ける前から綱島街道に車が列を作って待っていた。ガソリンスタンドやレストラン、企業関係者などが多く、皆さんが『とうよこ沿線』をお客サービス用のギフトとして使っていたのである。こちらは2束を次々渡せばいいだけで配本の手間が省け、私たちは編集と経費充当分の広告募集にだけ集中すればよかった。
伊藤川崎市長が本誌有料化をアドバイス
第3号まで発行したとき、長洲一二神奈川県知事の紹介で伊藤三郎川崎市長を川崎市役所に訪ねお会いした。話すうちに市長は本誌有料化についてこう提言した。
「『とうよこ沿線』のような立派な雑誌は、本当に読みたい人がお金を出して読む本にしたほうがいい。有料にすべきです。タダ(無料)だからもらうという人たちを相手にしていてはダメです」。
自ら体験した多摩区にある川崎市営の川崎市日本民家園を例にあげた。無料で開放していた当時は、昼間は子供のキャッチボールやかくれんぼなどの遊び場に、夜間は若い男女のデートの場や浮浪者の寝床に使用され、荒れ放題だった。多額の公費をつぎ込んだ施設の利用方法を再検討し、入場料を有料にした。すると、見学したい人が落ち着いてゆっくり鑑賞でき、いつも清潔な綺麗な施設に変わっていったという。伊藤市長は私に有料化を強く勧めたのだった。
毎晩、商店街のシャッターが下りるまで
その忠告どおり、第4号から1冊200円で販売することにした。
まず最初が「駅売店。。私は東急の子会社で駅売店を運営管理する“東弘商事”と交渉し東横線の渋谷〜横浜の各駅売店で扱ってもうようにした。
続いて「書店」。大手書店の有隣堂と文教堂の各支店と各駅周辺の書店を一軒一軒訪ね歩き販売してもらうようにした。
また、『とうよこ沿線』を販売することはお客様とのコミュニケーションの糸口になることを訴え、喫茶店・レストラン・クリーニング店・和菓子店・ケーキ店・茶舗など業種を問わず委託販売していただけるようになった。
昼間は取材や広告取り、編集や会議などをやり、夕方から沿線各地の駅前へ出かけた。義母を車の助手席に乗せ、以下の街の店を次々、飛び込みで回った。それも駅前商店街のシャッターが下り、人通りが三々五々になるまで開いている店を探しては飛び込んで、委託販売の交渉をしたのだった。
55駅の街で、販売協力先は計約400ヵ所に
渋谷〜代官山〜中目黒〜祐天寺〜都立大学〜自由が丘〜田園調布〜多摩川園(現・多摩川)〜新丸子〜武蔵小杉〜元住吉〜日吉〜綱島〜大倉山〜菊名〜妙蓮寺〜白楽〜東白楽〜反町〜横浜の東横沿線、
さらに支線の伊勢佐木町〜関内〜石川町。横浜線の大口〜新横浜〜小机〜鴨居〜中山。
南武線の溝口〜武蔵新城〜武蔵中原〜向河原〜平間〜鹿島田。
大井町線は二子玉川〜上野毛〜等々力〜尾山台〜九品仏〜緑が丘〜北千束。
目蒲線(現・多摩川線)では目黒〜不動前〜武蔵小山〜西小山〜洗足〜奥沢〜沼部〜鵜の木〜下丸子まで。
池上線では東横沿線に近い千鳥町〜久が原〜御嶽山〜雪谷〜石川台まで。
以上55駅周辺に一駅最低2〜3カ所の“販売協力店”、後背地が広い日吉・綱島・大倉山・武蔵小杉には約20店舗の協力店を開拓し、東横線の駅売店を含め計約400カ所の『とうよこ沿線』販売ネットワークを確立することができた。
|
