わが家のたった1枚の写真
大切にしている1枚の写真がある。親戚の家で無事だったものを複製させていただいたものだ。セピア色に変色し、かつての鮮明さは失われてしまっているが、紛れもなく家族の写真なのである。撮影年月日は不明。右下隅に「サイパン写真館」と記されているので、島で最も繁華な町ガラパンで撮影されたものにまちがいない。おそらくこの日一家は精一杯のおめかしをして、思い思いに弾んだ気分でカレータに乗り込んだことだろう。
3男輝夫を膝の上に、母・都が中央で椅子に腰掛けている。その左手に長男のわたし、右手が次男の利夫。そのすぐ後ろで父・修蔵が、家長らしく頼もしげに直立している。わたしたちはみな白い色調に写っているが、父は背広姿でネクタイも着用している。だた、ゲートルをしているのがいかにも戦時下を思わせる。
この写真で最も着目したいのは、わたしのピカピカに光った学帽である。よく見ると、徽章がまだない。入学前のことだったのだろう。
わたしが南洋サイパン島アスリート小学校に入学したのは昭和17年(1942年)4月だから、記念撮影は同年の正月を前後する時期ではなかっただろうか。
昭和18年7月生まれの末弟・勝の姿がないのは、そのためだ。
「2年経ったら利夫の入学だ。そのときはまた、ガラパンを訪れよう!」。父と母はそんなことを語り合ったのかもしれない。
「家族みんなで・・・」「一家そろって・・・」。誰もが口にする月並みな言葉だ。が、それは、なんと温かく幸せ感の溢れた言葉だろうか。セピア色の写真の家族は、ガラパンの、とある写真館のスタジオ内に勢揃いして、文字通り幸福一家であった。
が、一家6人が勢揃いしたもう一枚の記念写真、利夫の学帽姿、そして勝がこの世に生を受けた証・・・を得ることはなかった。撮影の機会を永久に奪われてしまったのだった。
時は昭和19年に
昭和19年を迎えた。
10歳になった。4月から国民学校3年生である。
子どもの散髪は父の役目だった。バリカンのバネのたてる音が耳に快く、父の床屋さんは大好きだった。
ある日のこと、散髪でいい気分になっていた時の会話である。
「父ちゃん、学校の近くに兵隊さんが増えたね。陸軍も海軍も・・・。」
兵の増強が子どもながらに実感でき、父に報告できることが誇らしかった。兵隊さんの存在は頼もしくまた心強かったのだった。しかし戦争はどこか遠くの出来事だった。
「米軍の進攻は島伝いに来るだろうから、サイパンに来るのはまだ当分先のことだ。あるいは敵はサイパンを素通りするかもしれない」これが軍の判断であり、軍民ともまだのんびりムードにつつまれていた。
初の空襲
2月23日早朝、サイパンは初めて空襲を受けた。学校の近くのアスリート飛行場に小型爆弾が落ちた。ソウシジュ林の向こうで数日間黒い煙が上がり続けた。ちょっとビックリしながら眺めていた。第43師団が到着する前のことだった。
落下傘で米兵がジャングルに降り立ったという噂があり、事実、将校1名・兵卒1名が毎日サトウキビ畑を通ってジャングルの中に入って行った。捜索は難航しているらしく幾日も続いた。
ジャングル学校
学校にはもう通えなくなっていた。飛行場にあまりにも近接していたためだが、軍が使用しているとの噂も耳にした。
ジャングルの中で学習することになった。そのための建物はないので机も椅子もなかった。集合する場所だけは決まっていたが、それはジャングルの樹木群と軽便鉄道の線路に跨るエリアだった。
わたしたちは画板にひもを付けて首から掛けた。机の代用として・・・。近くの生徒が十数人集まってきた。年少者と年長者の区別もなく、男女の区別もなかった。男の先生が一人派遣されてきたが、授業をするわけではなく、生徒の自習するのを監督するだけだった。
いま復刻本で3年用の読本を開いてみても馴染みの教材文に出合うことはない。担任の先生がいなくて時間割表もないなかで、わたしたちに自学を望むのは土台無理なのだった。高学年の生徒でさえ先生に質問をしたり学習の相談をする者はいなかった。先生は出欠だけをチェックしているのだった。先生の名前も記憶に残らなかった。
学校とはいえ、ジャングルまでランドセルを背負って来る子はなく、みんな風呂敷に教科書を包んで通った。アスリートの校舎で学んだときの改まった服装でもなかった。ジャングル学校で雨に降られた記憶はない。乾季だったからだと思う。
いまでも気の毒に思うのは2歳年下の利夫である。ジャングル学校で新入生となり、ついにアスリート小学校の門をくぐることはなかったのだ。学帽もなかった。ジャングルの中では学帽は似合わないのだった。
1・2年生の時のような緊張した毎日ではなかったけれども、戦時下の小国民といった別の意味の緊迫感みたいなものがないわけではなかった。
父は畑の様子を気にしながらも、毎日飛行場に通った。先の空襲で破壊された滑走路を補修するために軍属として徴用されていたのだった。
ある日の午後、ジャングル学校から帰り、縁側に風呂敷包みを投げ出すや、いつものようにホウオウボクにのぼった。上気したほほに風が心地よかった。
そのとき軍刀を下げた将校がサンスベリアの径を近づいてきた。
第25対空砲連隊が周辺の民家に分宿することになり、将校の訪問を受けたのだった。翌日、我が家にも橋本兵曹長以下12名の兵隊さんたちがやってきた。高射砲陣地は我が家から200メートルのあたりに構築された。
空襲警報発令、防空壕へ
昭和19年(1944年)6月11日。
この日は日曜日だった。ジャングル学校は休みだった。家族6人と12名の兵隊たちはいつもと変わらず気持ちの良い朝を迎えた。綿をちぎったような白い雲が島の最高峰タッポ-チョの山頂のあたりをゆっくり流れていた。
「♪霞ヶ浦にゃ でかい希望の夢が湧くぅ〜」
橋本兵曹長の十八番『荒鷲の歌』だ。いい喉だ。
そうめんチャンブルーの調理で、 のんびり休日を楽しんでいた。近くには人家がない。遊び友達も来ない。わたしは自然と彼のそばにいることが多かった。
「うち の兵隊さんのなかで僕は橋本兵曹長がいちばん好きだ」。「僕も いまにあんな兵隊さんになるんだ」
予科練の話は興味深かった 。
「内地には霞ヶ浦といって、この島くらいの広さの湖があるんだよ」
わたしには雲をつかむような話だった。それだけに想像の翼がますます広がるのだった。 |
|
|
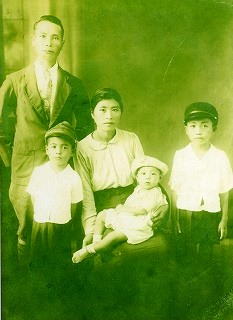 |
|
昭和17年(1942)1月ころ撮影。わが家の唯一の写真。著者栗原茂夫さんは右端 |
|
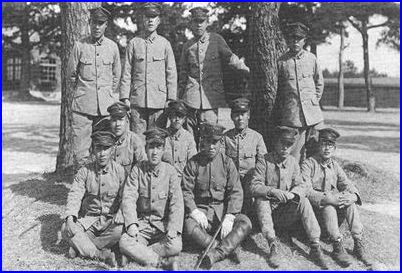 |
|
上官と一緒に記念写真を撮ったりして、どことなくのんびりムード漂う陸軍の将兵たち |
|
 |
|
突如、サイバン島上空に現れ、銃撃を開始し軍民を震撼させたグラマン戦闘機 |
|

