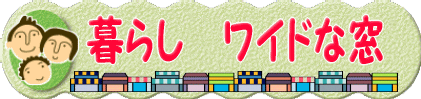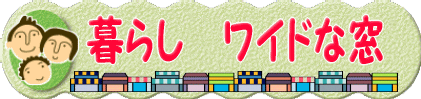再び「サイパンのやしの木は……今は一本もありまでせん」という中島敦の判断を吟味してみたい。
中島敦は仕事目的でサイパンに滞在した経歴をもつ。ただし行動半径はガラパン・チャランカノア・アスリートに限られていた。椰子をはじめ熱帯林を耕作地や住宅地に……と開拓者たちが流したエリア、島の中部から南部にかけた平地ばかりなのである。
仮に敦が、山地の多い中部以北のジャングル地帯まで足を延ばしていたら彼は豊かな椰子林を目にし椰子の実ジュースでのどを潤す体験も可能だったろうと思う。
敦が石川達三の「航海日誌」を読んだ可能性も否定できない。
敦は妻たかに宛てて次のように書いた。
<南貿(南洋貿易株式会社)という小さな百貨店へ行って文芸春秋(12月号)を買い、それから、そのほかの中央公論や改造や、色んな雑誌をガツガツ立ち読みしてきた。サイパンはさすがに雑誌が早く読めていいな。>
|
|
石川達三の「航海日誌」が中央公論に掲載されたのは10月号である。
南洋で仕事をする身の敦が中央公論に手をのばし「航海日誌」をガツガツ立ち読みしたことは容易に想像することができる。とすれば、<この島には椰子がないです。」と彼は言った。そう言われてみれば椰子は一本もなかった。>の箇所で敦の判断は一層強化されたはずだ。パラオ島のコロール町から「町の椰子の並木だけはみごとだよ。」と妻に書き送っているだけになおさら……。
サイパンに椰子の木はないという内容の長男桓宛ての絵葉書の日付は11月18日である。
「航海日誌」は10月号の雑誌に掲載されているのだから、時間的な矛盾も生じないのである。
|