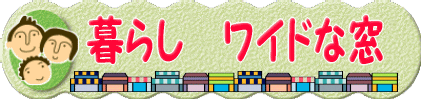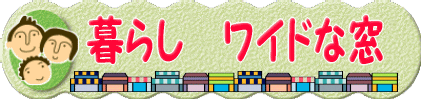高田保公園から地福寺に向かった。大磯駅前を過ぎ、サザンカ通りを海の方へ坂を下りきったところが地福寺である。
寂びた感じの境内に藤村の墓はあった。雪で洗われた墓石はすべて白い御影石だ。敷きつめられた白い玉砂利にも薄く雪が積もっていた。冬の柔らかい木漏れ日を受けたあたりは、いっそう白の輝きが鮮やかだった。

地福寺
|
|

藤村の墓 |
|
境内いっぱいに張った梅の枝々は、水晶のような雫に光を宿してみずみずしかった。梅の開花にはまだ早すぎたが、よく見ると花芽がすでに用意されているのだった。藤村の墓に接してやや小ぶりの墓が並んでいた。「島崎静子の墓」と知りちょっとびっくりした。以前にはなかったと記憶していたので……。
「非当世風」のエピソードを思い出した。
大磯町東小磯に住んでいたさる未亡人(寡婦のことを当時はこう称した)が、埼玉の実家の方に引っ込むことになり、そのあとに高田保が引っ越してくる。氏が、さて荷物を納めようと押入れを開けると、何やら紙包みが置いてある。
|
|
「未亡人の方で忘れていったものとばかりおもって、わきへ片づけようとすると私の家内あての名刺がはってあるのに気がついた。家内にあけさせてみると、上等な障子紙が一本と、それに未亡人手作りの雑巾が何枚か入っていた。本来ならば障子の破れもつくろい、きれいに掃除した上でお引渡しするのですが、こちらも引っ越しのごたごたゆえに、という行き届いたあいさつが聞こえるようだ。ああと家内も深い息をして、りっぱなことを教えられましたといった。」(「非当世風」の一部)
「藤村忌」が書かれたのは、高田保が藤村の旧宅に住むようになった秋のことである。さる未亡人というのは、実は藤村夫人だったのである。
年譜等によって、藤村が昭和16年2月25日東京から大磯町東小磯88に転居、「東方の門」を続稿中脳出血が再発して昭和18年8月22日逝去したことを確認することができる。静子夫人によると「涼しい風だね」と二度繰り返したのが最後の言葉だったそうである。
高田保は昭和18年2月から旧島崎藤村邸に転居、昭和27年2月20日胸部疾患のため死去。わずか8年と3か月に過ぎない大磯町民だった。が、その間地元の多くの人々と濃密な交わりを重ねた。
多くの町民の故人に寄せる想いは「高田保公園」として後世に残されたのだった。
|