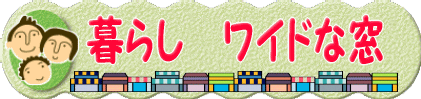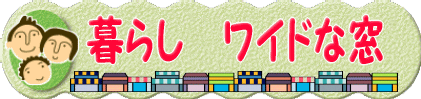春 山間の道から見た斜面の低木群は?
|
母子3人が身を寄せた旭村(現平塚市)の伯父の家から大磯のお屋敷に移り住んだのは昭和21年4月の半ばだった。
春の訪れの遅い大磯丘陵の北側から相模湾に臨んだ代官山の麓のお屋敷までリヤカーを引いた。一家の全財産は軽かった。
山間の細い道の両側には草や木が萌えていた。往くほどに盛んに萌えていた。常夏の島から引き揚げてきた兄弟が初めて迎えた内地の春だった。
|
|
やがて右手に田や畑が見えてきた。斜面は規則的に植えられた3〜4メートルの低木の群だった。青葉若葉が陽にきらめいていた。
|
斜面の低木群はミカン畑 |
後にウサギを飼い始めたわたしは、あのなつかしい山間の道や田畑の向こうの斜面のあたりで餌を求めるようになった。ノゲシやタンポポを好んだ。オオバコもよく食べた。
|
|
再び寒い季節が巡ってきた。低木の果実は濃橙色に色づいた。それで分かった。斜面の低木群はミカン畑だったのである。「ミカン正月」の温州ミカンに間違いなかった。驚いた。
|
代官山の斜面もミカン畑
|
遊び友だちと白岩神社の脇道から代官山の頂上をめざしたことがあった。途中から頂上まで相模湾を見下ろす南の斜面は一面のミカン畑だった。また驚いた。
社会科の教科書で大磯丘陵がミカン栽培の北限であるという記述に出合った。北限とは初耳だったが栽培されている事実は既に知っていた。新制中学校1年生の時だ。
|
|
|

相模湾を見下ろす斜面 |
|
|
ミカン畑に立ち入ることは我慢
|
代官山に登ればミカンなど食べ放題だったにちがいなかった。が、空腹を抱えた戦後の子どもたちでも、一人でミカン畑に立ち入ることは我慢した。
|
|
当時の子どもたちは集団遊びが多く、リーダーは最年長者の役目だった。リーダーは集団のモラルと秩序について責任を感じ、メンバーのなかから悪事をなす子を出さないように目配りしていた。戦後盛んになった野球に興じたり、路上で相撲をとったりして遊んだ。
|
ミカンに手を伸ばしたわたしは…?
|
ミカンが色づく季節を迎えたある日、わたしはウサギの餌を求めて例の山間の道を行き、斜面のミカン畑に近づいた。小一時間もすると竹籠はウサギの餌でいっぱいになった。帰りかけたら、のどがひどく乾いていることに気づいた。ミカンが欲しくなった。
近くのミカンの木の下に半ば地に埋もれて錆びたドラムカンがあることに気づいた。足場にすればうまそうなミカンまで楽に手が届くと思った。天井のしっかりしたドラムカンに見えたので片足を乗せ体重を預けた。意外や、わたしの体はあっという間に沈んでしまった。満杯の液体は“肥溜め”だったのだ。
当時の肥料といえば多くが人糞だったのである。耕地の至るところにコンクリート製の肥溜めが点在していた。トタン板などで覆われて……。
|
|

自然豊かな大磯の山間 |
|
わたしは道の向うの山に沿って流れる川の流れで、何度も衣服をゆすぎ、からだを洗った。何度も何度も洗った。洗いながら母にこの事態をどう説明すべきか苦慮した。
|
天罰か
|
「善いことも悪いことも天の神様がちゃんと見ている。」「悪いことをすれば天罰が下る」
|
|
サイパン島が戦禍に遭うまでの2年間、国民学校で聞いた神様の話など肥溜めの中の人糞みたいなものだと今は思うのだが、その時は、ミカンに手を伸ばそうとした瞬間を神様が見ていて即座に天罰を下したのだと思った。
|
牛乳を受け取りに
|
国民学校から小学校となり民主教育がスタートした。
そのころわたしは早起きをして、東海道線の踏切を渡り国道の向こうの小規模な酪農家まで通った。表札には「柳田」とあった。
|
|
こゆるぎ海岸から松林を越えて波の音が聞こえてくるようなところだった。乳牛が数頭飼われていた。お屋敷の奥様の牛乳を受け取るのがわたしの役目だった。
|
恵比寿神からのご褒美(?)
|
柳田のおばさんはいつもやさしい言葉をかけてくれた。
新しい年を迎え。寒さが一層厳しさを増し吐く息が白かった。そんなある朝とびきりうれしいことがあった。
「毎朝ご苦労様だね。今日は恵比寿講(えびすこう)だから特別よ…」
紙袋のなかは輝くばかりのミカンだった。5〜6個もあったろうか…。
恵比寿講だからいただけたミカンだった。が、そのとき恵比寿講とはなにかを知らなかった。後年書物で調べたところ次のように解説されていた。
|
|
|
<商売繁盛の神様である恵比寿神を祭る民間行事>で<農村ではかまどや田の神として><漁村では豊漁をもたらす神として>古くから篤く信仰の対象とされてきた。
|
|
わたしが柳田のおばさんからミカンを頂戴したのは1月10日の早朝だったようだ。この日は恵比寿講の日なのである。
|