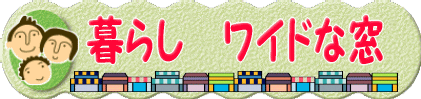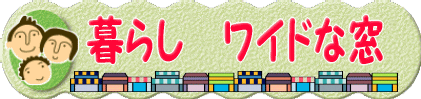|
椰子の実ジュースを飲んだ幸せ体験の記憶とともにわたしが目にした椰子林はサイパン島の原風景として80歳のいまでも忘れえずにいる。
再び中島敦にもどる。息子の桓に届いた椰子の実の絵葉書はサイパンからだった。
11月28日 (一部を省略)サイパンのやしの木は2・3年前に虫がついてすっかり枯れてしまったので今は一本もありません。やしのみずがのめなくてこまります。
初めて椰子の実ジュースを味わったわたしの体験とほぼ同時期に書かれた通信である。
|
|
どうして「サイパンのやしの木は…今は一本もありません。やしの水がのめなくてこまります」となるのだろう???
|
|

椰子の実ココナッツ
緑色の外皮をむいて、包丁でパカッと割るとジュースとコプラの両方が楽しめます |
|
|
|
敦の思い違いだろうか。それならば誤解が生じた根拠を知りたいと思った。
石川達三は、昭和16年5月から7月にかけてサイパン、テニアン、ヤップ、パラオ等の南洋の島々を旅している。動機は未開の土地に対する単純な好奇心かららしいが、昭和18年に見聞や体験をまとめた「赤虫島日誌」を出版している。
敦と石川達三はほぼ同時期にサイパンの土を踏んでいるので、敦の誤解を解く鍵が得られないだろうか…。
|
|
「赤虫島日誌」を入手したいと思った。インターネットでアマゾンに注文したところ練馬区の史録書房に1冊あることが分かった。今、手元に確保している。
しばらくの間、<サイパン島の椰子>をめぐって文献探索の旅をしてみたい。
「未開の土地に対する単純な好奇心」なのではなく、サイパンに生まれ育ったわたしの原風景を大事にしたいのが、これからはじまる旅の動機なのである。
|