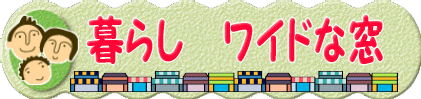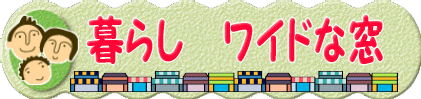「ミカン正月」の記憶である。わたしが国民学校1年生(8歳)のときだった。
正月を前に内地から小包が届いた。
縁側に置かれた白木の箱は早くもあたりに馥郁たる香りを漂わせていた。父の手で開けられた箱の中に偏円形の実が縦横2段に行儀よく並んでいた。あざやかな橙黄色に輝きながら……。
「父ちゃん、このくだものはなんていうの?」
「ミカンだよ。船ではるばる運ばれてきたんだ」
いい匂いの箱だった。ミカンの方はもっともっといい匂いで、色も香りも最高だった。
新年を迎えた。庭の向うの門柱で国旗が風に吹かれていた。が、島の正月では門松やお飾りがなく、お雑煮もなかった。遠く離れた島だから質素だったのか、戦時中は内地も外地もみなそんなものだったのかは知らない。ただ、島に生まれ育ったわたしには餅のあるなしは問題ではなかった。
国民学校1年生が迎えた正月である。家族はそろって内地のミカンを味わった。甘くておいしかった。島のオレンジよりずっと魅惑的だった。内地へのあこがれが一層増した。
学校で「1月1日」の儀式があった。元日でも全員登校しなければならなかった。
下校後、最上級生を中心に10名前後の学童たちが部落の家々を訪問した。年始回りである。一軒ごとにリーダーの挨拶に続いてわたしたちは声高らかに「アケマシテ オメデトウゴザイマス!」と唱和した。
すると、挨拶を受けた家の家長が子どもたちの手に5銭硬貨を握らせてくれた。どの子もうれしそうだった。
|
|
いよいよわが家の番だ。父も5銭硬貨を……と思っていたら違っていた。父は一人一人に例のミカンを配り始めたのである。わたしはうれしかった。が、同行の多くの顔に不満の表情が走ったようだった。集団の雰囲気はやや重くなった。
沖縄の風習を知らなかったからか、子どものしつけについての父らしい判断があったのか。あるいは両方だったのかもしれない。わたしは栗原家の長男として、自慢のミカンが正当に評価されないことを不満に思った。弾んだ気分でいた仲間たちの間に起きた空気の変化に少しだけ傷ついてもいた。
|

橙黄色に輝く温州(うんしゅう)ミカン
|
|
内地から届いたミカンが「温州ミカン」であることを知ったのはずっと後年になってからである。送り主を聞いていなくて悔やまれてならないが、今となっては手段がない。
|
わたしたち母子3人が浦賀の土を踏んだのは昭和21年1月21日のことだった。
引き揚げ援護局鴨居寮(※鴨居は浦賀近くの地名)に入所した。引き揚げ者は可能な限り早く寮から立ち退くよう勧告を受けていた。親戚の青木家・杉山家は帰る家があるので早々に寮から立ち退いた。が、内地に雨露をしのぐところのない栗原家は2月の上旬になって伯父の家に世話になるまで浦賀から動けなかった。
寮の近くに住む斉藤ケイジ君といつか言葉を交わすようになった。年齢も近かったのだろう。浦賀小学校に通っていると聞いていた。昭和19年4月から戦禍のなかの逃避行、抑留生活と続き、学校に通っていないことを異常なこととも思っていないわたしだった。
わたしはケイジ君が学校から戻るのを待っていて彼の家に遊びに行った。
瓦葺(かわらぶき)の屋根を初めて見た。B29の滑走路の下に消えてしまった生家の庭ほどではなかったが、周囲の家々のなかではかなり広い庭だった。わたしの目を奪ったのは冬枯れのなかで陽を受けて黄金(きん)に輝く鈴なりの大きなミカンだった。
|

黄金に輝く大きなミカン(?)
|
|
|
|
あれは、(家族そろった「ミカン正月」で賞味したミカンの大きいやつだ)……とっさにそう思った。のどが渇きをおぼえるほどに欲しいと思った。
|
翌日はハーシーのチョコレートを手にケイジ君の下校を待った。彼との物々交換は簡単に成立した。
|

わたしのチョコレート |
|
アメリカの軍政府から引き揚げ者に支給されたチョコレートの何枚かはこうしてミカンに化けた。
斉藤家のミカンは「ミカン正月」のミカンとは別種で夏ミカンだと知ったのは内地の風物に多少の理解が増した後年のことである。
チョコレートが化けた夏ミカンは1月下旬に食するには酸味が強すぎ、4月から6月に熟し初夏の果物であるとは知らなかったのだった。
南の島にはなかった夏ミカンをわたしは高く評価し過ぎていたようだ。(内地から届いた温州ミカンの味も尾を引いたかも知れない)母はわたしの物々交換を好ましくないこととして苦にしていた。
|