兎の干支年に、調神社に行きました。調神社と書いて「つきじんじゃ」と読みます。「つき」から連想するのは「ウサギ」です。この神社の御使姫は「ウサギ」なのです。
埼玉県の浦和駅から歩いて15分くらいのところに、この神社があります。着いて見て吃驚、何だ、この人の波は? 駅の方から数百㍍に及ぶ人の列が、延々と……。
浦和駅前の広場に「浦和うなこちゃん」の像が建っています。流石にすぐ並ぶ気は失せてしまったので、うなぎ像に触発されて、名物のうなぎでも食べに行くことにしました。
|
しかし、どこも人でいっぱいで、食べ損なってしまいました。
このうなぎ像は漫画家・やなせたかしさんの作です。江戸時代に中山道を旅する人々にうなぎの蒲焼が提供されたので、蒲焼の発祥の地とも言われています。
気を取り直して、調神社の行列に並びます。牛歩すること1時間半、ようやく境内へ。
境内の門には、2羽のウサギが狛犬よろしく睨みを利かせています。大きなネズミのように見えます。
|

参道入口
2011年1月3日撮影:狛犬のように狛ウサギがいます |
|
歩を進めると、左手に手水場がありました。
この手水場にも大きなウサギがいます。柄杓で水を汲んでくれます。
江戸時代からあるとの話なので、昔からいるのだろうが、やけにリアルです。
とても可愛いですけどね。ここまでに来る間に、鳥居が一つもありませんでした。不思議ですね。
|
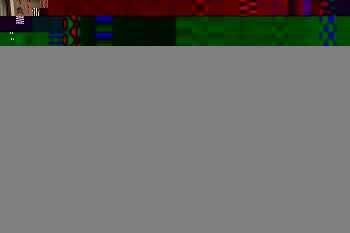
手水ウサギ
2011年1月3日撮影:まるでウサギが柄杓を渡そうとしているようです |
|
|
本殿に来ました。本殿の彫り物の中に、ウサギが跳ねまわっています。「随所にウサギが隠れているのよ」とは、前に並んでいた品の良い奥さんの言葉でした。「確か三箇所あるのよ」と連れ合いの方と話していました。
二礼二拍一礼のお参りを済ませ、干支の縁起物を買いに行きました。可愛いウサギの土偶が売っておりました。
2センチくらいの大きさで、置いとくだけで御利益がありそうでした。面白いことに、このウサギのフォルムは参道にあった狛ウサギにそっくりです。耳が短く頭が大きい、独特の形です。
境内には神楽殿があり舞台の背景の置いてある大きな絵馬に、大きなウサギが描かれている。これで、もう幾つのウサギを見つけたことになるのだろう。 この絵馬はお正月だけのものか、随分綺麗なものでした。
|
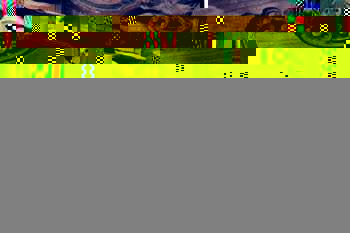
本殿の彫刻
2011年1月3日撮影:この彫刻の中に3体ウサギがいるとか
|
|
|
裏に回って見ると池がありました。池の中には水を吐くウサギと白ネズミのようなウサギがいます。
この池の畔に訳の分からない不思議な石像があります。バットを持っているようで、野球の神様ではないようですが。
瓢箪池の橋を渡っていくと、そこに調神社の元々の本社があります。鎮守の森の中に、こじんまりとした社が見えます。ここには、鳥居が沢山並んでいます。
本殿の大賑わいと違い人数もなく、本殿のお参りには2時間も掛けて歩いたのに、あれっと言う感じです。この先消えてしまいそうなのは、このお社のことです。お正月なのに少し侘しい。
|

元々の調神社
2011年1月3日撮影:小さなお社です
|
|
|
|
|
拝殿をみると、小ぶりながらウサギのモニュメントが沢山ありました。本殿と同じ正面の額の付近に、跳ねているウサギが2羽、彫られています。回廊のところにも見事なレリーフがあります。
江戸時代の様式美とウサギのリアルっぽさがミスマッチで、この神社の面目躍如たりです。
この本殿がオリジナルと聞いていますので、数百年経った今では貴重な彫り物ですね。風雨に晒されている割には、色も形もはっきり残っており素晴らしいものでした。
|
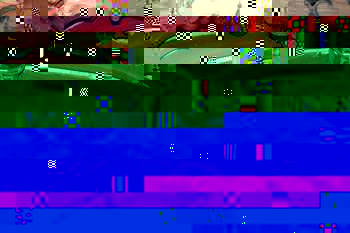
拝殿のウサギ
2011年1月3日撮影:うさぎというよりは鹿のように見えます
|
|
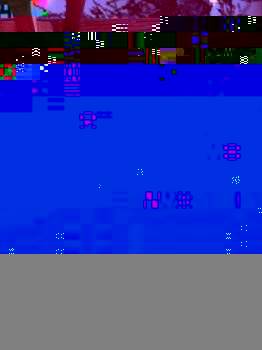
回廊のウサギ
2011年1月3日撮影:リアルによく彫れています
|
|
|