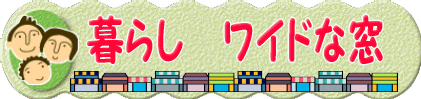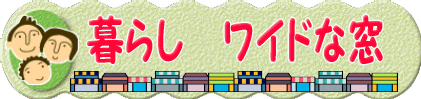|
雁追橋から直ぐのところに、津島神社があります。面白いことに、上新田と下新田に津島神社と呼ばれる神社さんが存在し、縁起も祭神も全く同じです。御祭神は素戔嗚尊で、津島神社・稲荷神社の「合体社」だそうです。かつて水争いをした時に、相手の土地に神社があるとお祭りが出来ないから、同じ神社を造ったのだと、誰かが言っていたように記憶しています。
さらに用水を辿ってみると、「いちょう並木通り」を越えたあたりに、洗い場がありました。
昔はもっと素朴なものだったと思いますが、今は整備されすぎて少し趣が足りません。
|

洗い場
2012年11月9日撮影:昔は野菜を洗ったりしたとか |
|
|
菅堀はここから、稲城長沼駅の方に戻るように曲がっていきます。
中島のあたりに来ると、「旧川崎街道」が通っており、その街道の三差路には石塔群があります。石塔群は、道標、常夜塔、石橋供養塔、馬頭観世音、庚申塔が並んでいます。
あまりにも何気なく建っているので、道祖神か、お地蔵様だと思って見逃しそうです。
|

川崎街道と道標
2014年10月17日撮影:石橋供養塔は大きいので目立ちます |
|
|
菅堀は住宅街を通ってきましたが、これからは畑地が垣間見える土地を通ります。農作業をされている方や、声を掛けているご近所の方たちの姿が、何ともほのぼのとしています。
やがて、橋のたもとに葎草橋碑が見えて来ます。石碑がそっぽを向いているのと、あまりにも地味な感じで建てられているので、見逃してしまいました。探し回った結果、ようやく草の中から石碑が見つかりました。
この石碑は、天保9年(1838年)に長沼、押立両村が、大丸用水の木橋を石橋に架け替えたことで、建てられたものです。
石碑の側面に<渠田川や多摩の葎の橋はしら、動ぬ御代の石と成蘭>と彫られています。
また、傍らの看板には、江戸・八王子・川越・府中・小田原・大山・川崎・日光山の八方面の道標とされていたことが記されています。
|

葎草橋跡
2014年10月17日撮影:特に電柱が悪さをして隠しています |
|
稲城市の案内板「-江戸時代の歴史を中心として-」では、
「菅堀は村の北都を迂回するような形で流れたのち押立村方面に向かって、喧嘩口(けんかぐち)と呼ばれる分水口でさらに三つの流れに分かれます。」
と既述され、菅堀、北堀、中堀に分かれます。この分かれた堀はここで暗渠になりますが、稲城大橋につながる道路(地下道)では、セミシェルターの天井空気抜き部分で箱樋として現れます。
|
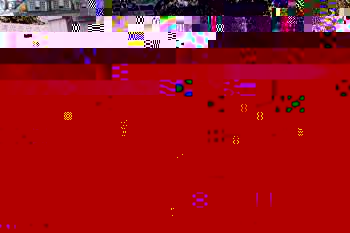
喧嘩口
2014年10月17日撮影:右が菅堀、左が中堀、さらに手前に北堀に分かれます |
|
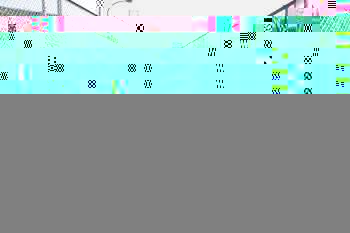
喧嘩口付近
2014年10月17日撮影:稲城大橋地下道、箱樋が列をなして見えます |
|
菅堀をさらに矢野口のほうまで辿っていくと、ルネ稲城のマンション前で分かれます。しかし、分かれた先には、大丸用水としての記録がありません。多分、昭和の時代に梨畑か、葡萄畑に用いるために、新たに分岐させたのでしょう。
菅堀は矢野口を過ぎると、豊堀につながり用水は消滅します。
最近、稲城長沼駅の南側を流れていた新堀が、市街化整備工事により駅側に付け替えられ、古い用水は水が枯れた状態になっていました。
江戸時代の遺構として石積みだけでも残らないものかと思っています。 (完)
|

矢野口付近分水堰
2004年11月24日撮影:前はここに「いなげや」がありました |
|