なんとABC兵器のうち、B(生物兵器)、C(化学兵器)までもが、ここで研究されていました。
※ABC兵器:atomic,
biological and chemical weaponsの頭文字をとって付けられた。
戦争は残酷なものだなあと思うのは、こういう開発を見せられた時です。
この研究所で開発した風船爆弾(ふ号兵器)などは、ネーミングのせいか、おっとりと聞こえますが、風船が落ちてきても爆発、撃ち落としても爆発、やはり怖い代物です。
他にも、侵攻しようとする国の偽札や、暗殺用の武器、精細写真術(そう言えば、当サイト「鬼人粋人伝」登場の羽根田武夫さんは、藤沢の海軍電波兵器測定学校で、写真技術の教官をされていたそうですが、ここの研究所には教えに来なかったのか、興味をそそられます)、電波兵器が展示されています。
明治大学の資料館が注目されている点は、旧日本軍の研究施設をそのまま保存していること、あまり公にされない秘密戦の資料が保管されていることなどです。
現に見学に行った日にも、海外のお客さんが来ており、教授と院生と思しき方々が、施設の来歴について流暢な外国語で対応されていました。
|
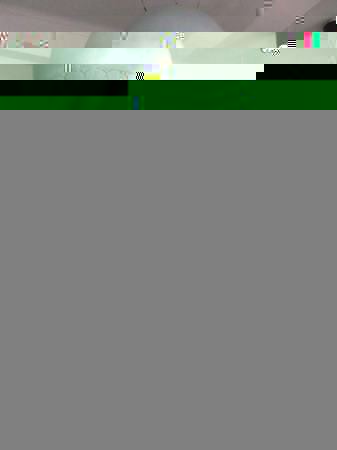
風船爆弾
2014年8月14日撮影:資料館では当時の研究成果を模型で見せています
※明治大学平和教育登戸研究所資料館蔵 |
|
|
現存する施設
この資料館は、数年前までは設立当初からの木造の建物でしたが、老朽化し危険なため、新しいものになりました。5号棟、26号棟は、数年前に取り壊したので、現存していません。
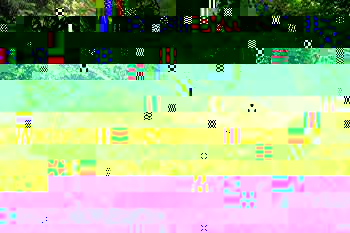
弾薬庫跡
2014年8月14日撮影:入口の後ろが山になっている
資料館の入り口斜め前にある地下壕倉庫は、「弾薬庫跡」と言われています。私の子供の頃には、このような防空壕跡に人が住んでいました。
|
|
倉庫跡
2014年8月14日撮影:丘の下にひっそり隠れています
明治大学の第1号舎1号館裏手の、菜園の麓に地下壕があります。今は園芸学部の物置として使われているようです。「花卉園芸」と書かれています。
|
|

消火栓跡
2014年8月14日撮影:もう一つの消火栓は,半分地中に埋まっています
消火栓は、構内には相当な数があったと聞きますが、今現在、判っているのは2つです。消火栓の文字の上に、帝国陸軍を表す星形が付いています。
|
|
|
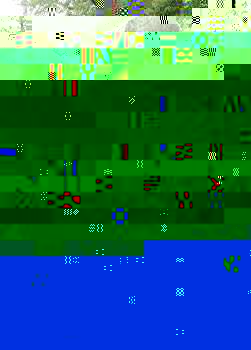
動物慰霊碑
2014年8月14日撮影:正門の裏にあり、目立たないので探しづらい
動物慰霊碑です。実験に使われた動物たちの霊を慰めるために、非常に立派な石碑を建てています。実験のために死なせた動物たちに、愛情を感じていたのかもしれません。
|
|
|
|