|
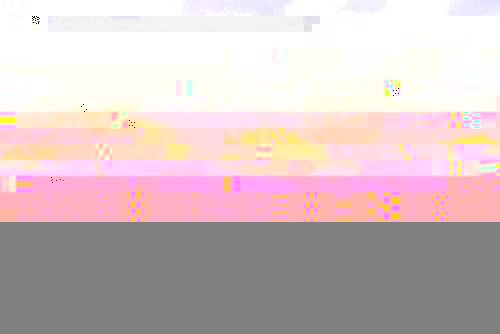
旧小松川閘門跡
2012年4月30日撮影:西洋の古城のように見えます
|
|
|
江東区船番所資料館――東京都江東区大島
番所資料館が大島小松川公園から、見渡せるところにあったので行ってみました。
この資料館前の東屋が、船番所だったようです。江戸時代はもっと水際にあったとかで、低い位置にありました。
資料館の中には、船番所を再現したジオラマがあり、お金がかかった仕掛けがあって、さすが、東京都はお金持ちだなあ。
年配の男性の方が一人、このあたりの好事家なのでしょうか、丹念に遺物や文献を見ておりました。
写真を撮ってはいけないところで、パチリと一枚、もちろん、私はこの方のひんしゅくを買っていました。
|

中川船番所資料館
2012年4月30日撮影:手前の船番所は公園の休息所です
|
|

中川船番所資料館内
2012年4月30日撮影:実物大のジオラマです
|
|
|
現在稼働中の
新扇橋閘門――東京都江東区猿江
実際に稼働している閘門を見に行ってみました。新扇橋閘門の手前に小松橋があります。トラス橋で年代を感じさせるものです。背後にスカイツリーが望めます。この橋から、閘門を覗けます。なかなか迫力があります。
川の中に信号機があり、まるで交差点のような雰囲気です。小松橋と閘門が近いので、閘門の仕掛けが手に取るように分かります。
ニョキッと伸びた操作室が、ここは普通の橋と違うんだぜ、ワイルドだろうってなことを言っているようです。ぐるりと廻って前扉のほうに行ってみます。ゆっくり歩いていくと、小さな公園が閘門の脇にありますので、入ってみると絶好の見学場所です。操作室は見晴らしが良くって、気分がよさそうです。
閘門事務所の前にお住いのおじいさんが、超高級なカメラを見せて、東京スカイツリーの建設中の写真を大量に見せてくれました。
前を回ると、ちょうど閘門を潜って船が出てくるところです。本当にラッキーでした。閘門が上がっていく様を、パタパタ写真のように写しまくりです。これならデジタル・ビデオカメラで撮ったほうがいいですね。
「扇橋閘門」の説明板には、
「江東区は、東側が地盤が低く西側が高い地形になっています。そこで1971(昭和46)年策定の江東内部河川整備計画では、東側を常に水位を一定に保つ水位低下区域としてまた西側の感潮部を耐震区として整備をすることになりました。この閘門は、両区域の接点に当たる小名木川の中間に位置し、水位差を調整して舶の航行を可能にするための施設です。30億円の事業費と5年3ヵ月の歳月を費やして1977(昭和52)年に築造されたものです。この方式は,パナマ運河と同じです。」
と書いてあります。
耐震区って何でしょう? 何となくは理解できますが、良く分かりません。撮影場所は、新扇橋。新扇橋は小松橋とそっくりです。
|

小松橋
2012年4月30日撮影:青い水道橋の向こうに閘門があります
|
|
|
|

新扇橋閘門
2012年4月30日撮影:堰の上に載っているのが操作室
|
|

新扇橋閘門
2012年4月30日撮影:普段は閉まっており、めったにない機会です
|
|
|
|
「民営機械製粉業発祥の地」の碑が、新扇橋のたもとにあります。碑文は、以下のように。
「1879 (明治12)年, 明治を代表する実業家 雨宮敬次郎は、水運の便のよい小名木川に着目して、この地にそれまでの水車動力に代わる 蒸気機関を動力源とした、 民営では最初の 近代機械製粉所「泰晴社(たいせいしゃ)」を創設しました。(中略)
雨宮の製粉事業は 東京製粉合資会社に受け継がれ、1896(明治29)年に 日本製粉株式会社に改組されました。また、 小名木川沿岸には 明治30年台に製粉会社が次々と設立され、全国でも屈指の小麦粉生産高を誇るようになりました。(後略)」江東区
この碑の脇を通って、川沿いの遊歩道に降りることができます。水は穏やかで、小名木川を満喫できます。
|