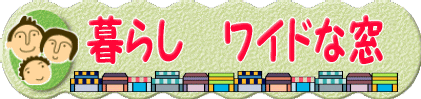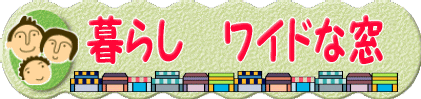私的「浦島伝説考」
不老不死は権力者の夢
個人的には、浦島伝説と補陀落(ふだらく)伝説と徐福伝説は、関連性があると思っています。まあ、伝承ですし、有力な物証もありませんし、勝手に思っているだけですが…。
この3つの共通点は、不老不死です。秦の始皇帝は天下を取り、自己の栄華を永続させるために、徐福に不老不死の薬を探させます。徐福は、若い男女3千名と膨大な生活必需品を何艘もの船に積み、東方の蓬莱山(またの名を不二山と言います)をめざして出かけます。その地が日本とも台湾とも言われております。そのせいか、日本各地に徐福伝説が残っています。
垂仁天皇は田道間守に酥(そ)を探しに行かせます。酥は酪(らく)の最高のもので、その上を行くのが醍醐でした。醍醐とは想像を絶する美味な食材だそうで、また、不老不死の薬だと言われています。酪とはチーズのようなものと言われていますので、醍醐も乳製品かもしれません。しかし、田道間守は不老不死の薬として、蜜柑(みかん)を見つけてきます。
徐福伝説と似た話に、補陀洛伝説があります。補陀洛山(ふだらく、ポーダラーカ)とは観世音菩薩が住まわれている浄土のことで、南方の海中にあるとされています。日本ではとくに和歌山の「補陀洛渡海」が有名で、浄土をめざして粗末な箱舟で海に繰り出します。
華厳経では、「補陀洛は泉があふれ木々が繁り、花の香りが漂い、観音菩薩が金剛石の上に座していらっしゃる」とのことで、永遠の時間を過ごせるとのこと。死もなく、病気もなく、苦痛もない、不老不死の究極です。
補陀洛山と呼ばれる山は、関東にも数多く存在します。とくに日光の東照宮が有名で、東照宮の中の日光二荒山神社は、補陀洛が二荒(ふたあら)に訛り、音読みして日光(にこう)となったと言う説があります。
さて、補陀洛浄土は南海の海にあることが判りました。となると次の連鎖は浦島伝説です。
浦島太郎は南海の竜宮城に連れて行かれます。蓮法寺(横浜市神奈川区七島町)の「丹後国風土記」によると、「浦島子が海に出て五色の亀を釣り、船の中に置いて眠ると、亀はきれいな女に変身する。女は自分は仙界の者で、風流な浦島子に感応し、参り来たと言い、浦島子を誘って不老不死の蓬莱山に連れて行きます。仙女とともに、蓬莱山で3年間、生活を送りますが、故郷の両親が恋しく帰郷を申し出ると、女は別れを嘆き、戻って来たいなら決して開けないようにと言って玉匣(たまくしげ)を授けます。故郷に戻った浦島子は、地上では3百年もの時間が経過していたことを知り、驚きのあまりに約束を忘れ玉匣を開けると、若々しかった肉体は風雲とともに天空に翔り飛んで行き、浦島は鶴になり、竜宮の亀姫(乙姫)と共にめでたく暮らし、夫婦の明神として祭られた。」
浦島伝説にも、蓬莱山が出てきます。徐福伝説と補陀洛伝説が微妙に絡み合っているようです。
|
浦島伝説、その証拠は?
神奈川区内の建造物その1 蓮法寺(元観福寺)――神奈川区七島町
横浜市神奈川区に観福寺という浄土宗の寺院があり、通称「浦島寺」と言いました。この寺の略縁起によれば、三浦半島出身の浦島太夫が妻子とともに丹後半島に赴任し、息子の太郎が浜で大亀を釣ります。 この亀が美女に変身して太郎を竜宮城へ連れて行き、竜宮城ですばらしい日々を過ごします。太郎はやがて帰郷を願い、玉手箱と観音菩薩を与えられます。
丹後半島に戻った太郎が両親や知人の不在を知って観音菩薩に祈ると、「私を背負って関東に下れ」との夢告を得ます。 三浦半島に戻った太郎は,自分の9代後の子孫に逢い、両親の眠る地を知らされます。それが神奈川の浦島丘でした。
太郎は両親の墓前に小堂を建てて、竜宮から持ち帰った玉手箱と観音菩薩を安置し、何処かへと去って行きました。神奈川付近の漁師は、海に現れた浦島太郎と乙姫の観音菩薩護持の誓約を聞き、浦島太郎の建てた小堂を、立派な寺院(観福寺)に建て直し、観音菩薩を信仰し続けました。浦島太郎が竜宮城から持ち帰った観音菩薩を本尊とし、亀乗聖観世音立像と浦島大明神立像・亀化龍女神像の3像を祀りましたが、観福寺が火事で焼失したため、今は慶運寺に祀られています。 (有鄰 No.458「よこはまの浦島太郎」阿諏訪青美著)
|
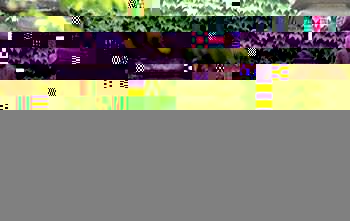
蓮法寺伝供養塔
2008年7月21日撮影:観音像の背後の大きなものは亀
|
|
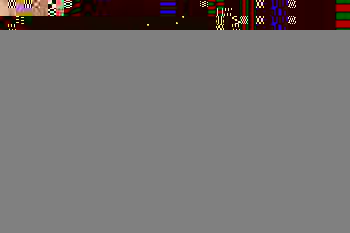
蓮法寺山門の寺紋
2008年7月21日撮影:亀が可愛らしい
|
|
神奈川区内の建造物その2 慶運寺――神奈川区神奈川本町
ここで分かることは、南海か東海に蓬莱山(竜宮、常世:別名不二山)があること。その地は観世音菩薩がいる楽園であること。不二山とは不死山のことで、その地では永遠に歳を取らないか、現世の 100分の1 程度の時空間の中にあること。その地が日本ならば「富士山」がそうでしょうか。
最近、中国本土で徐福の子孫がいることがわかり、徐福が史実の人であることが分かりました。もしかすると、浦島の伝承のなかにも、僅かな史実が含まれている可能性もあります。
蓮法寺には、浦島太郎と乙姫の供養塔があります。慶運寺は、幕末にはフランス領事館として供用されました。この寺には先ほどの3像と山門入口に亀像が残されています。
|
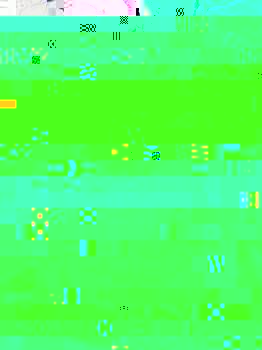
慶運寺山門の碑
2001年1月7日撮影:別名「うらしま寺」と言います
|
|

慶運寺山門の碑
2008年8月21日撮影:横から見ると亀がいます
|
|
神奈川区内の建造物その3 浦島観音――神奈川区亀住町
亀住町公民館(横浜市神奈川区亀住町)の前には浦島地蔵が建っています。また、このあたりの第一京浜国道にも、亀をモチーフとした街路灯や車止め(上部が亀)があります。
|

亀住町の浦島観音
2009年11月23日撮影:隣は馬頭観音の碑
|
|

第一京浜国道の街路灯
2008年8月13日撮影:波に亀です。別の街路灯は波のデザインの切子硝子細工です
|
|
|
|
|
|
|
|
|