今年の夏はお盆休みもなく働き、ふと気がつくとすでに9月になってしまい、朝晩に半袖では寒い季節になってきました。
多忙極まるというわけではなかったのですが、毎日のように処理すべき業務が入っていて、まとまった休みを取ってどこかに行くということができませんでした。土日を使って一泊の温泉旅行に行ったくらいが唯一のバカンスと言える内容となってしまいました。
ホテルでの仕事の合間に函館山へ
ビジネスホテルの一室は上司や電話といった様々な外乱に囲まれたいつもの環境に比べると、その閉鎖性からきわめて能率が上がる場所なのでしょう。いつの間にかどっぷり集中して仕事に没頭し、気がつくと昼の1時を過ぎていました。
午前中の雨が止み、何か食べようと函館に来るとよく行くそば屋で、函館名物のイカ天が入った蕎麦を食べてから、その店を出て函館山を見上げた途端、唐突に登ることを考えてしまいました。
以前、函館に住んでいた当時、登山を始めたこともあって、よく足慣らしやトレーニングといって登っていた山です。函館山といえば夜景が有名で、頂上から眼下に見下ろす夜景は、香港、ナポリと並んで世界三大夜景に数えられているほどです。足下に迫っている市街地と頂上が近接している割に高度差があるため、夜景に迫力が加わり人気があるのだと思います。といっても、高度差というのは大げさかもしれません。標高は334㍍、東京タワーより1㍍高い程度の山なのです。それ故、市街地に近い低山ということで、昼下がりにも気軽に散策が楽しめます。
|
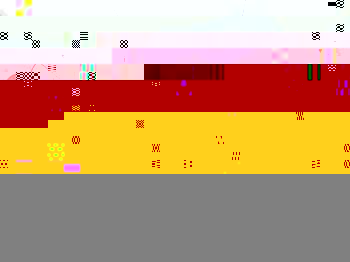
市街地から函館山を見上げる
|
|
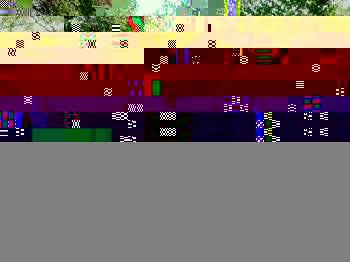
登山口にある函館山ふれあいセンター
|
|
函館山ロープウェイ乗り場を脇目に、住宅地の細い道を進んだ所に登山口の一つがあります。ここはいくつかの登山口で一番アクセスしやすく、多くの利用者への情報発信拠点として「函館山ふれあいセンター」が設けられております。
この日は生憎の休館日でしたが、案内リーフは自由に持って行けるようになっています。一部ずついただいてペットボトルの水を買ってから、いよいよ登りにかかります。
有名な夜景では見られない、昼間の函館山の魅力
出張で着ている会社の作業衣スタイルなのでムリをしないよう、登りに苅分の登山道、下りに昔の車道を使う行程を、としました。現在使用されている舗装の車道とクロスしてから、左に行くと苅分の汐見山コースとなります。
このコースは一気に登ってから、細い尾根伝いに主稜線に出るコースで、秋や冬に登るのがとくに良いコースでした。ひょっとしたら夏に登るのは初めてかもしれません。連日続いていた雨のせいなのか道端にキノコが目立ちます。タマゴタケでしょうか。食用に向いているらしいですが、一切食欲が湧きません。
|
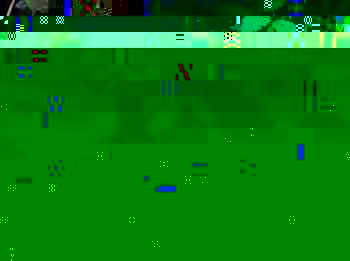
タマゴダケ? 最初に食べた人はスゴイ
|
|
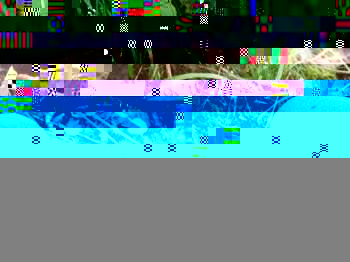
ヤマイグチ? これも食べられる・・・
|
|
|
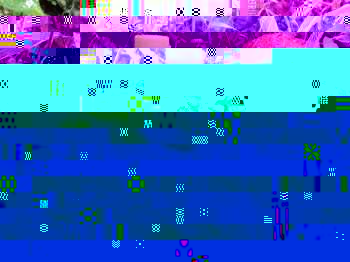
ノウタケ ペットボトルに匹敵する大きさ
|
|
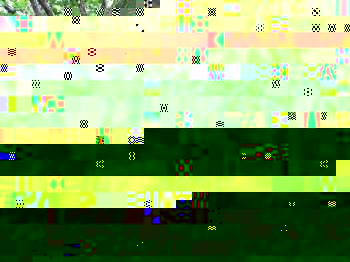
主稜線へ続く尾根道
|
|
よく分かりませんが、とにかく大きなキノコが目立ちます。中にはペットボトル級のものもあります。写真に納めておいて帰ってから調べることにしました。出張で携行しているカメラなので接写に向きません。四苦八苦しながらピントが合っているのかよく分からないままシャッターを切っていきます。
尾根に出ると風に当たることができ、蒸したキノコの登り坂を来た身には爽快です。秋になれば頭上から足下まで奇麗な紅葉が楽しめるポイントです。また、冬は稜線がリッジ状になる部分があるので結構スリルがあったように覚えております。
そんな尾根を進むとなだらかな主脈に到達します。この辺りまで来ると日当たりが良いせいか、花々が増えてきます。函館山は何かと夜景で有名ですが、実は山野草などの宝庫で、以前足繁く通いこの山で多くの花の名を覚えました。雪解けと同時にフクジュソウ、イチゲと始まり、とくにスミレは多種にわたり5月くらいにかけては非番も惜しんで、植物図鑑を片手に登っていたくらいです。秋の花にはまだ早かったようで、夏の花が季節の移ろいを惜しむように寂しげに咲いておりました。
|
|