駅大改修と東急ストア
東急が菊名駅の大改修を計画したのは、出水と新幹線のためであったが、その際駅の天井を強固にして、大東急ストアを作ってしまった。近隣のスーパーや商店は大打撃を受けたらしい。中小企業というものは哀れなものである。
しかし、世の中には不思議なことも、あるもので、中小企業でも大企業に負けないで成長してゆく、勇ましい例もある。
|
|
たとえばカメラのドイ(北九州のカメラ小売店から…)、メガネドラッグ(メガネの利益率がべら棒に良かったので…)、イトーヨーカドー(洋品店から…、薬ヒグチ(大阪の一薬局の息子が…)、ダイエー(神戸の小さな安売り店から…)、ロッテ(チューインガムの内職手作業から…)などなど、不思議な連中もいるから、そう悲観するにも当たらないだろう。
そういえば、大東急の開祖・五島慶太も、国鉄の一役人に過ぎなかった…。中小商店諸君! 現状ばかりを気にしないで、朗らかに頭を働かせよう。
|
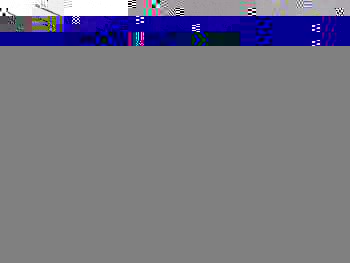
露店も出る西口駅前と横浜線のホーム |
|
小さな喫茶店、ママは人気者
菊名駅の西口正面の本屋さんの裏に、小さな喫茶店がある。ここのママは、たいへんな人気者で、近所界隈の人が集まる。小さな店だから、たちまち満員になるが、そのたびにうまくしたもので、誰かがスーッと出てゆく。こういう雰囲気の店は、昔は方々にあったものだが、今では極めて珍しい。PTA帰りの若い奥さんも気軽に立ち寄れるし、2階は若い学生さんたちのクラブのようになっており、時折狭い階段を津波のように駆け降りてくる。
この小さな喫茶店の壁のあちこちには、アンティックドールがかけてあり、電話台の下には、ドールの本が重なっている。ふと手にとって読むと、それはアンティックドール展のカタログであった。そして、その値段に一驚した。たとえば、1885年のフランス・ジュモー作「ギターを奏でる娘」1800万円、「花の手入れ」1350万円、一番安いので50万円が1個だけあった。これらは展示会中に売切れてしまうという。
わたし自身男性であり、孫が3人とも男の子であるため、人形に対する関心が薄かったことに気付き、感電したような衝撃を受けた。
ママさんは2年ほど前まで、毎年自身で英・仏・独へ行き、1か月位滞在してアンチィックドールを買い求めてきたという。日本で買うことを考えれば、旅費・滞在費はたちまち出てしまうと言っていた。コレクションもかなり進んだので、目下この近くに「人形の館」を建築中であり、5月末には開館できると、張り切っている。
菊名名物がふえるのを楽しみにしている住人たちが、入れ代わり立ち代わりコーヒーを飲みながら、人形談義に華を咲かせている。しばらく来ないうちに、菊名という街は、夢のあふれる楽しい街になっていた。
|
アンティックドール、その世界
ものはついで、ママのアンティックドールのお話を少々記してみよう。
人形の発生の源には、宗教的なものがある。紀元前のエジプトでは、副葬品の中に〝人形(ひとかた)〟があった。ギリシャ、ローマ時代になると、観賞用のものも現れてくる。人形は少女のものであり、結婚の日まで大切に持ち、結婚のとき神にささげる、すなわち神に処女を返還するという意味を持っていた。
その後、18世紀まではパンドラといって、ファッションドールの性質を帯びており、フランス宮廷の最新のモードを、世界各国の宮廷へもたらす使節となっていた。写真やテレビやファッションショーのない時代、ファッションモデルの役目を果たしていたのである。しかし当時は、人形は王侯貴族の愛玩物であり、子供の手には入らなかったのだ。
19世紀に入ると、革命後のブルジョワの台頭で、民間の窯ができてきた。豪華な衣裳をつけたビスキュードールは、少女たちの熱烈な憧れの品で、ステータスシンボルであった。やがて天才的な人形師、ジュモー、ゴーチェ、ブリユーなどが工房を開き、次第に市場に売り出されるようになっていった。
その頃には、〝オートマータ〟(自動人形)が最盛期を迎える。字を書く人形、チェスをする人形、宝石の実をついばむ鳥のオルゴールなど、いろいろ出現した。しかし超高価なため、王侯貴族の独占物であった。やがて、少女たちの身近なものとして、首の回る人形、関節を曲げる人形(抱き人形)などが普及し、衣裳の着せ換えなどが行なわれるようになった。
しかし、全盛だったビスキュードールも、第一次大戦の勃発で、一時中断された。戦後は新素材セルロイドによる大量生産により、徐々に衰退していった。
そして今日では、アンティックドールとして、古きよき時代の香りを胸いっぱいに秘めて、その碧く澄んだ瞳で私たち現代人を魅了するのである。
ママの雄弁を要約すると、以上の如くである。菊名名物〝人形の館〟の落成を待望しつつ、ペンをおく次第である。 |
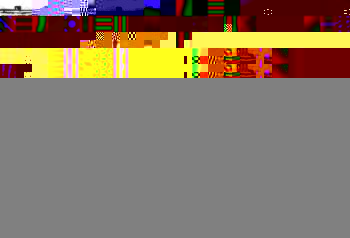
人気のある小さな喫茶店
|
|
|