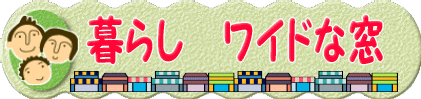 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| NO.78 2014.6.28 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
 |

駅誕生秘話(日吉~桜木町)
|
|
編集:岩田忠利 |
|
| 掲載記事:昭和56年(1981年)7月1日発行「とうよこ沿線」.6号から |
|
◆日吉権現ちなんで、日吉
若人の熱気がムンムン……これほど〝フレッシュ族〟がいっぱいの駅があるだろうか……。
日吉の駅名は、駅所在地の日吉村に由来する。現在の日吉地域を構成する日吉本町あたりは江戸時代「駒林村」、日吉町が「矢上村」、下田町を「駒ケ橋村」、箕輪町はそのまま「箕輪村」といった。
明治22年の市町村制施行の際に日吉に改称。これは金蔵寺にまつってある日吉権現にちなんだというのが一般説である。(談・佐相政雄氏「郷土史家」63歳)
現在、線路の通っている部分は、昔、谷底で、谷を埋めたてて駅をつくった。日吉駅造成のために土を削った現在の、矢上公会堂の所には、「東急線発祥の地」という碑が建っている。
|
|
|
学生ハイツのあたりには、箕輪池という用水のための大きな池があり、夏は水泳、冬はスケートが出来た。開通当初は、ホームは一棟だけで、平屋建ての無人駅だった。大正9年頃、日吉台の土地は坪7銭で、あたり一面、春は麦畑、秋はイモ畑だった。駅付近の土地を、東横電鉄が坪5円で買い取り、分譲地として売り出した。観光事業として、日吉ではサツマイモ掘り・イチゴ狩りなどもやっていた。
昭和5年、東横電鉄が慶応義塾大学に日吉台の土地32万平方メートルを寄付し旅客誘致をはかった。
その結果、慶應義塾大学予科の日吉移転後、日吉の土地の売れゆきは、それまでの10倍以上にも伸びた。また、大学移転に伴い、それまで駅前に12~3件しかなかった商店が、洋服屋や喫茶店をはじめ、急激に増え始めた。
今では、日比谷線も乗り入れ、マンモス学園として新鮮さにあふれ、各商店は賑わいをを見せている。
談・杉崎真一さん・65歳/取材・文・海老塚 操(綱島・学生)
|

日吉の街は西口駅前を起点に放射状に広がる
|
|
|
◆名馬、温泉、桃で栄えた綱島
大正15年2月、開通時の駅名は「綱島温泉」であった。昭和19年10月20日に「綱島」に改称された。戦時中に〝温泉〟というような名称は、士気にかかわるため、やめたらしい。
綱島という地名の由来は諸説あるが、昔この辺は東京湾の入江で、現在の高台部分だけが島になっていた。さらに〝綱〟は牧場を意味し、鎌倉時代に名馬の産地だったため、とも聞く。また、島が細長く連なっていたので、“つながり島”を略して「つな島」と呼ばれた、ともいう。綱島三郎という武士が住みついており、その姓からとったものである、という説もあるが、〝決定打〟ではなさそうである。(談・池谷光朗さん 55歳)
|
|

東横線開通時は「綱島温泉駅」だった綱島 |
|
綱島地区は、昔、地下を70メートルくらい掘ると〝赤水〟が出たが、飲用水にはならなかった。この水を風呂用に使っていたところ、持病のリュウマチが治り、不思議に思った人がいた。内務省温泉研究所に成分分析を依頼した結果、「ラジュウム沃土エマネチオン」の含有量がわが国で3番目に多いことがわかった。
それに着目して昭和2年、東横電鉄直営の綱島温泉浴場が開場、入浴料は20銭だった。ただし往復乗車券所有者は無料で入浴できた。体の良く温まるラジュウム温泉は、たいへんな賑わいとなった。今では綱島東口にある「東京園」がその名残をとどめる程度になってしまった。
また明治40年頃からピーチゴルフの先々代・池谷道太郎さんが綱島の土地に合った「綱島桃」を開発。これが味良し、香良しと評判になり綱島一帯は農家が桃栽培の果樹組合を組織し西の桃の名産地、岡山県と並ぶ東の桃の名産地、綱島と呼ばれるほどになった。昭和13年の洪水で桃の木が土砂で埋まり立ち枯れ。それに太平洋戦争の食糧増産と相まって衰退、今は綱島最古の商店街「桃栄会商店街」にその名を留めるのみとなった。
(港北百話』昭和47年出版より) 文・海老塚 操(綱島・学生)
|
|
|
◆実業家・大倉邦彦の名をとって、大倉山
大倉山駅は東横線開通時、「太尾駅」といった。所在地の太尾町にちなんでつけられたのであったが、昭和3年3月「大倉山駅」と改称された。
大倉山というその名は洋紙界の実業家、大倉邦彦氏の当地域に対する貢献により名付けられ、駅名もそれにちなんだ。大倉山駅北側高台一帯を大倉山という。
昭和7年3月、渋谷~桜木町間が開通、記念のため当地に白梅約5百本が植樹され、大倉山梅林がオープンした。また北側の山陰に大倉山天然スケート場(民営)が開設され、沿線各駅に「当日のスケート可能・不可能」などと、その日のコンディションが掲示されたことを覚えている。滑れない日のほうが多かったようだ。
電鉄側では数年前まで、ここで梅まつり・宝探し・モデル撮影会などを盛大に催し(現在は中止)乗客を誘致した。また付近の住宅分譲地大売り出しには、梅林のある〝閑静な住宅地″として宣伝、大成功を収めたらしい。
駅西側、線路づたいの坂を登りつめると、大倉精神文化研究所の白亜のギリシャの神殿風の建物が目につく。少し進むと、すり鉢形のところが梅林となっている。周辺の小高い丘には梅のほか、つつじ・松・もみじ・桜なども生い茂り、人びとの心をなごませている。
昭和48年、当梅園はあやうく会員制のテニスコートになるところだった。が、町内の有志で「大倉山の自然と環境を守る会」を結成。反対運動(横浜市民2万人の署名陳情)を起こし東急本社・県庁・市庁を何度も訪問し、働きかけ、同計画をくい止めることに成功した。
当公園は港北区唯一の自然公園であり、野鳥、野草の宝庫である。公園山頂から望む富士山の雄姿、丹沢山塊の眺望は天下一品である。
なお大倉山駅周辺は近年中に大改造されることになっており、地下に自転車1千台を収容できる施設が完成した暁には、駅周辺の放置自転車問題が解消され、面目も一新されることであろう。
文・井上 幹(大倉山・自営業)
|

梅林とスケート場で賑わった大倉山駅もいまは、商店街再開発工事で大きく変わろうとしています |
|
|
◆鎌倉時代からの地名、菊名
うっすらと辺りが暮れゆくころ、改札口からはき出された大勢のひとびとは、足早に家路に向かってゆく……。
ここ、私の住む菊名・・・でもこの駅名、あまり好きではないのです。
A「あなたどこに住んでるの?」
B「きくな」
A「?」
というように「聞くな」と間違えられ、漫才のようになってしまうのです。
でも、菊名という地名が初めて文献に登場するのは、菊名東口にある浄土宗のお寺、蓮勝寺がりますが、ここの山号が「菊名山」と言います。ここの創建は正和年間(1312~1317)と言いますから鎌倉時代後期、こんな大昔から「菊名」の名前が地名として呼ばれていたのです。
東横線が開通したのは大正15年(1926)2月。すでに明治41年(1908)9月、横浜線は開通し菊名地区内を18年も以前から走っていたのです。でも菊名の人々は汽車の姿を眺めるだけで利用することはできませんでした。それは、菊名地区内に駅が無いからです。
東横線の駅が完成したとき、地域の住民はどれほど喜んだことでしょう・・・。当時、駅の所在地は橘樹郡大綱村大字菊名。住民合意で駅名を地名「菊名」で決め、開通日には男女長老を主賓にして青年団や村役員でその喜びを記念写真に収めています。
しかし、その開通が禍根を残すことも記しておかなければなりません。皆さんは、現在の菊名東口から妙蓮寺方向へ100㍍ほど先、踏切りを渡ると錦が丘の住宅地に立派なロータリーと放射線状の街区があるのをご存じですか?
じつは、東京横浜電鉄はここを田園調布や日吉のような街区の駅前に造成したのです。錦が丘は今日、“桜の名所”になっていますが、このとき、今上天皇の誕生を祝い、錦が丘の皆さんが桜の植樹したのです。
「あんな所に駅を造ったら困る。わしの土地に電車は通さない!」と大反対したのが、線路を挟んだ両側の大地主2軒。造成がすっかり済んだ電鉄側は困惑。結局、泣く子に勝てず完成の錦が丘ロータリー街区はそのままに、急遽現在地に駅舎を建てたのでした。 |
|

開かずの踏切で悩まされる菊名西口
|
|
現在の駅の地形は、東西口とも急勾配の丘が迫る谷底。ひとたび大雨が降ると雨水が流れ込み、線路はたちまち冠水します。東横線は<ただいま菊名で線路が冠水、不通です>の張り紙が各駅に出て、乗客を困らせたものでした。
もう一つの問題は渋谷側のホーム脇の「開かずの踏切り」。ラッシュ時は1時間に50分程度遮断機が下りたままの有り様で車も人も大渋滞・・・。なにしろ、踏切上に電車がはみ出し、停車しているのですから。結局、ホームの横浜寄りのすぐ先が急カーブしているため構造的にホームの長さを電車停車に見合った長さに造れなかったのです。従って「踏切り上に電車が停車」という珍光景をいつも露呈しているのです。
菊名駅の駅長は大倉山~白楽間の4駅を管理する“管理駅”です。みずからの駅の上記線路冠水問題は、昭和47年線路をかさ上げして駅舎を橋上駅舎化して解決しました。しかし毎日悩まされる「開かずの踏切」問題は未解決。早急に対処して管理駅の面目を保ってほしいものです。
文・浅野桂子(菊名・学生) 加筆:岩田忠利
|
|
◆駅前の寺院の名前から、妙蓮寺
妙蓮寺……一見〝お寺の町〟というイメージが浮かぶが、ズバリその通り、駅前のお寺の名前を駅名にしている。もっとも線路敷設当時、寺が6百坪の土地を東京横浜電鉄に提供する代わりに駅名を「妙蓮寺前」とするの約束を取り付けた。そう、なるほど、という気がした。
その後数年が経ち、電鉄が将来を見越してホームを菊名寄りの水道道沿いにまで移動するという建設計画を立てた。それには寺や商店街が大反対して電鉄側に「土地を返せ」という話にまで発展、昭和6年1月1日、建設計画はお流れになり、駅名を“妙蓮寺前”から、寺院名どおりズバリ「妙蓮寺」に改称し、一件落着といったエピソードもある。
大正15年2月東横線開通当日、駅では祝い餅がまかれ、地元の人は餅拾いに総出で出かけ「電車の運動会だ!」と電車の窓から手を振ったりして喜んだ、という。
しかしその頃、乗客はめったになく乗務員だけで走っていることが多く、たまに乗る客は社長などの大金持ちで、地元の人は電車通りを、指をしゃぶり眺めていたという。
菊名駅を奥へはいると篠原町という所がある。現在は閑静な住宅地として知られているが、昔は『大綱村の満州』と呼ばれていた。 また、富士塚という町があり、当地は、大昔、海だったらしく、貝塚があったらしい。
太平洋戦争で、爆弾を落とされたりしたが、多くの人が難をのがれることができ、せめてもの幸いだった、という。
談・峰岸宇助(篠原東) 文・石井真由美(綱島・店員)
|

右、駅前の踏切りを渡ると駅名の「妙蓮寺」の山門 |
|
|
◆馬にご縁があって、白楽
地名「白楽」という地域は、ごく小さく狭い面積で、歴史的にも新しい所のようです。ここは昔からある地名の橘樹郡大綱村大字白幡にあり、すぐ南に橘樹郡小机村大字六角橋と西北が橘樹郡大綱村大字篠原でした。
現在の駅所在地は、東口駅前の高い丘が“源兵衛山”といわれる大地主の中村源兵衛さんの土地で、その一角でした。角川書店の『神奈川県地名大辞典』にも載っていない白楽は、おそらく中村源兵衛さんが手放した土地が町名「白楽」として現存しているのではないかと推測できます。
駅名「白楽」は、江戸時代東海道の宿場で栄えた神奈川宿の馬喰(ばくろう)がこの地に多く住んでいたことによるという説が濃厚のようです。馬喰のことを別名「伯楽」といい、馬の売り買いや弱った馬を治療する獣医のような仕事も兼務する人たち。この伯楽が転じて「白楽」といわれます。中国の詩人・白楽天とは、なんら関係がないようです。
大正15年(昭和元年)2月、東横線白楽駅に電車が通ると、この地域に大きな動きが出てきます。
まず、昭和3年に横浜市電の開通。横浜駅~保土ヶ谷橋~弘明寺を通り、尾上町~高島町をぐるっと回って六角橋停留所を終点とする循環路線です。市交通局出身の川俣勝一さんの話では「これだけ長い距離を乗って均一料金6銭でした。昭和48年に廃止になるまで、まだ均一料金20円でしたね。そのうえ、早朝7時までに乗ると早朝割引でもっと安くなるのですね。で、乗客とよくモメました~。7時を過ぎた、過ぎないで・・・」。 |
|

中国・唐の時代の詩人、白楽天とは関係ない白楽
|
|
白楽駅から200㍍足らずの六角橋停留所、この周囲に関東大震災と横浜大空襲で焼け出された商店が次々出店してきて、六角橋商店街ができ、買い物客が連日押し寄せ、通りを人を押し分けて歩く賑わいでした。
次が昭和5年、桜木町から六角橋の宮面ヶ丘に移転してきた横浜専門学校。昭和24年、「ヨコセン」で親しまれた校名が学制改革で「神奈川大学」に昇格、その後順次新学部を新設し、今や大学院まである総合大学に発展しています。箱根駅伝では「ジンダイ」の名で何度も優勝するなど知名度も急上昇、今やジンダイと白楽の街は切っても切れない太い絆で結ばれ、共存共栄の道を歩んでいます。 文・岩田忠利
|
|
|
◆白楽の東にあたり、東白楽
また一両、また一両、通勤客を乗せた東横線は休みなく走りつづけます。都心を結ぶ重要な〝パイプ〟でありながら、当東横線にも午後11時以降は無人駅になってしまうことがあります。
ここ、東白楽駅は、沿線中、比較的乗降客が少ないからでしょうか。駅員さんも、午前6時にならなければやってきません。
「キセルするヤツ、一日何人?」こんな思いを抱くのは、私だけでしょうか。
元住吉の車庫から桜木町に通じる現在の東横線は、以前は高島町が終点でした。
その間、昔の市電のように、駅のホームから次の駅までが見えるほどでした。
「白楽」の名称は、馬喰の意味から付けられたそうです。なお、当地に馬がたくさんいて、綱島街道と呼ばれるように、昔は幹道(かんどう)だったのです。
東白楽という町名はありませんが、駅名に「東白楽」とつけられたのは、白楽駅より東側にあたるからとのことです。
現在は道路をまたぎ、高架線になっていますが、以前は道路沿いに走っていました。
昔の東白楽地域は、「トラック」などとの呼び名もなく〝荷車自動車〟がたまに通るくらいで、30分間隔で走る市電は、原っぱを、田んぼをつっきり、ゴトゴトのんびり通りすぎてゆきました。
一刻を争い、ビリビリと神経を張り詰めての今日の社会と、当時とでは、どちらが人間らしい生き方ができるのでしょうか。
文・重田真介(白楽・自営業)
|

駅前商店街が無い東白楽駅 |
|
|

江戸時代の宿場町、反町 |
|
◆反物や農耕と関係があって、反町
江戸時代に宿場町として栄え横浜開港時の歴史を残す反町。駅周辺の商店街は、終戦後まもなく建てられたためか、古い商店が軒を並べている。
創業90十年という老舗のうなぎ屋「菊家」のおばあさんを訪ねた。当時、菊家の表井戸の隣に大門があり、そこから現在の反町公園のあたりまで遊郭があったそうだ。反町は、かつて色街でもあった。明治34年に反町郭ができ、大正に入ってからこの反町郭大通りは、露店でにぎわう、夜の盛り場だった。
反町という町名の由来は、いろいろな説があり、確かなことはわかっていない。昔、絹を、八王子方面から運んだ道で、反物が集まることから反町とした説。また、このあたりの田畑では、数年ごとに耕作を休んでいたため、「はずす」や「よける」の意味の反が町名になった、という説などがある。
この辺は、市電も国電も走っていて便利な所だった。横浜へは歩いたり市電に乗ったり。東京へ行く時は東横線を利用した、という。その後戦災で焼けた反町・三ッ沢地区は「菊家」の、亡き御主人が委員長になって、14~15年もかけて区画整理を行なったそうだ。以前、横浜市の市庁舎があった所に、反町公園がつくられた。
文・久保島(現姓・加賀)紀子(日吉・会社員)
|
|
◆歴史のある地名、横浜
絶えまなく行き交う群集-横浜駅。横浜の名は、すでに江戸時代からあった、という。現在の横浜のイメージとはほど遠く50年前ごろは何もない原っぱだ、というから驚きだ。
青木町・鈴木写真館の安藤瑛子さんは戦後、平沼高女に通学していた当時の横浜駅西口の模様をこう話す。
「戦後、焼け野原となった現在の西口は『裏口』と呼び、米軍に接収され石炭置き場や石炭ガラの山。夕方になると、街灯が一つポツンとつく淋しい所でした。父からは『追剥が出るから、あそこは通っていはいけないよ』とよく注意されてました」
横浜の復興は速かった。ここ数十年の間に、急速な変化をとげ、西口も東口も、まさに大都市横浜となった。古くからの家を探すにも、ビルに埋もれてしまい、ひと苦労・・・。 |
|
|
東横線が開業した大正15年(昭和元年)2月の頃は、丸子多摩川駅から神奈川駅(現在は廃駅となった)までの間、東京横浜電鉄最初の路線でこれを「神奈川線」と呼び、ここしか通っていなかった。が、横浜市中心部まで延ばす計画が実現し、東京・渋谷~横浜を結ぶ東横線が開通した。
大正12年9月、高島町にあった2代目・横浜駅は関東大震災で倒壊した。3代目・横浜駅が現在地開業したのは、昭和天皇御大典のお召列車通過に間に合わせるため完成させた、昭和3年のことだった。
見わたす限り〝ういういしさがただよう横浜〟だが、西口駅前には、ガス灯と古めかしいベンチがおかれている。横浜が日本の開港地として、西洋文化の発祥の地となったことを示している。ほかにも電信・ホテル・マッチ・理髪店など数えきれないほど多くの舶来文化が横浜の地に着き、それがやがて日本全国に行き渡った。
文・久保島(現姓・加賀)紀子(日吉・会社員)
|

1日の乗降客二百数十万人という横浜駅と西口広場
|
|
|
|
◆埋め立ての功績者・高島嘉右衛門をたたえ、高島町
以前は、川沿いを国電が走っていて、2代目・横浜駅があった場所。
海浜の埋め立てによってできた街である。その際に、神奈川から横浜に至る広大な海面埋め立て事業を果たした、故高島嘉右衛門。その名が現在の高島町として残されている。
東横線各駅を見ても、駅名からひとりの人間が浮かび上がることは少ない。それほど、高島嘉右衛門の功績はたいへんなものだったのだろう……。この広大な面積の埋め立てを1年たらずで完成させたという。技術や労働者の問題など、多くの障壁の中でひとつの街をつくり出した。
|
|

高島町駅ホームから見える三菱造船所も間もなく消える |
|
現在、高島町の街は、家並み、人並みとも、ひっそりとしている。大きな道路を行きかう車の群れだけが、駅を包みこんでしまっているようだ。駅の東には、道路を隔ててドックや倉庫など、労働の港が見える。けっしてきれいとはいえないが、そんな港が見たくなって道路を渡ろうと思ったが歩道橋ははるかに遠い。道路を渡りたくても車は途切れず、さみしい思いがこみあげた。
ここに住むひとたちは、新しく移ってこられたひとが多い。兵学校へ行くのに、当時の東横線に乗って行った、という人に会った。駅の辺りは何もなかった、という。震災で壊れた2代目・横浜駅のあと、東横線の高島駅は (国電横浜駅が今の地に移設開業するまで)横浜と呼ばれていた。その後、本横浜、そして現在の高島町という駅名に定着した。
文・久保島(現姓・加賀)紀子(日吉・会社員)
|
|
|
◆かつて桜木川があった、桜木町
「♪汽笛一声新橋を……」と歌われた日本最初の汽車が明治5年(1872年)に走った終着駅。桜木町の名は、この鉄道敷設の際に桜木川に面する鉄道柵外を埋立てて誕生した。駅前には鉄道発祥の地を記念した大きな碑が建っている。
それにもう一つ、小さな記念をみつけた・・・かわいい碑は現在の地下鉄の入り口の所にあり、小さな文字が刻んであった。「横浜駅長室の跡」と。こんな目立たない所にも、歴史の重みが感じられた。
桜木町駅で、海と逆の改札口を出ると、建ち並ぶ大きなビルが目にとびこみ、向こう側が海であることなど忘れてしまいそうだ。少し歩くと野毛山公園・掃部山公園・紅葉坂など、緑がいっぱいの場所がある。が、それとは対照的に、野毛の繁華街がある。戦災の焼け野原から横浜で最初に店ができ、栄えた繁華街だそうだ。細い路地に、たくさんの店がひしめきあっている。
今度は反対側に行ってみると、山下公園へと続く絵タイルの出発点がある。以前はこの桜木町が港への一番近い駅だった。こちら側にもビルが建ち並んでいる。しかし、歩いて大岡川にかかる弁天橋まで来ると、やはりここは港へ通じる街だったことを感じさせられる。弁天橋の下にはたくさんの小舟がびっしり、いわばここは、船の〝駐車場〟
思いがけない光景に、私の足は弁天橋の上で釘づけになった。なぜか、これらの船は、このままここから出て行かないのではないか・・・などとへンなことを考えた。これらの船は、港へ、海へと出て行っているのに・・・。
文・久保島(現姓・加賀)紀子(日吉・会社員)
|

日本最初の汽車が走った終着駅、桜木町駅 |
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
 |
駅名の由来③へ |
|