cc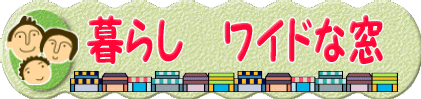 |
| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |
| 投稿:坂上武史(札幌市中央区在住) 編集:岩田忠利 NO.93 2014.7.07 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
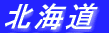 |
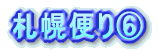 山紀行① クヮウンナイ 山紀行① クヮウンナイ |
|
| |
北海道も異常気象
関東は梅雨ですね。北海道は梅雨が無いはずですが、ここ数年は6月になると梅雨に似たどんよりとした天気が続くのが当たり前になってきているように思います。特に今年は、5月の下旬に関東を上回る夏日を記録したにもかかわらず、6月に入ってからは涼しいと言うよりは寒い日が続いて、記録的な連続雨日となってしまいました。
ゴールデンウィーク中でも網走沖に流氷が観測されておりましたが、5月下旬には30℃を超える猛暑となり、月が変わると再び寒くなって、体調の維持管理に苦労します。ひょっとしたら、網走をはじめとしたオホーツク沿岸では既に夏が終わってしまったかもしれないと思っていました。ところが、7月に入って再び暑くなり出してひとまず安心しております。
関東でも梅雨入り宣言が数日さかのぼる形で事後報告的になされることが少なくないと思いますが、今年の北海道の夏も「実は5月下旬が夏の盛りでした」なんてことになると子供たちにも可哀想です。
独身時代、山行の思い出
♪夏が来れば思い出す と言って思い出すのは尾瀬でしょうか。でも私の夏の思い出は、大雪山でよく登った沢だったりします。
今回は札幌にも横浜にも関係がないのですが、こんな時期でもあることから少し爽やかに大雪山を題材に書いていこうと思います。
昔、と言っても10年くらい前の近い昔、私は登山が趣味でしたので山の話です。
まだ独身で、休日は天気が悪くない限り通年で山に行っていました。年間の週末が大体50回くらいありますが、そのうち35回くらいは山で遊んでいたという放蕩ぶりでした。
金曜夜に仕事から帰ってくると、一週間分のワイシャツ類の洗濯を干してから、夜な夜な車を運転して登山口に向いました。深夜2時くらいに到着してから缶ビールを寝酒で呑んで車中泊をし、早朝5時には起床して6時前には登り始めるという、仕事より数倍ハードな週末を毎週のように送っていました。行く頻度の多さから装備に気を遣い、常に最新の物を揃え、ガソリン代や行動費を含めると相当な出費で、先記の「放蕩」が最も相応しい生活ぶりでした。
|
|
大雪山の概要
大雪山は、北海道のほぼ中央に位置し、北海道を代表する最も代表する山岳の一つといえます。しかし、大雪山という個別の山はなく、最高峰の旭岳をはじめとしたその周囲の高地に連なる山々の総称を表します。八ヶ岳のようなものですね。
火山活動により形成されており今でも旭岳と十勝岳は活火山で噴煙を上げています。隆起で形成された日高山脈と比べて新しいため氷食地形が発達しておらず、たおやかな山並みと雄大なお花畑が広がっており、周囲の原始性の高い自然を含め、神奈川県に匹敵する面積で日本最初の国立公園に指定されております。アイヌ呼称はヌタプカムウシュペで、「川がめぐる上の山」と言う意味(深田久弥「日本百名山」より)で、その名のとおり北海道の母なる川である石狩川や十勝川はこの山塊を源流としております。
「とうよこ沿線」の事務局、日吉にある慶応にちなんだ登山家「大島亮吉」が歩み、この世に北海道の山岳の原風景を広く紹介した「石狩岳より石狩川に沿うて」(山―研究と随想)は、大正9年7月21日~31日までの10日間にわたり大雪山を縦走した、約100年前に記された記録です。でも、現在でも色褪せない鮮明な描写に感銘を受け、石狩川の支流である忠別川の源流クヮウンナイを遡った時のことを振り返ってみたいと思います。
|

神奈川県と同じ広さの大雪山国立公園
白雲岳からトムラウシ(中)、十勝連峰(左奥)
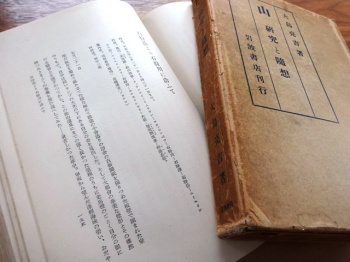
昭和5年発刊の大島亮吉「山 研究と随想」
今でも色褪せない文章が登行欲を高めます
|
|
|
|
クヮウンナイ
信じられないかもしれませんが入山口には、下の写真のような看板が建っています。これまでにも、クマ被害や増水による遭難、植物の盗掘など、不遇の客や招かれざる客が多かったことがうかがえます。何度読んでも少しドキッとするのですが、入山時の戒めにもなるもので、一応一通り読んでから入るのが常でした。
最初に一回高巻く所がある以外、坦々とした変哲もない河原をひたすら歩きます。ここを辛抱しないと後の美観にたどり着けません。しばらくは我慢です。(こうやって文章で書くと2、3行ですが、歩くと4時間強くらいです)
やがてF1(FALL1=1番目の滝)が魚止めの滝となって現れ、この上部から源頭にかけて大島亮吉が古今無双、唯一無二と絶賛した「瀧の瀬十三丁」が展開するのです。
|
|
瀧の瀬十三丁
イメージとしてはフラットに舗装されたアスファルトに苔を這わせ、苔に水がかぶるか、かぶらない程度にサラサラと水を流しているような道という感覚です。そこをヒタヒタと足を運んでいくのは何とも爽快な沢旅でした。といっても悠長に構えて転んだりしたら、ウォータースライダ-となって際限なく滑っていきそうです。要注意です。ちなみに、降雨で増水したら沢自体が排水溝のようになり命取りになります。
私も一回雨にやられて沢の中程で泊まったことがありました。その時は本州から沢登りが初めてというゲストを連れていたので、かなり気を遣いました。その時は翌朝が晴天で水が引いていたので源頭まで逃げるように登ったこともありました。(その後、再度夕方から次の日まで豪雨に見舞われ夏道を逃げ帰りましたが・・・)
話は戻って、先人が世に紹介した絶景「瀧の瀬十三丁」を、水遊びする気分で旅程を稼いでいきます。
早朝に先の看板を発つと、ちょうどこの辺りで正午になり、頭上にトップライトを浴びカンカンに火照った身体と足下の冷涼感が何とも言えず気持ちよいです。岩床を覆った蘚苔が絨毯のような感触で、この滑にフェルトの靴底が吸い付いていく心地よい感触を一歩一歩味わいながらゆるゆると登っていきます。日高山脈など緊張を強いられる沢登りが続いた後にデザート感覚で無性に登りたくなるやさしく美しい沢の一つでした。
許すならいつか流しソーメンをやろうと仲間内で冗談交じりに言っておりましたが、ついに叶うことはありませんでした。なんと言っても熊の生息圏、そこまで悠長には構えていられません。
|

降雨による増水時には沢水が濁る

滑滝が麺類を連想させる
|
|
|
|

デブリの上や合間を慎重に登ることも…

「瀧の瀬十三丁」とお花畑は小滝で結ばれる
|
|
|
源頭へ
初夏でも時期が早すぎてデブリに覆われていたり、時には錦秋の秋に、また時にはトムラウシの傍にあるヒサゴ沼で兄との待ち合わせのため、その時の背景などに応じて緩急自在に遡れる楽しく綺麗な沢でした。
約2キロにわたる滑の途中には、なだらかに落ちる滑滝が幾つかあって、柔らかい風情ながら「瀧の瀬」にアクセントを加えております。滑床の蘚苔に弾ける水泡と、軽く飛沫が浮かぶほどに足を蹴散らせて進む爽快感がこの沢の最も大きな魅力でしょうか。
入山後からF1に至る4時間余りの道程で熱しきった身体が、約1時間程度の滑の流れを歩くことで全身がクールダウンし、これから先に待っているお花畑への期待感が否応がなくとも高まっていきます。快適な滑がもっと続いて欲しい衝動と、早くお花畑に出たい衝動と、矛盾した二つの我が儘を抱きながら歩みを進めると、どんどん沢筋が細くなっていきます。小さな滝は水が滴る階段のごとく直登が可能です。いつの間にかに樹林限界を脱し、真夏でもエゾノリュウキンカ(=ヤチブキ)が咲き乱れる源頭に達します。
涼しげな「瀧の瀬十三丁」を終えてしまい少し残念ですが、これから先は沢登りではなく花見登山に変わってゆくのです。 (札幌便り(7)に続く)
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
 |
札幌便り(7) 山紀行②へ |
|