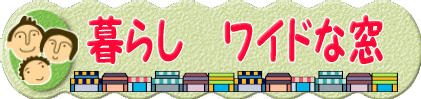|
ここはそんなに古く感じませんが、大きな規模を感じます。人工物の巨大構造物にはなぜか感動します。この日は年に一度の施設の公開日で、桜が満開でしたので花見も出来るのですが、連れて行った犬は入れて貰えませんでした。
給水池の貯水位置は、どうやら地上から15㍍くらい上にあると考えました。この施設の漏水が見える高さを考慮してそう思いました。
2014年1月に久しぶりに訪れてみたら、この給水所が解体工事中で、消えゆくものの儚さを感じながら撮影してきました。土木構造物には、独特のレトロ感があります。でも、この古さがたまらないですね。
|

和田堀ポンプ所4
2014年1月26日撮影:堤の上の建屋
|
|

和田堀給水所5
2014年1月26日撮影:裏側の公園から撮影
|
|
|