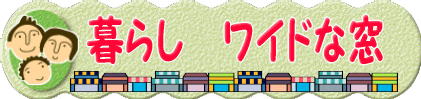|
この地下壕に続く道沿いに建つ学生寮(寄宿舎)を、日を改めて見学してきました。
こちらはまさに建て直しが進んでいるもので、今後はもう見ることも出来ないと思います。学生寮の建物は谷口吉郎氏が30歳の時に設計したものだと言います。1937年(昭和12年)に建てられたものだと資料には書いてありました。
全体写真はありませんが、学生寮は日吉の丘の上に3棟並んでいます。建物の間はゆとりを持って建てられており、どの棟屋も日差しが十分に入ってきます。見学させてもらった学生寮は最近リニューアルしたところで、住みやすそうな雰囲気の中にレトロな個所が随所に残っていました。
反面、他の棟は老朽化が進行しており、ベニア板の張られた開口部や千切れたカーテンが痛々しく感じられました。もちろん学生さんは住んでいません。躯体の老朽化はコンクリートの表面にも現れていて、爆裂(鉄筋の腐食により体積が膨張してコンクリート押し上げる現象)が随所に生じていました。
|
|
|

学生寮北寮。草むした中の学生寮
2012.2.8 撮影(以下同日撮影) |
|