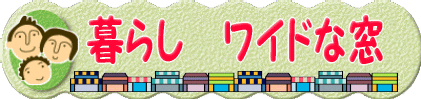| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژوچقپE•¶ڈWپFٹâ“cپ@’‰—کپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ |
|

‘هگ³‚V”Nپi1918پj‚VŒژپAگىچèژs’†Œ´‹و‹{“à’n‹و—Lژu‚جٹF‚³‚ٌ‚ج•xژm“oژRپBگ{‘–Œû‚ج•xژmگَٹشگ_ژذ‚إ
پ@’†‰›پA’·”¯‚ة’·‚¢Œû‚ذ‚°‚ج‚ذ‚ئ‚«‚ي–ع—§‚آگl‚ھپA•xژmگM‹آ‚جڈCŒ±ژز‚إ‹ك‹½‹كچف‚ة‚»‚ج–¼‚ھ’m‚ç‚ꂽŒ´پ@ڈئŒ¹‚³‚ٌپB’nŒ³‚إ‚ح‰®چ†پu‚خ‚ٌ‚خپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‹Œ‰ئ‚جگlپB
پ@چإŒم—ٌ‰E’[‚جگl‚ھچإژل”N‚ج”¨ƒP’JڈdگM‚³‚ٌپiچ¶ٹ¯گEگlپjپBژتگ^Œfچعژ‚ج•½گ¬12”NپA‚±‚جژتگ^‚ةژت‚邽‚¾ˆêگl‚²Œ’چف‚جگl‚إ–100چخ
پ@’ٌ‹ںپF“‡“cپ@ڈ¸‚³‚ٌپi‹{“àپjپ@پ@پ@پ@ژتگ^ڈWپw‚ي‚ھ’¬‚جگج‚ئچ،پx‘و2ٹھپuگىچè’†•”•ز‹y‚ر“–ƒTƒCƒgپuژتگ^‚ھŒê‚鉈گüپvŒfچع |
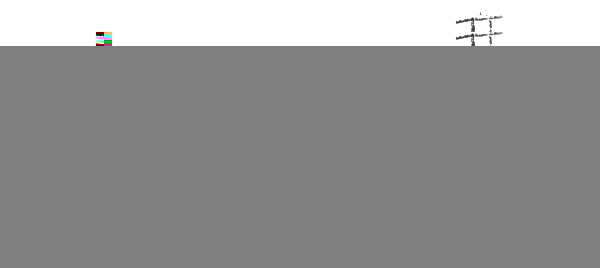
پ@پ@پ@پ@ژتگ^ڈم‚ج•xژm“oژRژز‚ج–¼‘Oپ@پ@ڈî•ٌ’ٌ‹ںپF“‡“cڈ¸‚³‚ٌپi‘½–€‹وگ›گه’Jپj
پ@ˆب‰؛‚ج–¼‘O‚حپA“‡“cڈ¸‚³‚ٌ‚ھ‘¶–½’†‚ج•ƒپE‹`‹v‚³‚ٌ‚©‚ç•·‚«پAڈ‘‚«‹L‚µ‚ؤ‚¨‚¢‚½‚à‚ج‚إ‚·پB
پ@چإ‘O—ٌ‰E‚©‚猴•؛ŒةپA‚Qگl‚¨‚¢‚ؤ“‡“cکZ‘ پAڈ¬ژR‹à‘¾کYپAŒ´’ه‘¢پAŒ´ڈي‹gپAˆêگl‚¨‚¢‚ؤژR–{چ²ژsپB‚»‚جڈم‚ج‚Q—ٌ–عپAچ¶‚©‚ç‘هŒF‹v‘¢پAگخˆن’·ژںکYپAŒ´Œ ŒـکYپAگخˆن‹`—YپB
پ@‚R—ٌ–ع‚ج‰E‚©‚çگخˆن‹I‘مژiپAچ•“cگVڈ•پAŒ´‹àŒـکYپA“‡“c”~‹gپAŒ´ڈئŒ¹پAگ´گ…ٹK‘ پAŒ´ŒH‹gپAگ´گ…•F‘¾کY
پ@چإŒم—ٌ‚جچ¶‚©‚çگ´گ…“`‘ پAژR–{‹vچىپAŒ´Œ“‘¢پA“‡“cŒ¹‘¾کYپAˆêگl‚¨‚¢‚ؤژR–{ŒـکY‹gپAŒ´•ںژںکYپAڈ¬ژRگَ‹gپA‰حŒ´‰F‘¾کYپA“‡“cڈ•ژںکYپA‹àژqگ³’jپA“‡“cنف‹gپAˆêگl‚¨‚¢‚ؤژR“c”~‹gپA‘هŒFŒ³ڈtپAŒ´چD‘ پA”¨ƒ–’JڈdگM‚جٹF‚³‚ٌ
|
|
|
|
پ@ژpŒ`‚ج”ü‚µ‚¢•xژmژR‚ھگ¢ٹEژ©‘RˆâژY‚إ‚ب‚پAگ¢ٹE•¶‰»ˆâژY“oک^‚ج——R
|
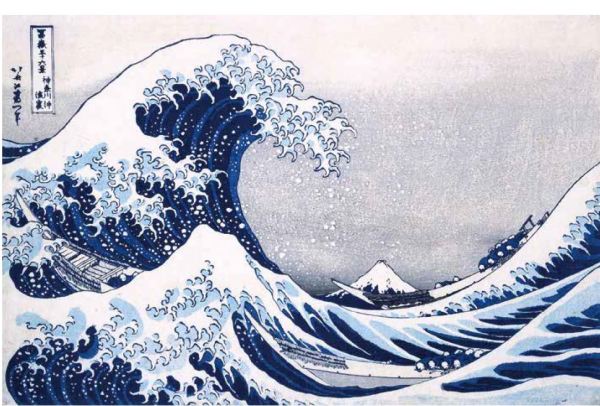
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•‚گ¢ٹGپ@ٹ‹ڈü–kچضچىپu•x›شژOڈ\کZŒiپvپiژR—œŒ§—§”ژ•¨ٹظڈٹ‘ پj
|
پ@“ْ–{چإچ‚•ô3776‡bپAژp‚©‚½‚؟‚ج”ü‚µ‚¢•xژmژR‚حگ¢ٹEˆâژY‚ة“oک^‚³‚ê‚é‚ب‚çپAپu“–‘RپAژ©‘RˆâژY‚¾‚낤پv‚ئژ„‚ح—\‘z‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚ئ‚±‚ë‚ھپA•½گ¬‚Q‚T”N‚UŒژپA‘و‚R‚V‰ٌگ¢ٹEˆâژYˆدˆُ‰ï‚ج”•\‚إ‚حپu•¶‰»ˆâژYپvپEپEپEپB—\‘z‚ح‘هƒnƒYƒŒ‚إ‚µ‚½پB
پ@Œأ—ˆ‚©‚ç•xژmژR‚حگ_ڈZ‚ـ‚¤ڈٹ‚ئگ’‚ك‚ç‚êپAژR’¸‚ض‚ج“oژR‚âژRک[‚ج—ى’n‚ض‚جڈ„—ç‚ً’ت‚¶‚ؤگ_•§‚ج—ى—ح‚ًگg‚ة‚آ‚¯‚é“ئ“ء‚ج•xژmگM‹آ‚ًˆç‚ٌ‚إ‚«‚ـ‚µ‚½پB‹ك—×ٹeŒ§ٹe’n‚ة•xژmژR‚ً–ح‚µ‚½پg‰½‰½•xژmپh‚ھ‘¢‚ç‚êپAڈZ–¯‚ج•xژmگM‹آ‚ھگ·‚ٌ‚إ‚µ‚½پB
پ@Œ|ڈp–ت‚إ‚à•xژmژR‚ً‘èچق‚ة‚µ‚½•‚گ¢ٹG‚ھٹ‹ڈü–kچض‚âˆہ“،چLڈd‚ç‚ة•`‚©‚êپAگ¢ٹE‚جŒ|ڈp‰ئ‚ة‘ه‚«‚ب‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚±‚جگM‹آ‚ج‘خڈغپAŒ|ڈp‚جŒ¹گٍ‚ئ‚µ‚ؤ‚ج•xژmژR‚حپAگ¢ٹE•¶‰»ˆâژY‚ئ‚µ‚ؤچ‚‚•]‰؟‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚µ‚½پB
|
|
|
|
|
ڈم‚جژتگ^‚ًŒ©‚½ژR—œŒ§•xژm‹g“cژs‚ج•û‚©‚çˆب‰؛‚جƒپپ[ƒ‹‚ھپEپEپE
پ@ |
پ@ٹâ“c’‰—کپ@—l
پ@‚ح‚¶‚ك‚ـ‚µ‚ؤپA“ث‘R‚جƒپپ[ƒ‹‚إژ¸—ç‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پBژR—œŒ§•xژm‹g“cژs‚جپu‚·‚»‚جکH‹½“yŒ¤‹†‰ïپv‚ئ‚¢‚¤‹½“yŒ¤‹†‰ï‚ةڈٹ‘®‚µپA•xژmگM‹آ‚جŒ¤‹†‚ً‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·ٹڈہ‚ئگ\‚µ‚ـ‚·پB
پ@“–’n‚ة‚حپAگىچèژs’†Œ´’n‹و‹{“àڈoگg‚جŒ´ڈئŒ¹ژپ‚ھ‘هگ³7”N1Œژپ`2Œژ‚ة‚©‚¯‚ؤپAگل’†•xژm“oژR‚ًچs‚¢پAژR’¸‚ة–ٌ1ƒ–ŒژٹشژRکU‚ً‚µ‚½ژ–‚ً‹L”O‚µ‚ؤŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽگخ”è‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAگخ”肨‚و‚رŒ´ژپ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا’m‚ç‚ê‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@Œ´ژپ‚ج‹ئگر‚ًŒمگ¢‚ة“`‚¦‚éˆ×‚ة‚ئŒ»چفپA’²چ¸Œ¤‹†‚ًچs‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA“–ژ‚ج’nŒ³گV•·‚ج‹Lژ–‚ئپA•xژm‹g“cژs‚ج“oژR“¹‰ˆ‚¢‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚錴ژپ‚جگل’†“oژR‚ج‹L”O”肾‚¯‚إژ‘—؟‚ھ–³‚پAژè‹l‚ـ‚è‚جڈَ‘ش‚إ‚µ‚½پB
پ@‚»‚ٌ‚بژ‚ةپAŒ´ژپ‚ج–¼‘O‚ًƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒg‚إŒںچُ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚±‚ëپAپwژتگ^‚ھŒê‚鉈گüNo16پ@•گ‘ ’†Œ´’n‹وپ@گl‚ج‰c‚ف‚ئڈîŒiپx‚ةŒfچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚錴ڈئŒ¹ژپ‚جژتگ^‚ة‚½‚ا‚è’…‚«‚ـ‚µ‚½پBپwژتگ^‚ھŒê‚鉈گüپx‚ة‚و‚é‚ئپAŒ´ژپ‚ح’nŒ³‚إ‚ح•xژmژR‚جڈCŒ±ژز‚ئ‚µ‚ؤ’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚ب‚ج‚إ‚·‚ھپAŒ´ژپ‚ج––هل‚ج•û‚âپAŒ´ژپ‚ة‚آ‚¢‚ؤڈع‚µ‚’m‚ء‚ؤ‚¢‚é•û‚ب‚اپA‚¢‚ç‚ء‚µ‚ل‚¢‚ـ‚µ‚½‚çپA‚²ڈذ‰î‚¢‚½‚¾‚¯‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پHپ@Œ´ژپ‚ةٹض‚·‚éڈî•ٌ‚إ‚µ‚½‚ç‚ا‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚إ‚à‚¢‚¢‚ج‚إ‹³‚¦‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚و‚낵‚‚¨ٹè‚¢‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پBپ@
پ@ژèژ‚؟‚جŒأٹG—tڈ‘‚ةŒ´ڈئŒ´ژپ‚جگل’†•xژm“oژR‚ً‹L”O‚µ‚ؤڈo‚³‚ꂽٹG—tڈ‘‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپA‰و‘œƒfپ[ƒ^‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إ‘—‚è‚ـ‚·پB‚g‚o‚إژg‚¦‚é‚و‚¤‚إ‚µ‚½‚炨ژg‚¢‰؛‚³‚¢پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚·‚»‚جکH‹½“yŒ¤‹†‰ïڈٹ‘®پ@•xژmژRچDژ–‰ئپ@ٹڈہپ@گi
|
|
|
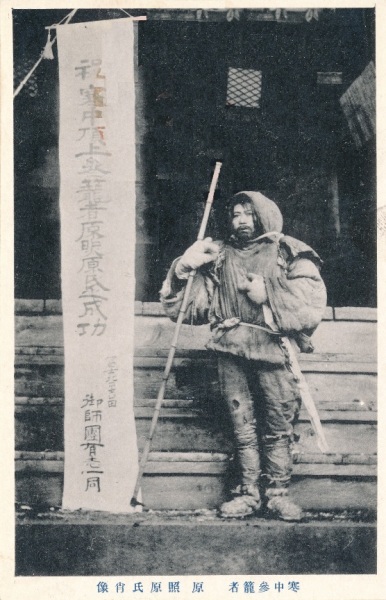
پ@پ@پ@ڈم‹Lٹڈہگi—l‚©‚ç‘،‚ç‚ꂽٹG—tڈ‘•،ژت‚جژتگ^
پuڈjٹ¦’†’¸ڈمژQâؤژزŒ´ڈئŒ´ژپ”Vگ¬Œ÷پv‚جگ‚‚ê–‹‰،‚ة—§‚آژp‚حپAگlٹش‚ًٹٌ‚¹‚آ‚¯‚ب‚¢‰كچ“‚بٹ¦’†‚ج•xژmژR’¸‚ة1ƒJŒژ‚à‚جٹشژRâؤ‚肵‚½‚»‚جŒƒ“¬‚ش‚è‚ً–³Œ¾‚إ•\Œ»‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پAچ،‚©‚ç98”N‘O‚جژتگ^‚إ‚·
|
|
|
|
پ@پ@–³ژ–‰؛ژR‚ً•ٌ‚¶‚éژR—œ“ْ“ْگV•·پi‘هگ³‚V”N‚QŒژ11“ْ•t‚¯پj
پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFٹڈہپ@گi‚³‚ٌپiژR—œŒ§•xژm‹g“cژsپj
|

پuگل’†“oژRژزپ@–³ژ–‰؛ژRپ@•Xگل’†‚ة‚R‚S“ْچrچsپv‚جŒ©ڈo‚µ‹Lژ–‚ئژتگ^‚ةپuگل’†•xژmژR’¸‚ةچrچs‚¹‚錴پ@ڈئŒ´ژپپv‚جƒLƒƒƒvƒVƒ‡ƒ“•t‚«‚إŒfچع
|
|
|
پ@پ@گV•·‹Lژ–‚جŒ»‘مŒê–َ
پ@پuگل’†“oژRژزپ@–³ژ–‰؛ژRپ@•Xگل’†‚ة‚R‚S“ْچrچsپv
پ@گوŒژ‚PŒژ‚U“ْ“ى“s—¯ŒS‹g“c‘؛‚و‚èگل’†•xژm“oژR‚ً‚µپA•Xگل‚جژR’¸‚ة‚R‚S“ْٹشچrچs‚ًˆ×‚µ‚½“Œ‹گ_“c‹و‰h’¬چc‘cژهگ_‹³‰ï’·پEŒ´ڈئŒ´ژپپi‚T1چخپj‚ح‚µ‚خ‚µ‚خگ¶ژ€•s–¾‚ً“`‚¦‚ç‚ꂽ‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‚QŒژ‚W“ْŒك‘O11ژ–³ژ–‹g“c‚ة‰؛ژR‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پ@گS”z‚µ‚½‘؛–¯
پ@‚±‚ê‚و‚èگوپA“oژRŒمپAŒ´ژپ‚حگ”‰ٌپA‰خŒُپi‚¢‚ي‚ن‚éپg‚½‚¢‚ـ‚آپh‚ج‚±‚ئپj‚إ–³ژ–‚جگMچ†‚ً”‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA‹ژ‚é‚T“ْŒكŒم‚Uژچ ژR’¸‚إ‰خŒُ‚ً”F‚ك‚½‚ـ‚ـ“VŒَ•s—ا‚ة‚ب‚èڈء‘§‚ًگâ‚؟‚ـ‚µ‚½پB‚V“ْپA‹g“c‘؛–¯‚ح‘و‚R‰ٌ‚جŒˆژ€‘à‚ً‘gگD‚µ“oژR‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھ‘O“ْ—ˆ‚جگدگل‚Qژعپi60.60‡aپjˆبڈم‚ة’B‚µپA“oژR‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚¸پA‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@Œ´ژپ‚ح‘O‹L‚ج‚ئ‚¨‚è‚W“ْŒك‘O‚P‚Pژ–³ژ–‰؛ژR‚µپA‚ـ‚¸گَٹشگ_ژذ‹«“à‚ةژp‚ًŒ»‚ي‚µ‚ـ‚µ‚½پBپiچ¶‰؛‚ة‘±‚پj
پ@ |
پ@گ”•S–¼‚ھڈW‚ـ‚ء‚½گ·‘ه‚بپuŒ´ژپٹ½Œ}‰ïپv
پ@Œ´ژپ‚ج–³ژ–‰؛ژR‚ً•·‚¢‚½‘؛–¯‚ج‹ءٹى‚حˆê•û‚ب‚炸پA’¼‚؟‚ةŒ´ژپٹ½Œ}‰ï‚ًٹJ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج‰ï‚جژQڈWژز‚حگ”•S–¼‚ة’B‚µپA‘O“c‘؛’·‚ھٹ½Œ}‚جژ«‚ًڈq‚×پAŒنژt’cپiپu‚¨‚µ‚¾‚ٌپv‚ئ‚حپAگ_ژذ‚ةڈٹ‘®‚·‚éگ_گE‚ج’c‘جپj‚©‚ç•\ڈ²ڈَ‚ئ‹L”O•i‚ً‘،‚èپAژR“àژ؛ژهپi‚³‚ٌ‚¾‚¢‚ق‚ë‚ت‚µپj‚©‚çگ´ژً‚P’M‚ً‘،’و‚µ‚»‚جکJ‚ً‚ث‚¬‚ç‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@Œ´ژپ‚حژR“àپi‚³‚ٌ‚¾‚¢پj‚ة‚¢‚邱‚ئ‚R‚S“ْٹش‚ة‹y‚رپAŒg‘ر‚µ‚½گH—ئ‚ح‚ي‚¸‚©‚ة‹¼”•²‚Qڈ،پE”~ٹ±‚R‚O—±پE’إ‘ù‚R‚OŒآ‚ة‰ك‚¬‚¸پB‚µ‚©‚µڈ‚µ‚à”وکJ‚ج•\ڈî‚àŒ©‚¹‚¸پAگ؛گF‚àڈيگlˆبڈم‚إژQڈW‚جگlپX‚ج‘O‚إژں‚ج‚و‚¤‚ةŒê‚è‚ـ‚µ‚½پB
پ@پuژ©•ھ‚ھ‚R”Nٹش•xژmژR’¸ژQâؤ‚ًŒˆˆس‚µ‚½‚ج‚حپAچDٹïگS‚©‚ç‚إ‚ح‚ب‚پA‚à‚ئ‚و‚è‹•‰hگS‚©‚ç‚إ‚à‚ب‚¢پB–¾ژ،45”N‚VŒژپAگو’éپi–¾ژ،“VچcپjŒن•s—لپi‚²‚س‚ê‚¢پj‚ج‚±‚ئ‚ھ‚ ‚èپAگQگH‚ً”p‚µپA“ٌڈd‹´”ب‚إŒن•½–ü‚ً‹F‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚»‚جچb”م‚à‚ب‚پEپEپEپiˆب‰؛—ھپjپB
|
|
پ@چcژ؛‚جˆہ‘ׂً‹F”O‚·‚錴ژپ‚ج”M•ظ‚ةگlپX‚حٹ´Œƒ‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپAژهچأژز‚حژپ‚ج”وکJ‚ً‹CŒ‚¢پAچu‰‰‚ج’†ژ~‚ًŒî‚¢پA–œچخ‚ًژOڈ¥‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پ@‰ˆ“¹‚àچ•ژR‚جگl
پ@Œ´ژپ‚ًŒنژtپE‹e“cگ•vژپ•û‚ض‘—‚铹’†پA‰ˆ“¹‚ةŒ´ژپ‚جژè‘«‚ةگG‚ê‚و‚¤‚ئ‚·‚éژز‚ھ‘½‚پA‰ˆ“¹‚حگlژR‚ً’z‚«‚ـ‚µ‚½پB‹e“c‰ئ“’…Œم‚àڈ‚µ‚à”وکJ‚ج‹C”z‚ح‚ب‚گl‚ًˆّ‚«‚ئ‚ك‚ؤ“oژR‚جŒoŒ±’k‚ًپEپEپEپB
پ@ˆمژt‚جŒ’چNگf’f‚حپEپE
پ@‚ب‚¨پA’r’Jˆمژt‚جگf’f‚ًژَ‚¯پA‚»‚جŒ‹‰ت‚حˆب‰؛‚ج‚ئ‚¨‚èپB
پ@“oژR‚جچغ‚ج‘جڈd‚Q‚Oٹر–وپi75kgپj‚إ‚µ‚½‚ھپA‚Rٹر‚R‚O‚O–وپi12.4kgپjŒ¸‚ء‚ؤ‚P‚Uٹر‚U‚V‚O–وپi–ٌ62.5kgپj‚إ‚µ‚½پB‰Eژè’†ژw‚ة‹حڈ‚ج“€ڈ‚ً•‰‚ء‚½‚¾‚¯‚إ‚µ‚½پBˆف‚ح‹ة‚ك‚ؤڈ¬‚³‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚»‚جکr—ح‚ًژژ‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپA‰Eژè‚ة‚R‚Pٹرپi116.25ƒLƒچƒOƒ‰ƒ€پjپAچ¶ژè‚ة‚Q‚Qٹرپi82.5ƒLƒچƒOƒ‰ƒ€پj‚ج•¨‚ًٹyپXژ‚؟ڈم‚°‚½‚ج‚إ‚µ‚½پB
پ@”畆‚ھڈ‚µچr‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حگ_Œo‚ھٹô•ھگٹژم‹C–،‚ئŒ©ژَ‚¯‚ç‚ê‚ـ‚·‚ھپA‚ظ‚©‚ةˆظڈي‚ح‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤پB
پ@ |
پ@‹A‹‚ً•ٌ‚¶‚é“ا”„گV•·پi‘هگ³‚V”N‚QŒژ13“ْچ†’©ٹ§پj
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFٹڈہپ@گi‚³‚ٌپiژR—œŒ§•xژm‹g“cژsپj
|
|

پu•xژmژRâؤ‚جچrچsژزپ@چً–é—IپX‹A‹پvپuڈoŒ}‚¦‚حچg‚؟‚ه‚¤‚؟‚ٌ‚ة–طŒگكپv‚جŒ©ڈo‚µ
|
|
|
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œ»‘مŒê–َ
پ@پu•xژmژRâؤ‚جچrچsژزپ@چً–é—IپX‹A‹پvپuڈoŒ}‚¦‚حچg‚؟‚ه‚¤‚؟‚ٌ‚ة–طŒگكپv
پ@ٹ¦’†•xژm“oژR‚ةگ¬Œ÷‚µ‚½چc‘cژهگ_‹³‚جچrچsژزپEŒ´ڈئŒ´ژپ‚حپA12“ْ–é‚Vژ–³ژ–‹‹´گV‰h’¬‚P’ڑ–ع‚ج–{•”‚ة‹A‚ء‚½پB
پ@ژپ‹A‹‚ج’m‚点‚ً’m‚ء‚½“¯‹³چu’†کA‚جگ”•Sگl‚حپAگ”ٹٌ‰®‹´Œِ‰€‚ةڈWچ‡‚µ‚ؤژپ‚ًŒ}‚¦پA‹L”Oژتگ^‚ًژB‚èپA’¼‚؟‚ةگ¨‘µ‚¢‚µ‚ؤگ”ڈ\Œآ‚ج–“”‚ًگو“ھ‚ةژè‚ةژè‚ةپuŒ´ڈئŒ¹–هگl‰½–^پv‚ئ‹L–¼‚µ‚½چg‚؟‚ه‚¤‚؟‚ٌ‚ًگU‚è‚©‚´‚µپA–طŒگك—E‚ـ‚µ‚–{•”‚ة‘—‚肱‚ٌ‚¾پB
پ@–{•”‘O‚حŒQڈO‚ھچ•ژRپA‚T‚Pچخ‚جژپ‚ھگل’†‚ج“ïچs‚ًژv‚¢‚â‚ء‚ؤ—ـ‚ً—¬‚·کVگl‚à‚¢‚½پB
پ@‚±‚جگ·‘ه‚بٹ½Œ}‚ة•ï‚ـ‚ꂽژپ‚حپA‚R‚O“ْٹش‚جژRâؤگ¶ٹˆ‚ةپg–H”¯چC–تپiگg‚¾‚µ‚ب‚ف‚ھˆ«‚پA‚ق‚³‹ê‚µ‚¢‚³‚ـپjپhپA‚ـ‚ئ‚ء‚½”’ˆك‚ح‘lگF‚ة•د‚ي‚èˆس‹CŒ¬چVپA‹àچ„ڈٌ‚ً“ث‚¢‚ؤ—IپX‚ئ•à‚قپB
پ@گ¢کbگl‚جکb‚إ‚حپAژپ‚حگوŒژ‚T“ْپA“Œ‹‰w‚ًڈo”پA‚U“ْ“oژRپA–{Œژ‚X“ْ‰؛ژR‚µپAچ،‰ٌ‚إ‘و‚S‰ٌ‚جچrچs‚إ‚ ‚é‚ھپAگلگ[‚چإ‚à‹êچs‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
|
|
|

ژR—œŒ§•xژm‹g“cژs‚ج•xژm“oژR“¹‰ˆ‚¢پAگٍگ…“üŒû‚ةŒڑ‚آپuگل’†ژRâؤ‹L”O”èپvپB‘هگ³10”N‚PŒژŒڑ—§
پ@”è•\–ت‚ةŒ´پ@ڈئŒ¹ژپ‚جگل’†“oژR‚جŒoˆـ‚ھڈ‘‚©‚êپAچإŒم‚ةپu“oژRƒmŒg‘رگH—؟•iƒn‹¼”•²“ٌڈ،”~ٹ±گ¶›IژOڈ\Œآƒmƒ~ƒiƒٹƒLپv
ˆبڈمƒn“–ژٹxک[گlƒmژہژ‹ƒZƒ‹ڈٹƒiƒٹپ@‘هگ³ڈ\”NˆêŒژپv‹LڈqپBپ@پ@ژB‰eپFٹڈہپ@گi‚³‚ٌپi•xژm‹g“cژsپj |
|
|

پ@پ@پ@پ@“¯‹L”O”è‚ج— –ت
پ@”’‚¢‚ج‚حژB‰eژزپEٹڈہ‚³‚ٌ‚ھچڈ•¶‚ھ“ا‚ك‚é‚و‚¤‚ة•ذŒI•²‚ً“h‚ء‚½‚à‚جپBŒڑ—§گ¢کbگl‚ھ–¼‚ًکA‚ثپAˆêٹp‚ةپuŒ´ژپگ¶’nپ@‹{“àگآ”N’cپvژ^ڈ•ژز‚ج–¼‘O‚à‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@پ@ژB‰eپFٹڈہپ@گi‚³‚ٌپi•xژm‹g“cژsپj
|
|
|

چً”N4Œژ3“ْپA‰ُگ°‚ج•xژmژR’¸
|
|
پ@پ@پ@‘z‘œ‚إ‚«‚ـ‚·‚©پAٹ¦’†‚جژR’¸‚ج‹Cڈغ‚ًپH
پ@ 3776‡b“ْ–{ˆê‚ج•xژm‚جچ‚—نپA‚»‚µ‚ؤژص‚é‚à‚ج‚ج‚ب‚¢“ئ—§•ُپEپEپEپB
پ@’n‹…‰·’g‰»‚إ‹C‰·‚حڈمڈ¸‚µ‚½‚ئ‚ح‚¢‚¦پA1Œژپ`2Œژ‚ج•½‹د‹C‰·ƒ}ƒCƒiƒX25پژ‘OŒمپB“ئ—§•ُ‚¾‚©‚ç•—“–‚½‚è‚ھ‹‚پA‚PŒژ‚ج•½‹د•—‘¬پc16.4‡bپA‚QŒژ‚ج•½‹د•—‘¬پc15.85‡bپB
پ@‚±‚ج‹•—‚ةگل‚ح”ٍ‚خ‚³‚êپAگپ‚«—‚ـ‚è‚ح•ت‚ئ‚µ‚ؤ•½‹د‚Pپ`‚Q‡b‚µ‚©گد‚à‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB
پ@“~‚ج•xژm‚إŒ°’ک‚ب‚ج‚ح‹Cˆ³‚ھ’ل‚‚ب‚邱‚ئ‚إ‚·پB”Nٹش‚Pˆت‚ھ‚PŒژ‚إ–ٌ626.33ƒwƒNƒgƒpƒXƒJƒ‹پihPaپjپA2ˆت‚ج‚QŒژ–ٌ626.33ƒwƒNƒgƒpƒXƒJƒ‹پihPaپjپB‹Cˆ³‚ھچ‚‚¢‚ئپAŒŒٹا‚حچׂ‚ب‚èپA“à‘ں‚حڈk‚قپBŒŒ‰tڈzٹآ‚ھˆ«‚—₦‚â‚·‚¢پB‹t‚ة‹Cˆ³‚ھ’ل‚¢‚ئپAŒŒٹا‚حٹg‚ھ‚è“à‘ں‚ح–c‚ç‚قپBŒŒٹاپA“à‘ںپA‹ط“÷‚ھ–c‚ç‚ك‚خ’ة‚ف‚ھڈo‚â‚·‚¢‚ج‚إ‚·پB•½گ¬18”N“x‚ج‰ن‚ھچ‘‚ج•½‹د‹Cˆ³‚حپA114hPaپBڈم‹L‚جگ”’l‚ج”¼•ھ‚‚ç‚¢‚µ‚©‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@ٹ¦’†‚ج•xژmژR’¸‚ح‹C‰·پA•—‘¬پA‹Cˆ³پA‚¢‚¸‚ê‚à•½’n‚جژ„‚½‚؟‚ج‘z‘œ‚ًگâ‚·‚éگ¢ٹE‚إ‚·پB‚»‚ٌ‚ب‰كچ“‚ب’†‚ةچ،‚©‚ç‚X‚W”N‘OپA‚PƒJŒژٹش‚à‹¼”•²‚Qڈ،‚ئ”~ٹ±پEگ¶›I30Œآ‚¾‚¯‚جگH—؟‚إپAڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚ة‘د‚¦پA‚µ‚ج‚¢‚إ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پEپEپEپB
|
پ@پ@پ@‹{“à‚ج—l‘ٹ‚حˆê•دپcپc
پ@•xژm‹g“cژs‚جٹڈہ—l‚©‚çƒپپ[ƒ‹‚ً‚¢‚½‚¾‚«پA‚³‚ء‚»‚—‚“ْپAژ„‚حگىچèژs’†Œ´‹و‚ج‹{“à’n‹و‚ض”ٍ‚ر‚ـ‚µ‚½پBژتگ^ڈW”چs‚جژوچق‚إ–K‚ê‚ؤˆب—ˆپA14”N‚ش‚è‚ج‹{“à‚ج’¬•ہ‚ف‚حگF‘N‚â‚©‚بٹإ”آ‚âمY—ي‚ب“X‚ئڈZ‘î‚ھ•ہ‚رپA‚·‚ء‚©‚è—l‘ٹ‚ً•د‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚ـ‚¸چإڈ‰‚ة–K‚ꂽ‚ج‚حپAچإڈم’i‚ج‘هگ³‚V”N‚جژتگ^’ٌ‹ںژزپE“‡“cڈ¸‚³‚ٌ‘îپBƒCƒ“ƒ^پ[ƒzƒ“‚إگq‚ث‚½‚çˆسٹO‚ب“ڑ‚¦‚إ‚µ‚½پBپu‚à‚¤پA‚±‚ج‰ئ‚ة‚ح‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB“ا”„ƒ‰ƒ“ƒh‚ج‚ظ‚¤‚ةˆّ‚ء‰z‚µ‚ـ‚µ‚½پvپB
پ@“–ژ‚ج’¬“à‰ï’·پE“‡“c–Lچى‰ئ‚ً–K‚ث‚é‚ئپu‚S”N‘O‚ة–S‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پv‚ج‚¨•شژ–پBپg‚ـ‚ٌ‚ھژ›پh‚إ—L–¼‚بڈيٹyژ›‚جڈZگEپE“yٹٍڈG—G‚³‚ٌ‚ة‚حپu‚ئ‚¤‚و‚±‰ˆگüپv‚ج‘nٹ§“–ژ‚©‚炲‹¦—ح‚¢‚½‚¾‚¢‚½‚ج‚إ–K–âپBڈZگE‚ح‚س‚½گج‚à‘O‚ة‘¼ٹEپA‘¼ڈٹ‚©‚çژل‚¢ڈZگE‚ھ’…”CپAگج‚ج‚±‚ئ‚حٹF–ع•ھ‚©‚ç‚ب‚¢‚ئ‚ج‚±‚ئپBپu‹{“àŒِ–¯ٹظ‚ب‚çپAŒأکV‚ج•ûپX‚ھڈW‚ـ‚é‚©‚çپA‚»‚؟‚ç‚ضچs‚ء‚ؤ•·‚¢‚ؤ‚ف‚½‚çپEپEپEپv‚ئ‚جچô‚ًژِ‚©‚èپA’تچsگl‚ةŒِ–¯ٹظ‚ج“¹ڈ‡‚ًگq‚ثپA‚و‚¤‚â‚’…‚«‚ـ‚µ‚½پB‚ھپAŒِ–¯ٹظ‚حƒJƒM‚ھٹ|‚©‚èپAٹا—گl•sچفپEپEپEپB
پ@‚ب‚ٌ‚جژûٹn‚à‚ب‚‹A‚é‚ي‚¯‚ة‚à‚¢‚©‚¸پA—ׂجپu“خڈبŒڑگفپv‚ئ‚¢‚¤ٹإ”آ‚جژ––±ڈٹ‚ة”ٍ‚رچ‚ف‚ـ‚µ‚½پB
•sژv‹c‚ب‚²‰ڈپA“خڈبŒڑگف‚جگeژq‚ئ‚ج‘ک‹ِ
پ@‚ب‚ٌ‚ئپA‚ـ‚ء‚½‚—\ٹْ‚µ‚ب‚¢ٹً‚µ‚¢•شژ–پEپEپEپB
پ@پuڈئŒ¹‚³‚ٌ‚حپA‚¤‚؟‚ج–{‰ئ‚إ‚·‚وپB‚¢‚ـ‚حپA‚¤‚؟‚ھڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ج•و‚ًژç‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·‚وپBڈع‚µ‚¢‚±‚ئ‚حگe•ƒ‚ھ’m‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚©‚çپAگe•ƒ‚ة‰ï‚ء‚ؤکb‚ً’®‚¢‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پvپB‚ئ‚رگEپE‚R‘م–ع‚جŒ´پ@گ³ˆê‚³‚ٌ‚ح‚±‚¤Œ¾‚ء‚ؤپAژ©‘î‚ضˆؤ“àپA‚Q‘م–ع‚جŒ´پ@”ة‹`‚³‚ٌپi87چخپj‚ًڈذ‰î‚‚¾‚³‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@‹L‰¯—ح‚à”²ŒQپA‚ئ‚ؤ‚à”ھڈ\‘م‚ة‚حŒ©‚¦‚ب‚¢گl‚إ‚µ‚½پB
پ@”ة‹`‚³‚ٌ‚حڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ئ“¯گ¢‘م‚جگlپA‘c•ƒپEŒ´پ@‰أڈ•‚³‚ٌ‚©‚ç•·‚¢‚ؤ‚¢‚½ڈئŒ¹‚³‚ٌ‚جƒGƒsƒ\پ[ƒh‚ًژںپXکb‚³‚êپA‰œ‚©‚çٹz“ü‚è‚جڈئŒ¹‚³‚ٌ‚جژتگ^‚ًژ‚ء‚ؤ—ˆ‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پ@ڈم‚جژتگ^‚©‚ç98”N‚جچخŒژ‚ھŒo‚؟پAŒ³‹C‚بڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ً’m‚éگl‚حŒ»چفˆêگl‚à‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAŒ´پ@”ة‹`‚³‚ٌ‚ة‚¨‰ï‚¢‚إ‚«‚½‚¨‰A‚إپAپgŒ¶‚جڈئŒ¹‚³‚ٌپh‚ھ‹{“à‚ھگ¶‚ٌ‚¾—ًژjڈم‚جژہچف‚جگl•¨‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
|
|
پ@پ@ڈCŒ±“¹‚ئڈCŒ±ژز
پ@ڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ج‚و‚¤‚ةژR‚ةâؤ‚ء‚ؤŒµ‚µ‚¢ڈCچs‚ً‚·‚邱‚ئ‚إŒه‚è‚ً“¾‚ؤپg’´ژ©‘R—حپh‚ًگg‚ة‚آ‚¯پAڈژ–¯‚ج‹~چد‚ً‚ك‚´‚·ڈ@‹³‚ًپuڈCŒ±“¹پv‚ئŒ¾‚¢‚ـ‚·پB‚±‚جڈCŒ±“¹‚جژہ‘Hژز‚ًپuڈCŒ±ژزپv‚ـ‚½‚حپuژR•ڑپv‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پB
پ@’´ژ©‘R—حپEپEپEژد‚¦‚铤‚ً‘fژè‚إ‘~‚«‰ٌ‚·
پ@’´ژ©‘R—ح‚ئ‚¢‚¦‚خپAڈمڈq‚جŒ´پ@”ة‹`‚³‚ٌ‚جکb‚إ‚حپA‘ه“ç‚إ‘ه“¤‚ًژد‚ؤگMژز‚ة‹ں‚·‚é‚ئ‚«پAژüˆح‚جگl‚½‚؟‚جگ§ژ~‚à•·‚©‚¸پAژد‚¦‚½‚¬‚é“ç‚ج’†‚ةژè‚ً“ü‚êپA“¤‚ً‘fژè‚إ‘~‚«‚ـ‚ي‚µپA‰خڈˆê‚آ‚µ‚ب‚ء‚©‚½‚»‚¤‚إ‚·پB
پ@–¾ژ،“Vچc‚ج•ِŒن“ْ—\Œ¾پA•sŒhچك‘ك•ك
پ@ژں‚جƒGƒsƒ\پ[ƒhپEپEپEپB‹ك‘م“ْ–{‚جژw“±ژز‚ئ‚µ‚ؤچ‘–¯‚©‚ç‹آ‚ھ‚ê‚ؤ‚¢‚½–¾ژ،“VچcپBڈئŒ¹‚³‚ٌ‚àپu–¾ژ،‘ه’éپv‚ئ‚¨Œؤ‚ر‚µچإ‚à‘¸Œh‚·‚é“ْ–{گl‚إ‚µ‚½پB‚»‚ج“Vچc‚ھ–¾ژ،45”NپAژ•a‚ج“œ”A•a‚ھˆ«‰»‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‰\‚ًژ¨‚ة‚µ‚½ڈئŒ¹‚³‚ٌپAچc‹ڈ‘OچLڈê‚إ—¼کr‚ة‰خ‚ً“_‚¯‚½‘¾‚¢ƒچپ[ƒ\ƒN‚ًˆê–{‚¸‚آ—§‚ؤپAˆêگS‚ة–¾ژ،“Vچc‚ج‰ٌ•œ‚ً‹Fٹ肵‚ـ‚µ‚½پB
پ@پ@چ•ژR‚جگlپX‚ھŒ©ژç‚é’†پAڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ح“ث”@پA‚»‚ج‹F‚è‚ًژ~‚ك‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپA‚ذ‚ئŒ¾پA™ê‚â‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚½پBپuژ„‚ج‹F‚è‚à‚ق‚ب‚µ‚پA–¾ژ،‘ه’é‚ح7Œژ29“ْ–é10ژپA‚²•ِŒن‚¹‚ç‚ê‚ـ‚·پvپB‚¨‚»‚ꑽ‚‚à‚²•ِŒن“ْژ‚ًƒYƒoƒٹ—\Œ¾‚µ‚½‚ج‚إ‚µ‚½پB
پ@ژو‚èٹھ‚–ىژں”n‚ح‘›‘RپEپEپEپB‚â‚ھ‚ؤ”ٍ‚ٌ‚إ‚«‚½Œxٹ¯‚ةڈئŒ¹‚³‚ٌ‚حپg•sŒhچكپh‚إ‘ك•ك‚³‚êپA—¯’uڈê‚ة“ü‚ê‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@‚»‚ج‚T“ْŒمپA–¾ژ،“Vچc‚ح“œ”A•a‚ة”A“إڈا‚ً•¹”پA‚آ‚¢‚ة–¾ژ،‚S‚T”N7Œژ29“ْ–é10ژ43•ھپA‚²•ِŒن‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB
پ@‹ء‚‚ׂ«‚±‚ئ‚ةپAڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ج—\Œ¾‚ا‚¨‚èپA‚»‚ج“ْژ‚ھƒsƒ^ƒٹ“–‚½‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚½پBŒِژ®‚ج‚²•ِŒن“ْ‚ح–¾ژ،45”N7Œژ30“ْ‚إ‚·‚ھپAچc‘¾ژqپE‰أگmگe‰¤پi‘هگ³“Vچcپj‚جگV’é‚ة‚ب‚ç‚ê‚é‹Vژ®‚ج“ْ’ِ‚©‚瑤‹ك‚ج‹¦‹c‚جŒ‹‰تپA‚Qژٹش’x‚点—‚“ْ‚ج‚R‚O“ْ‚ة•دچX‚µ‚½‚ج‚إ‚·پB
پ@‚±‚جژ–ژہ‚ً’m‚ء‚½Œxژ@ڈگ‚حپAڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ً‚T”‘‚U“ْ‚ج—¯’u‚إ–³چك•ْ–ئ‚ئ‚µ‚½‚ج‚إ‚µ‚½پB
|
|
|
•ھ‰ئ‚جŒ´پ@”ة‹`‰ئ‚ة‚ ‚ء‚½ڈئŒ¹‚³‚ٌ‚جژتگ^‚Q–‡
|
|

‹ك‹½‹كچف‚جگlپX‚ج•a‹CپEگV’zپEŒ‹چ¥‚ب‚اگ¶ٹˆ‚ج”Y‚ف‚â‘ٹ’k‚²‚ئ‚ةگeگط‚ة‰‚¦‚éگ_“¹چc‘cژهگ_‹³‚جٹJ‘cپB
پ@Œ»‘م‚ج‚و‚¤‚ب—L—؟‚جگ…“¹‚ج‚ب‚¢گجپA‰ئ‚ًŒڑ‚ؤ‚éڈêچ‡پA‚ـ‚¸‚ا‚±‚ةˆنŒث‚ًŒ@‚é‚©‚ھ‘ه–â‘èپB‚»‚جگ…–¬‚ھ’n‰؛‚ج‚ا‚±‚ة‘–‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©پA‚»‚جˆت’u‚ئڈêڈٹ‚ًڈئŒ¹‚³‚ٌ‚حƒsƒ^ƒٹ‚ئ“–‚ؤ‚é‚ج‚إپAگV‹ڈŒڑ’z‚جژ{ژه‚ھژںپX–K‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤پB |
|
پ@پB
|

چ¶چک‚ج‘ر“پ‚ح‹{“à’،‚©‚ç‹–‰آ‚³‚ꂽ“پ
پ@”_‰ئ‚جگlپX‚ج• ’ةپEŒ¨‚±‚èپEچک’ة‚ب‚اٹ³•”‚ة‘ر“پ‚ً“–‚ؤ‚é‚ئپA‚â‚ھ‚ؤ’ة‚ف‚ھکa‚炬پAگ”“ْŒم‚ة‚حژ،‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤•sژv‹c‚ب“پ‚إ‚µ‚½
|
|
|
پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈئŒ¹‚³‚ٌ‚ن‚©‚è‚جڈêڈٹ
|