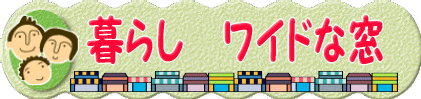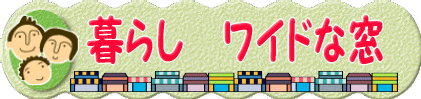|
娘夫婦の墓参
今年の彼岸は塩谷寺(港北区高田町)に向かう高田保育園のスモモが、空の青さと溶け合ってはっとするような美しさでした。先日は、はるばる大阪から夫婦そろっての墓参ありがとうございました。
いままではパパが墓石に何度も何度も水を注ぐのを不思議そうに眺めていた2人でしたが、今回はそろってたっぷりと水を注いでくれましたね。
きょうは栗原家の墓誌について触れたいとおもいます。骨壺のない3柱の仏様のことを香理にしっかり伝えておきたくなったからです。
殉国院修範釼正居士 昭和19年6月26日 俗名 修蔵 35歳
法名 釋勝浄童子 昭和19年8月1日 俗名 勝 2歳
法名 釋輝南信士 昭和19年8月24日 俗名 輝夫 5歳
浄修院都月妙鏡信女 昭和60年12月3日 俗名 都 71歳
3人の最期
昭和19年夏、パパの父(香理の祖父)と2人の幼い弟(同じく伯父)が相次いで亡くなりました。南の楽園といわれたサイパン島で幸せだった栗原一家6人が突然戦禍に見舞われたのは、昭和19年6月11日のことでした。パパが9歳のときです。
まず近くの洞窟に避難しました。が、まもなく米軍が上陸し北への逃避行を余儀なくされました。夜陰にまぎれてジャングルの中をチャッチャ方面に向かいました。あたりが昼のように明るくなることがあります。照明弾です。続いて容赦ない艦砲射撃が浴びせられます。一度は至近距離で砲弾が炸裂し、危うく命を落とすところでした。ジャングルの巨木によって救われましたが、パパの聴神経はやられてしまいました。(以来難聴です)。歩いては伏せ、伏せては歩きの行程は難渋を極めました。父の見事な統率により無事チャッチャに到着。再び洞窟での生活が始まりました。 |

結婚式当日の香理さんと父(著者) |
|
|
|
約半月の間一家が最も苦しんだのは、飢えと渇きでした。父は水と食料を調達するために夜明けとともに洞窟を出ていきます。が、ほとんど手にはいらず、わずかばかりの水をみんなで回し飲みできる日は稀でした。輝夫が水筒を抱え込んで手放さないでいると母(香理の祖母)は、こわい顔で奪うようにして次の手に渡します。もっと悲惨なのは勝です。栄養不足で出なくなった母親の乳房を必死に求めるのです。
6月26日、父が洞窟を出た後、米兵に発見されました。そのとき2発の銃声を聞きました。(一家の運命を大きく変えた真に呪わしい銃声であったことに気付いたのはずっと後のことです)。ジープの箱車で東海岸から西海岸のススペ民間捕虜収容所まで運ばれ、1年半の抑留生活を送りました。 |
その間8月1日と同月24日、勝と輝夫が相次いで亡くなりました。栄養失調でした。とうとう飢えと渇きから解放されることもなく……。ショベルカーとダンプカーで土木工事のように無造作に葬られた共同墓地と称する広場には色とりどりの百日草が咲き乱れているだけでした.
戦争が終わった昭和21年の冬、浦賀の土を踏んだのは母と名古屋の弟(利夫)とパパの3人だけで、父と幼い2人の弟は島の土となってしまいました。弟たちの死は確認していますが、父の死に立ち会った者は誰もいません。が、6月26日米兵に発見される前に耳にした2発の銃声を根拠に今では父の死を受け入れています。
|
|
|
軍服姿の父
水・食料の調達のためハグマン半島のジャングルを行動中の父も、遠目には日本兵と見紛うような国防色の上下にゲートル巻き、戦闘帽……と、まさに国防色一色でした。民間人は保護、日本兵は徹底的に殲滅というのが侵攻にあたっての米側の方針だったのですが、そのときの米兵たちの目には父修蔵が憎むべき日本兵と映ったのではないでしょうか。
じつは、太平洋戦争に先立つ昭和15年(1940)に「大日本帝国国民服令」が制定され、軍民ともに「国防色」一色となっていたのです。これは戦争に向けて次々に制定された法令のほんの一例に過ぎません。
戦争の悲惨さ・愚かさを伝える活動を
昨年12月、安倍政権のもとで「特定秘密保護法」が十分審議を尽くすことなく成立しました。戦前・戦中の「治安維持法」に重なってみえました。再び自由にものが言えなくなるのではないか……と心配です。「集団的自衛権」や「国防軍を保持する」などの議論は今後どうなっていくのでしょうか。
「父はよく『今の政治家は戦争を知らない』と言っていた。歴史の教訓に思いを致し、時々の潮流に流され安直な判断をしないよう、そして自立した真の平和国家として歩むことを願っていた」と、後藤田正晴元副総理は語っていたと聞きます。
子供ながらも戦争体験のあるパパは、今の政権が「いつか来た道」を再び暴走することがないよう、一人でも多くの方々に戦争の悲惨さ、愚かさを伝えていきたいと思っています。
今年の夏は、父や2人の弟が70回目の祥月命日を迎えます。供養のためでもあります。
|
|