�����M�͎�͎�
�R���J�i���j�搶 |
|
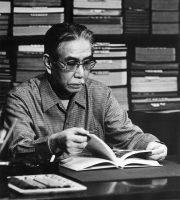
���R��̎���� |
|
|
���a63�N�Ə��Ζʂ̍��A�������J�҂̎�܂��ꂽ���ゾ���� |
|
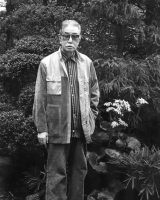
������̒�� |
|
|
|

��19����W��i�i1987�N�j
���U��x���W����������Ƃ��Ȃ��R�搶�́u�����̋C�ɓ���Ȃ���i�͔j���Ď̂ĂĎ��ɂ����v�Ƌ��Ă��� |
|
|
|
�@
�@�u�E�`�̏��X�X�ɓV�c�É��i�H�j���Z��ł���v
1987�N�i���a62�N�j�̏H�A���Ƌ`��͑�41���́u���X�́E���R����W�v���o�����߁A��䒬���̓��X�͂Ɣ��R��̊X������Ă����B�Ƃ��ɓ��������łȂ��A��䒬�������̊X�Ȃ̂ŁA�w�Ƃ��悱�����x�͒n��̐l�����ɓ���݂��Ȃ��A��ނ��L���W�߂���q���Ă����B���̕��A�����X��l�������x���K�ˁA�M�ӂƐ��ӂ������ق����@�͂Ȃ������B
�@�@���R�䏤�X�X�̒��ɂ��鏰�������K�˂��Ƃ��̂��Ƃ������B��l�����ɂ���Ȉꌾ���Ί�Řb�����B
�@�u�E�`�̏��X�X�̌����ɂ́g�V�c�É��h���Z��ł����v�B
�@�@�悭�u���A���{�����E�̒��_�ɂ�������ŁA�Z�������c�J�擙�X�͂Ƃ������Ƃ��珑���E�ł́g���X�͓V�c�h�ƌĂԂ̂��������B���}��`���Ă��炢�A�����������̑��ŖK�˂邱�Ƃɂ����B�ʂ����Ă��̓V�c�É��Ɂg�y���h�ł��邩�E�E�E�B
�@��э��݂̏��ΖʂȂ̂ɁA����100���̒�����
�@�Â��ȏZ��X�̍L�߂̒ʂ肩�猺��܂�20�b�قǂ́A�����鏬���̊X��������Ƃ������B�\�D�u�R���J�i���j�v���|�����Ă����B�p�������l�炵�������ɘb���ƁA���ɂ�����炵������l�Ɍ������đ傫�Ȑ��Łu���Ȃ��`�A���q�l�ł���`�I�v�B�Ԃ��Ă������t���u�p�������`�I�I�v�B
�@�ߏ����ɕ�������悤�ȑ吺���B��̎����ł����Ă����̂��A����^�I���Ő@���@���A���ꂽ�B���g�Ŋ����̂����A�܂��ɓV�c�ɂӂ��킵���ј\�̂��镗�e�A���̐l���g���X�͓V�c�h�A�R���J�搶�������B
�@�s�ӂɖK�˂����Ƌ`�ꂪ���k���Ă���ƁA�R�搶�͋��Ԃ̂ق��������ē{�����B�u���`���A���������`�I�v�B���Ԃɒʂ���A�w�Ƃ��悱�����x�̃o�b�N�i���o�[������������������Ɛ搶�͔M�S�Ɍ������Ă���ꂽ�B�P���Ԃقǘb���Ă���ƁA�R�搶�̌�����ӊO�Ȍ��t����яo�����B
�@�@�u�����́A�G�����I�@����ȃ^�C�w���Ȃ��Ƃ𑱂��Ă���Ƃ́A�������Ȃ��`�B���ꂩ�烏�V�ɂł��邱�Ƃ���������A���͂����B�Ƃ肠�������̐V�����疈��100���A���V�̉Ƃ܂œ͂��Ă��ꋋ���I�v�B
�@���Ζʂ̐R�搶����A�܂�������Ȋ��������t������������Ƃ́H�I�B
�@����100���������Ƃ����搶�̑������ɋ��������A����ɂ��Ă��A����Ȃɑ�ʂ̎G�����ǂ̂悤�ɏ����������Ȃ̂��낤���A�搶�̂��̂ق����S�z�������B���ƂŐV�������͂������Ƃ��A�����̎d�������������ƁA�R�搶�́u������͎R�قǂ����B�S�z����ȁI�v�B
�@�T���g���[�ւ̐��E���B�u���{�̏���100�l�W�v
�@�����Q�N�̂P���A���̃T���g���[�������c����d�b���������B
�@�u�M�c�̂�_�ސ쌧���̐V���Ђƃe���r�ǂ��T���g���[�n�敶���܌��Ƃ��Đ��E���Ă��܂����B�W�҂̐��E����Y���ď��ނ��o���Ă��������v�������B�R�搶�ɐ��E�������肢����ƁA�ȉ��̂悤�ȕ���Ԃ��Ă����������B
�@������̎G������ɂ����ҏW�҂��ˑR�킪�Ƃ�K�˂��̂́A���N�̂��Ƃ������B�w�Ƃ��悱�����x�ƌ�������A�������}�̂o�q�G�����Ǝv�����B�������A�u���Ή����Z�����]�ɂ𗘗p���č���Ă�����̂������ŁA���e�͈ӊO�ɏ[�����Ă���A�����Z���̃��A���Ȑ����`�ʂ����͓I�ł������B
�@�n���������玑���B���邽�߂ɍL�������߂邱�Ƃɋ�J��������łȂ��A��ނ̂��߂ɍŊ��w�����܂Ȃ��������A����ɕҏW�A�z�{�Ȃǒ������Ȃ������͕����Ȃ��̂ł͂Ȃ������悤���B�����[���I�ȏ����ȏ����G���s���Ă��邪�A�ƂĂ�����Ɣ�ו��ɂȂ�Ȃ����炢�A�y�Ȃ悤�ȋC�������B�i�ȉ����j��
�@�搶����͂���ȉߕ��Ȃ��J�߂̌��t�Ղ��邾���łȂ��A�R�搶�̍�i���W������鏑���W���ҏ�𑗂��Ă�����������A��ނ��A�ʼn������Ă����������肵���B
�@�Ȃ��ł���쏼�≮�ł́u���{�̏���100�l�W�v�ł͎������E�����[���E�I�єV�E�������^�ȂǓ��{�̗��j���99���̖��M�Ƃ̍�i�ƕ���ŁA�R���J�搶�̍�i���W������Ă����B�搶����������B��̌��㏑�Ƃ������B�搶�̈̑傳�Ɛ^���͌v��m��Ȃ����̂��Ǝ��������̂������B
�@���S���̉�����ƊԈႦ���受�D�̓d�b
�@56���̎��R���u���W�̂Ƃ��������B��l�̌��C�̂��������̐��œd�b���|�����Ă����B
�@�u��c����ł����H�@���R���u���W�������ł��ˁ`�H�v�B��l�ɁA���͈��鏗���̐���A�z�����B
�@�u���`�A���炭�I�@��i���w�O�̔��S������̉�����ł����ˁ`�H�v�Ɖ������̂������B
�@�ƁA�d�b�̌������̏����͋}�Ƀg�[���𗎂Ƃ��āu�����A���͐R���J�搶�̂��Љ�œd�b���Ă���r���~�q�ł��v�B
�@���`���A�g�e���r�h���}�̏����h�ŌN�Ղ��Ă������̒r���~�q�Ƃ́H�I�@�܂����受�D�A�r���~�q�����ڎ��ɓd�b�������Ȃ�Ė��ɂ��z���ł��Ȃ������B���̏�ŕ��g�ᓪ�Ɏӂ�A�Ȃ�Ƃ���������K�˂�����ĉ��Ƃ����̏�͎��܂����̂������B
�@���������A�R�搶���g���炤�������Ă����b�����̌�Ŏv���o�����̂������B�R�搶�̎Ⴂ���A�搶�͎���ŏ����m���J���Ă��������A�����ɒʂ��Ă����{���E����Ƃ������̎q�̈�ۂ����ɂ����b�����B�u���̒r���~�q�͍����Ⴀ�A�o���o���̏��D�����ǁA���ƂȂ����ĉ������l�`����݂����Ȏq��������v�B
�@�u���V�����̕�ɔ蕶�������Ă����悤�I�v
�@���{�|�p�@����ŁA�������J�҂ł���R���J�搶�B���̂悤�Ȉ̑�Ȑ搶�ɉ��ʂ��Ȃ��A�����ȎG�������肢���Ă��������Ƃ����l�Ԃ́A�Ȃ�Ɩʂ̔�̌����l�Ԃ������̂��낤�H�@��L�̖���100���̂������グ�A41������A�ڂ̃^�C�g�����e�u�S�l���l�B�v�̏��⎏�ʂ֊�e�̂��肢����10���N�L�O�p�[�e�B�[�ւ̏o�Ȉ˗��Ȃǂ̂��肢�܂ŁA�����u����A������v�̐搶�̂����t�ɊÂ��A�{���ɂ��낢��Ƃ����b���܂ɂȂ����B
�@�搶��Ɏf�����܁A����Ȃ��Ƃ��B�`�����S���Ȃ�A��n�����b��������A�u���V�����̕�ɔ蕶�������Ă����悤�I�v�ƐR�搶���{�l��������������B���̐�����A�d�b�Łu��c����A�ł�����`�A���ɗ��Ă��`�I�v�B�搶�̗����t���̗��h�ȋ˂̔��A���̒��ɒ����P���[�g���قǂ̘a���ɗY�ӁA舒B�Ȋ��|���얳����ɕ����E�E�E�B
�@�R�搶�̕���������͍j����̒����������ɂ���B�����Ɏ��ƈꏏ�Ɂw�Ƃ��悱�����x�S��74���܂Ōg������`��E��ؑP�q�������Ă���B�R�搶����̔蕶�������ꂽ�̂́A���ꂪ�ŏ��ōŌ�Ƃ������ƂŁA����q��R���J�M��҂̕��X�����̑�{�����Ɏ��X������悤���B
�@���L�̂Ƃ���A16�N�O�ɉi�����ꂽ�搶�����A���̐搶�̓�������ȂƂ���ɂ܂ŋy��ł���Ƃ́A�܂������̋����ł���B
�@���a�|�����̏��ƁA�R���J�搶�͏��a41�N�Ɂu���o�̈���v�Ō|�p�@�܂���܂����{�|�p�@����ɁB⽏��i�Ă�j�A�ꏑ�����ƂɓƎ��̕\���l�����m�������Ƃ��ď��a63�N�������J��܂��������J�҂ɁB�哌������w�����B�����S�N�A�����M�͎�́B���̗��N�A�����T�N�Q��13�������B���N80�B
|

