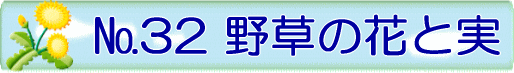
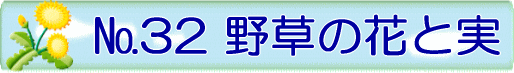
| 08.秋から冬に咲く美しく光沢のある黄色い花、コバノセンナ(小葉のセンナ) | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉本町6丁目 民家前の沿道 | |||||
| 科.属など | マメ科カワラケツメイ(河原決明)属 薬用植物 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.10.05 | ||||
| 20.道端や庭先によく咲いている、ビヨウヤナギ(美容柳)の花 | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区箕輪町 民家の庭先 | |||||
| 科.属など | オトギリソウ科オトギリソウ属 半落葉低木 | ||||||
| 見どころ | 「キンシバイ」と同じ仲間の花木です。高さ1〜1.5メートルほど。落葉低木。葉の形がヤナギに似ているので「ビヨウヤナギ」と言われていますが、ヤナギの仲間ではないそうです。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | |||||
2012.6.6〜 掲載20種
| 11.這うように広がっていきます、マツバボタン(松葉牡丹) | |||||||
|
所在地 | 川崎市中原区新城4丁目 江川せせらぎ遊歩道 | |||||
| 科.属など | スベリヒユ科スベリヒユ属 1年草 | ||||||
| 見どころ | |||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2012.8.16 | ||||
| 12.黄色の実の種皮と赤い実の対比が美しい! ツルウメモドキ(蔓梅擬)の実と花 | |||||||||
|
所在地 | 神奈川県箱根町仙石原817 箱根湿生花園内 | |||||||
| 科.属など | ニシキギ科ツルウメモドキ属、雌雄異株でつる性樹木 | ||||||||
| 見どころ |
|
||||||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.10.14 | ||||||
| 04.雄しべが赤いのが雄花、雌しべが緑色をしているのが雌花、 サネカズラ(実葛)の花と実 | |||||||
|
所在地 | 東京都立川市緑町3173 国営昭和記念公園 「みんなの原っぱ」南東トイレの生垣 | |||||
| 科.属など | マツブサ科サネカズラ属 常緑つる性木本 | ||||||
| 見どころ | どうしても撮影したくて開花するのをじっと待っていました。開花し始めたと聞いたので猛暑の中行ってきました。想像していた物より小さくて、葉に隠れるようにひっそりと咲いていました。その花が、目的でなかったら、見落としていたかもしれません。雄雌異株、または同株で、まれに両性花もあるそうです。 8〜9月に薄黄白色の花がやや下向きに咲き、雄花は咲いてすぐに落ちてしまうそうです。雄花は何輪も咲いていましたが、雌花は、ようやく1輪だけ見つけることができました。雌しべが緑色で、緑の粒粒が実になるのだと想像できます。10〜11月に艶やかな赤い実が集まった球になり垂れ下がります。すでに小さな青い実になって垂れ下がっているのもありました。
|
||||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.08.16 | ||||
| 15.色違いのエンジェル・トランペットの花とその秘話 | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区下田町5丁目 マンションの庭先 | |||||
| 科.属など | ナス科キダチチョウセンアサガオ属 落葉低木 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||
| 撮影者 | 池田はるみ | 撮影日 | |||||
| 01.艶やかな赤い色、イクソラ・コッキニア | |||||||
|
所在地 | 東京都江東区夢の島 3-2 夢の島熱帯植物館 | |||||
| 科.属など | アケネ科サンタンカ属 常緑低木 | ||||||
| 見どころ | インド原産の小低木で、高さ1メートル以下でよく分枝します。葉は小さく光沢があって美しい。花は小さいですが、枝先にかたまって咲きます。江戸中期に渡来しました。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.10.19 | ||||
| 07.蝶の形をしたシラハギ(白萩)の花 | |||||||
|
所在地 | 東京都世田谷区上野毛3-9-25 五島美術館正門入り口 | |||||
| 科.属など | マメ科ハギ属 落葉低木 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.09.29 | ||||
| 18.ワシントン条約で保護される貴重な植物、トゲオニソテツ(刺鬼蘇鉄)の花 | |||||||
|
所在地 | つくば市天久保4-1-1 筑波実験植物園内 | |||||
| 科.属など | ソテツ科オニソテツ属 | ||||||
| 見どころ | 原産地は南アフリカで、半低木です。高さ60センチ、葉は羽状に分かれ、葉の各羽片の先端には2個から4個の鋭い刺があり「トゲオニソテツ」と呼ばれています。花はオレンジ色で多数が集まって長さ30センチにもなる楕円球の花序をつくります。迫力を感じます。 「ワシントン条約で保護される貴重な植物」です。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.11.02 | ||||
| 19.住宅街で最近良く見かける花、タイワンレンギョウ(台湾連翹) | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉2丁目 民家のフェンス | |||||
| 科.属など | クマツヅラ科ハリマツリ属 常緑性低木 | ||||||
| 見どころ | 紫の可憐の花が垂れ下がっているフェンスや生垣を最近よく見かけます。花期が5月〜10月と長く咲くこと、挿し木で簡単に増やせること、乾燥に強いこと、3拍子揃った長所から道路沿いの低木として植えられているようです。 | ||||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | |||||
| 09.繊細な感じの花 ミヤマウグイスカグラ(深山鶯神楽)の花 | |||||||
|
所在地 | 千代田区皇居東御苑 | |||||
| 科.属など | スイカズラ科スイカズラ属 落葉低木 | ||||||
| 見どころ | 落葉低木で樹高2メートルくらいです。葉腋から長さ1〜2センチの花柄を出して、淡紅色の花を1〜2個下垂します。花径は1〜1.5センチの細い漏斗形で、先端は5裂します。花や実をついばむ姿が神楽を踊っているように見えるためカグラと名付けられました。ミヤマは深山に生えるという意味です。以前私が投稿しましたウグイスカグラ(鶯神楽)との違いは、ウグイスカグラは全体無毛で、ミヤマウグイスカグラ(深山鶯神楽)は腺毛があります。果実は甘くて美味しいそうです。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2011.3.20 | ||||
「とうよこ沿線」TOPへ戻る
野草-World TOPへ戻る
次ページNO.33へ
| 03.茎にトゲがある、ユーフォルビア・ハナキリン(花麒麟) の花 | |||||||
|
所在地 | 横浜市金沢区金沢町212-1 称名寺近くの民家の玄関先 | |||||
| 科.属など | トウダイグサ科ユーフォルビア属 多肉植物 | ||||||
| 見どころ | 茎にトゲのあるトウダイグサ(灯台草)科ユーフォルビア属。耐乾燥・非耐寒性常緑低木で多肉植物です。丸い花のように見えるのは苞です。一般家庭の庭など、比較的どこでも見られます。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.08.11 | ||||
| 14.フランス生まれの年2期咲きで優しい感じの花、エリカ・ホワイトデライトの花 | |||||||
|
所在地 | 東京都文京区白山 3-7-1 小石川植物園 | |||||
| 科.属など | ツツジ科エリカ属 半耐寒性常緑小低木 | ||||||
| 見どころ | この花は樹高は20〜100センチほど。葉は杉のように細い。開花は4月〜5月と9〜12月と年2期咲きです。初めは真っ白な筒状の花を咲かせ時間が経つにつれ、ピンクを帯びてきます。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | |||||
| 06.ムラサキシキブよりも人気がある、コムラサキ(小紫)の実と花 | |||||||
|
所在地 | 川崎市中原区西加瀬210 県公社西加瀬アパートの庭 | |||||
| 科.属など | クマツヅラ科ムラサキシキブ属 落葉低木 | ||||||
| 見どころ |
|
||||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.9.26 | ||||
| 17.「女王様の耳飾」とも呼ばれるアンデスの名花、フクシアの花 和名:釣り浮き草 | |||||||
|
所在地 | 鎌倉市小町2丁目 小町通り商店街のお店の前 植木鉢 | |||||
| 科.属など | アカバナ科フクシア属 常緑低木 | ||||||
| 見どころ | 中央アメリカから南アメリカが原産でアカバナ科の低木。アカバナ科の植物フクシアの花の色にちなんで名づけらたそうです。夏から秋にかけて開花します。 花は下向きに咲き、色はみごとな赤。古代インカで「女王様の耳飾り」と呼ばれたアンデスの名花だそうです。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.10.29 | ||||
| 10.花弁にシワがあり造花のようなルイラ草、ヤナギバルイラソウ(柳葉ルイラ草)の花 | |||||||
|
所在地 | 川崎市中原区井田2丁目 民家の垣根 | |||||
| 科.属など | キツネノマゴ科の非耐寒性小低木 | ||||||
| 見どころ | 草とついているのは小低木で草木植物とみての命名。「ルイラ」はフランスの植物学者、J・リュエルの音読みからと言われています。綺麗な紫色の花が目に入り、バイク走行中に戻って撮影しました。花弁にシワがあり、造花のようです。花は一日花ですが、4月〜10月まで咲いて楽しませてくれます。 | ||||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.10.12 | ||||
| 02.赤く熟した実は食べられる! アカモノ(赤物)の実 別名:イワハゼ | |||||||
|
所在地 | 山形県鶴岡市 月山八合目 弥陀ヶ原湿原 | |||||
| 科.属など | ツツジ科シラタマノキ属 常緑広葉小低木 | ||||||
| 見どころ | 5〜7月に白色の花が咲き、ガクと花の茎は赤褐色の毛が生えるためコントラストが鮮やかです。8月に球形で真っ赤な実が生り、食べると酸味があります。葉は硬く先が尖っているのが特徴です。シラタマノキは「シロモノ」といわれ、この「アカモノ」と比べられます。 | ||||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.08.02 | ||||
| 13.サルトリイバラと同じ仲間、ヤマガシュウ(山何首烏)の実 別名:サイカチバラ | |||||||
|
所在地 | 神奈川県箱根町仙石原817 箱根湿生花園内 | |||||
| 科.属など | ユリ科シオデ属 落葉つる性植物 | ||||||
| 見どころ | 山地に生え、雄雌異株で蔓が木などに巻きついて生長します。サルトリイバラ(猿捕茨)と似ていますが,5本の葉脈が目立つこと(サルトリイバラは 3 脈)、果実が藍黒色に熟すこと(サルトリイバラは赤)などの違いがあります。5〜6 月に黄緑色の小さな花をつけます。 | ||||||
| 撮影者 | 北澤美代子 | 撮影日 | 2010.10.14 | ||||
| 05.真珠のような純白の輝き、コシロシキブ(小白式部)の実 | |||||||
|
所在地 | 横浜市港北区新羽町1578 専念寺境内 | |||||
| 科.属など | クマツヅラ科ムラサキシキブ属 落葉低木 | ||||||
| 見どころ | 紫色のコムラサキの実の色違いかと思ったら、インターネットの花名の先生から「小白式部」と教えてもらいました。純白の実は真珠のような輝き、とても綺麗ですね。やはりコムラサキの仲間だそうです。 | ||||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2010.9.14 | ||||
| 16.花の色が一日で白から赤に変わる、シクンシ(使君子)の花 | |||||||
|
所在地 | 東京都江東区夢の島 3-2 夢の島熱帯植物館内 | |||||
| 科.属など | シクンシ科シクンシ属 | ||||||
| 見どころ | 熱帯アジアの常緑のつる性植物です。高さは3メートルほどになります。長楕円形の葉は対生し、5月〜9月にかけて、枝先の総状花序に5弁花を咲かせます。花は朝の咲き始めは白色で、午後になると赤く変わります。この種子は、漢方で「使君子」と呼ばれ、回虫駆除薬やニコチンの中和剤として使われます。夜になると独特な甘い香りを発します。 | ||||||
| 撮影者 | 石川佐智子 | 撮影日 | 2010.10.19 | ||||
写真をクリックし拡大してご覧ください。
写真を連続して見るには、左上の「戻る」をクリックしてください。